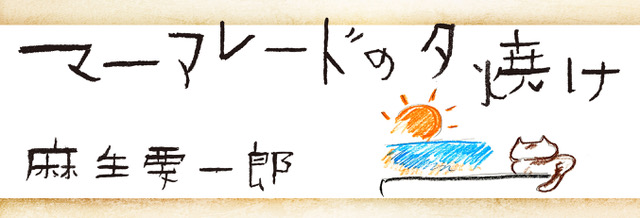第13回 ひと夏を過ごす島の宿
夏の朝は忙しい。
セミの鳴き声とともに、宿泊のお客様が起きてくると、フレンチトーストを焼き始める。コーヒーはオーダーが入る度、ハンドドリップで淹れる。フルーツをたくさん添えた、フレンチトーストが朝食の名物となった。島のベーカリーが焼いている食パンを、卵や牛乳と合わせた液体に一晩浸し、フライパンでバターを溶かしながら、じっくり焼く。よく考えると、なかなか贅沢な朝食であった。
2泊目の人には、食パンをトースト、ヨーグルトに自家製のグラノーラをたっぷりのせて。グラノーラは、ドライフルーツやナッツをスパイスと合わせて、オーブンで焼いていく。最初は朝食のために作っていたけれど、焼いていると甘くスパイシーな香りが外にまで広がり、お土産に欲しいという声も多かったので、パックに詰めて販売も手がけた。
朝ごはんが落ち着いた頃に、スタッフが朝の船や飛行機で着くお客様を迎えに行く。それが済むと皆で食卓を囲んで、その日の予定を確認する。チェックイン、チェックアウト、飛行機、船の送迎。船も海の状況によって港が変わる。確認事項は多くある。だいたい、トーストを焼いて済ませたり、失敗したフレンチトーストを食べたり。忙しい日には、ベーカリーでサンドイッチを買う事も。卵、ツナ、ハム、魚のフライ、コロッケ、たくさん種類があったけれど、僕は野菜サンドが好きだった。きゅうり、トマト、レタスがマヨネーズソースとサンドされていて、ぶつ切りと言っても良い厚みのある野菜は、やや水っぽいのだが、暑い夏の日には水々しく、とても美味しく感じたものだった。
毎年、ゴールデンウィークから、秋までと決めた営業期間。冬場は海が荒れるから、船が着かないこともあり、運行本数も減るので、営業はしなかった。その間は、東京に戻ったり、実家の水戸にいたり、島との二拠点生活を楽しんでいた。僕と、あと2人くらいが毎年入れ替わり手伝ってくれることで、この宿の運営は成立する。マニュアルなんてものは、存在しない。島にまで来て、決まりきった言葉で対応される息苦しさは、する方も、される方も嫌だと思うので。自分自身の言葉と気持ちで、お客様を迎え入れて欲しい。最初は、とにかく全ての仕事の手本を僕が見せていく。自身も、毎年手を動かしながら感覚を取り戻していく。それを少しずつ分担していく、これをやって、あれをやってと指図せず、自然に分け合う。それぞれの性格や仕事の適性を見ながら、得意なことをしてもらう。役に立つという事は、自然に自分の居場所を作ってくれるのだ。その積み重ねで、宿に愛着がわいていく。
午前中は、各部屋の掃除や洗濯もあり、忙しい。僕は、その合間を縫って、スーパーに買い出しに出かける。棚に並ぶ、煮物にすると美味しい金目鯛や、塩焼きにすると絶品の黄色い帯が特徴的なタカベ、他にも鯵や鯖など、島で獲れた魚を買いに行くのは、早いうちに行かないと無くなってしまう。翌朝のパンも必要な数を予約しておき、ベーカリーでピックアップ。お昼ごはんも、のんびり宿内で過ごしたい人向けには提供するし、帰りにお弁当を食べたい人には特別に作っておく。マニュアルがないから、臨機応変、行き当たりばったり仕事は増えていく。夏場は観光客も増えるので、数少ない島の飲食店ではランチ難民が続出。お昼はせいぜい、13時過ぎまでには済ませておかないと、お店は暖簾を下げてしまい、食べ逸れてしまう。我々も、気分転換に、お昼を食べに行った。中華&焼肉のお店、豪快な主人の人柄が好きだった。牛モツ塩ラーメンというのが、僕らのお気に入り。焼肉屋さんだから、新鮮で立派なモツが入っている。それが丼というか、洗面器のような器で出てくる。今だったら量が多くて、2人で1つがせいぜいかも知れないが、暑い中朝から動いているから、しっかり食べてしまう。レバニラ炒めもよく食べたし、刺身定食も美味しかった。忙しい時は、ちょっと手伝ったり、うちのオーダーが間違えて作った定食に変わっていたり、夫婦喧嘩が突然勃発、今思い出しても、面白い。いつも、食後にコーヒーを淹れてくれて、この店を訪れるのは、束の間のよい休憩時間となっていた。夜の焼肉も、本当に美味しかった。全て手作りの料理、山芋のキムチが僕は好きだった。
午後の時間、送迎はあっても、皆は少し休憩、僕は晩ごはんの支度。慣れてくると、お客様を送りながら、綺麗な海が一望できる石山の展望台や、長い砂浜の続く羽伏浦海岸とか、自分の好きな場所や景色を見に行ったりするようになる。慣れてきたなと、僕は安心する。食事も、1泊目、2泊目、3泊目と、メニューを変えないといけないし、アレルギー、ヴィーガンだとか色々な要望もある。台所でせっせと支度をして、夕方になると、きれいな夕焼けが広がる。空が一面オレンジ色、台所の窓からも、その様子が見てとれる、マーマレードの夕焼けが広がる。僕は、その光景が幸せな感じがして好きだった。夕食がはじまると、また大変。焼き魚、刺身、煮魚、とにかくお客様に喜んで欲しい一心で毎日、毎食、作り置きはせずに手間暇をかけた。それが終わると、今度はスタッフの賄い。それぞれの好みを把握して、色々と作る、友人達は、このスタッフルームでの賄いに混ざることが多かった。狭くて、ごちゃごちゃした部屋には、長いテーブルがあり、それを皆で囲む時間はとても幸せだった。皆が片付けをはじめる頃に、宿の予約のメール対応をしようと、パソコンを開く。すると誰かが、気を利かせて、僕にコーヒーを淹れてくれる。星空の下、ジョギングもしていた。一人で音楽を聴きながら海沿いを走る時間は、良い気分転換だった。
夜、眠れずに物思いにふけるお客様がいれば、頼まれてもいないコーヒーやお茶を用意した。スタッフの誰かがお客様と仲良くなって、飲んでいる姿もよくあった。僕が床に就くのは、いつも日付が変わってしばらくした頃である。ふすま一枚の仕切り、夜中にお客様の足音が聞こえると、何かあったのかなと心配になるし、物音にも敏感になった。眠りが浅いのは、そのせいかも知れない。
一体、何人のスタッフが手伝ってくれたのだろうか。そのシーズンずっとではなく、夏の一番忙しい時のお手伝いとか、色々な関わり方があった。すっかり会っていない子もいれば、よく連絡をする子もいる。スタッフ同士が仲良くなって、今でも交流しているという事もある、嬉しいことだ。いつも僕はこう考えていた、働き者のお母さん(僕)が営む、島の宿。毎年、親戚の子供達が手伝いに来る。そう、従業員ではないのだ。忙しくても、自由にのびのび人生の夏休み、責任をとるような場面があれば、僕がきちんと責任をとった。誰かの、たまの寝坊は、叱ったりせず寝かしておく。特殊な技能よりも、その人が持つ人間性を重視、採用していた。そうでなければ、夏の間、一緒に寝泊まりして宿を切り盛りすることなんてことは、絶対に出来なかったと思う。
ひと夏、東京の暮らしを諦めて、島へ行くのだから、当然ながら個性的な面々が多かった。3.11 の震災があった年のこと、もうメンバーは揃っていたけれど、働きたいという青年からのメールがあった。連絡をもらった日、僕はたまたま都心にいて、熱意ある文章に心打たれたので会う事にした。夕方時間があると伝えると、バイトをしていて夜にならないと時間が出来ないと返事が来た。生憎、夜は打ち合わせを兼ねた食事の予定があり、明日にしようか?と言うと、今夜良ければ会いたいと言う。僕の食事の場所は代々木、しかし確実な時間が分からないので、終わったら連絡すると伝えると、代々木で待っていると言う。確かに、タイミングを逃さないことは大事だと思いながら、忠犬ハチ公でもあるまいしと、彼が待っている場所まで出向こうと思い、連絡すると30秒もかからずに自転車で現れたので驚いた。お茶をして、僕はすっかり彼が気に入って、島に帰るタイミングに良かったら一緒に行く?と言うと、彼は素直に応じた。竹芝桟橋に朝の8時くらいの待ち合わせ、若者には辛いかなあ、起きられたかなあと心配しながら行くと、彼はもう既に到着していたので感心した。そして、驚愕の発言を耳にする。彼は下北沢に住んでいるのだが、夜に眠れなくて竹芝桟橋まで、歩いて来たのだと言う、まるで青春映画のようだと思った。天気の良い日で、海面がきらきら眩しかった、静かに隣に座った彼の瞳もきらきらとしていた。
彼は期待に応えてよく働いた、厳しい写真家のアシスタントで鍛えられていたのだと思う。質問などせずに、僕のやる事をよく観察して、自分で考え行動。合間に本を読んで、感動したような場所に付箋を貼って書き写していた。とにかく、何もかもが素晴らしかった。僕は、この子が成功しなかったら、世の中が間違っていると、根拠もなく思った。とにかく彼が、手応えを感じる人生を歩めるように願った。誰よりも早く起きていた彼が、卒業したあと、約束の時間に寝坊して遅刻してきた。僕は、その事が本当に嬉しかった。あの夏、彼は本当に頑張ったのだと、感じたから。その後、写真家として活躍。雑誌でも名前を目にするようになった頃、彼はあっさりと海外へ行った。大丈夫なのかと少し心配したが、タフな彼は力をつけて帰国。写真の事はよく分からないから、上手く褒めてあげられない事が口惜しいが、ぶれずに自分の写真を撮り続けて、作家としてきちんと評価されている事が嬉しい。先日も食事会の席でたまたま顔を合わせると、良きパートナーにも恵まれて、あの時と変わらぬ、きらきらした瞳を見せてくれたので、僕は安心した。
ここを手伝ってくれた一人一人とのエピソードは、僕の大切な宝物。島に来た時よりも、帰る時の方が良い顔をしていた。シーズンが終わり島の友人に見送られて、それぞれが涙した。絵に描いたような男泣き、目を真っ赤にして涙を堪える人、もらい泣き、クールに、笑顔で、それぞれの個性がよく現れていた。成長したのは、本人の努力と、こうした人との関係性。僕はただ、ひと夏の間、そのままでいいよと、背中をそっとさすっただけ。宿が閉まって、もう9年も経つ。皆、それぞれに活躍をしている。ひと夏を島の宿で一緒に過ごしたこと、マーマレード色に海と空が染まる、そんな夕焼けを屋上から眺めた時間、毎日一緒に食卓を囲んだ情景が、人生に寄り添う優しい力となる事を、僕は願っている。あの場所はもう存在しないけれど、長い人生の中で、そういう時間がまた再び必要と感じたとき、あの夏の日と同じように、食卓をまた一緒に囲みたいと思っている。
僕はいつでも待っている、ずっとずっと。