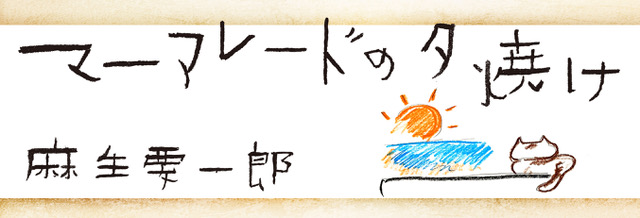第8回 銀座の情景
銀座という街には、特別な思い入れがある。子供の頃から母に手を引かれて特別な日に買い物へ出かけたのは、銀座だった。アスターで飲茶のワゴンが行き交う中で食べたお昼ごはんはとても新鮮で、煉瓦亭や木村家本店の3階にあるグリルで食べた洋食が美味しかった事をよく覚えている。当時、晴海通り沿いにあった、洋書を扱うイエナ書店、一般書籍を販売する近藤書店で本を買ってもらった。今はなきソニービルの地下、ソニープラザでは珍しい海外のお菓子をねだった。建て替え前の質実なる伊東屋を覗く事も楽しく、買い物をすると貰えるメルシー券は子供にとって金額以上に大切なもののように思えた。マリアージュフレールでは、ランチやケーキを楽しみ、たくさんある紅茶の種類から、選ぶのはボレロ。アイスティーを頼むとふくよかなワイングラスで供され、上質な紙のストローがそえられ、より一層贅沢な味わいが楽しめた。この街の思い出を振り返れば、キリがない。
今でも、煉瓦亭には洋食を食べに出かけるし、木村家の銀座本店だけで販売されている、酒種酵母の甘い香りがするやわらかな食感のコッペパンは卵サンドにすると絶品である。散策の合間に、佇まいの良い教文館で書籍を選んでから、シネスイッチの隣にある凛でコーヒーを飲む。教文館に自分の本が並んだ時、とても嬉しかった。好きな書店に並ぶ自分の本を眺めるというのは、格別である。打ち合わせでもよく訪れる、泰明小学校の前にあるオーバカナル。季節毎に変わるパフェが楽しみな、和光ティーサロン。母ともよく食べた、ウェストの大きなシュークリーム。肉料理の聖地のような、マルディグラ。銀座の街も刻々と変化しているけれど、まだまだ善き時代の大人の街としての面影はしっかり残っている。現在進行形で、この街への思いについても書き上げれば、キリがない。
松屋の裏手、野花を扱う花屋の路地奥に「はち巻 岡田」と提灯が下がっている。何の店だろうと、何度か通り過ぎていたが、ある時パートナーと思い切って暖簾をくぐった。岡田茶わん(鶏のスープ)、粟麩田楽、刺身などを一通りいただく。店内に飾られた、山口瞳の直筆の原稿、値段の記しがないお品書きの美しい文字、とても静かな店内、年齢だけは十分に大人だけど、改めて大人の仲間入りをしたような、そんな気持ちになった。養親の姉から、銀座の思い出話を聞いていた時に、たまたまこの店の話が出て来た。それは、養親の妹がまだ子供の頃、父親の大井広介に連れられて銀座へ出かけた時、この店を訪れて、綺麗な薄作りを箸でつまんで目元にひらひらさせながら片目を瞑り「パパが見えるー」とやったそう。行儀が悪いと叱られ、恥ずかしくてしばらく行けないと嘆いていたそうだ。そして、山口瞳の話になり、サントリーにいた頃、佐治敬三からの使者として当家へウイスキーをよく届けてくれたそうだ。そして、同社が刊行していた懐かしき「洋酒マメ天国」(全36冊)を、書庫から引っ張り出してくれた。全体的に少し傷んでいたが、全巻揃っていた。当時はまだ、ウィスキーの花形は海外産、少しでもサントリーのウィスキーを広めようという意味で、色々な努力を積み重ねた結果が今に繋がっているのだろう。「山口さんはよくいらしてね、パパと楽しそうに話していたわよ」と姉は懐かしそうに、機嫌良く話していた。
刺身をひらひらとさせて叱られた幼かった妹が、もう少し大きくなって学生の頃の話。友人と一緒に当時流行のミニスカートを穿いて銀座を歩いていた時、大井を見つけて「パパー」と走り寄ると、スーツ姿でハットを被りステッキを持った大井は、一瞥すると無言でその場を立ち去ったそうである。何で無視されたのか分からぬ彼女が家に帰ると、書斎に呼ばれて「銀座という街をあんな格好で歩くものじゃない」と諭されたそうである。その時、大井の側には矮鶏(チャボ)がいて、意地悪そうな顔でこちらを見ていたとは、妹の話。考えてみれば、もう今から70年くらい前の話、今は何を着て出かけても自由である。その話の是非はともかく、銀座という街の当時の面影が垣間見える話だと思う。その話が頭の片隅に残っているので、銀座へ出かける時には、それなりに気を使って出かけるようにしている。ちなみに、矮鶏が家の中にいるのには訳がある。山間に暮らしていた友人が、お土産にと矮鶏を抱えてきたそうで、本人は新鮮なお肉を食べさせたいという意図だったそうなのだが、大井は「僕は食べないよ、この子は賢いからね」と、そのまま飼う事にしたのだとか。命を救われた矮鶏は大井に忠誠を誓い、大井以外には好戦的だったそうである。大井は動物には、とにかく優しかったと言っていた。その血は、姉妹にも受け継がれており、当家には数々の犬、猫、カメレオン、鳥、そして山羊までいたそうだ。時代が違うとはいえ、都心の個人宅で山羊を飼っていたというのは、うちぐらいなのではないだろうか。
大井は、61歳の若さで患って亡くなったが、最後の入院生活を送っている時に、飯田橋にある病院から、夕食時になるとガウンを引っ掛けて、当たり前のようにタクシーへ乗り込むと銀座へ向かう。ある日は河豚を食べ、ある日は寿司を食べて、また病院へ帰るのだとか。娘達と他の病室を一緒に覗いては「いいか、病院というところは、病気ではなくて、皆飢えて死んで行くのだ、ほら見てみろあの食事を!」と、大真面目な顔をして語っていたそう。さすがに毎晩の銀座通いを医師に咎められると「分かりました」と素直に応じたと思ったら、その夜からは、馴染みの店が重箱を抱えて出前に来たそうで、他の患者さんにもお裾分け、まだ大らかな時代だったのだと思う。戦前から馴染みだった河豚屋は無くなったようだが、寿司屋の方はまだ銀座の街に健在である。銀座寿司幸本店、丸ビルにある支店へは出かけた事があるが、本店にはまだ出かけていない。なんとなく大井に、君にはまだ早いと言われそうな気がして遠慮している。もう少し、自分の中で手応えのある事があった時に、記念として出かけたい。葬式不要、戒名不要と、言った大井の葬式は行わず、当時はまだ珍しかった、お別れ会が開催された。文芸評論に加え野球評論もしていたので、文壇、球界から、たくさんの方が駆けつけた。球団の関係者はまとまりが良いのだが、文壇や評論家達は、当時は思想も色濃い時代で、無用な口論が起きぬよう配慮して思想により左右に分けて座ったそうである。姉妹達に代わり、親交が深かった松田政男氏(評論家)が、座る位置の割り振りをしたそうであった。お経をあげる訳でもなく、ただ酒を酌み交わすような席であったが、そこへ田中清玄氏が颯爽と現れて、迫力ある般若心経を唱えたそうだ。そのめちゃくちゃな感じ、坂口安吾曰くデタラメな感じが、大井の魅力だと僕は思っている。
養親の姉妹は、大井が健在の頃に、銀座でお店をやっていた事がある。お店の近くには、まだ1店舗だけだった銀座コージーコーナーがあり、前を通ると新作のケーキを出されて「今度こういう商品を出そうと思うんだけど、どうかな?」と、相談されたとか。その話は、たまたま知り合いからコージーコーナーのエクレアをいただいて一緒に食べていた時に、ふと思い出してくれたのだった。「あのおじちゃん元気かなあ?」と、姉は当時の心境で小さく呟いていた。お店の名前をすっかり失念してしまったのだが、銀座8丁目の辺りに文士達にも人気の「タンシチュー」が美味しいお店があったとか。姉の好物はタンシチューなので、よく通っていると、店主が高齢になってきて、自分の代で店を閉めようかという話をされ「もし、あなたがこの店、引き受けてくれたら良いんだけどなあ」と言われたそうだ。それがどの程度に本気の話だったかは、今となっては知る由もないが、厨房にも招き入れて作り方をきちんと教えてくれたのだとか。「私も当時はモテモテだったし、夜の銀座が楽しかったから、話を流しちゃったけど、私があの時、お店を継ぐって言っていたら、あなたにタンシチューのお店残してあげられたのよねえ」と言いながら、本当に残念そうな顔で煙草を燻らせていた。その店のご主人仕込みかは知らないが、姉は何度も僕にタンシチューを作ってくれた。牛すじと香味野菜でベースのスープを作って、タンを入れて煮込み、何日かかけて仕上げていた。寸胴鍋いっぱいに仕上がるが、本人は作るだけ、食べるお客さんは僕一人。美味しいけれど、食べるのが大変で、それはまるで修行のようだった。そのシチューには、街の情景、誰かの背中の記憶、様々な思い出が詰まっていた。時折、鍋底が焦げている時があり、それもまた人生の味わいだと、受け止めていた。時に人生とは、苦々しいものである。伝統ある料理屋を受け継ぐというのは、大変な事。受け継がなくて、良かったと思っている。だけど、こうしてその味を僕へ繋いでくれた事に、とても感謝している。今は手に入りやすくなったコージーコーナーのエクレアも、思い出深いお菓子となった。一口食べると、ふと思い出す、銀座の情景、食べ物は深い記憶を繋ぎ止めておくものだと知った。
今度、時間をかけてタンシチューを煮込んでみようと思う。そして、その味をまた誰かに伝えよう。僕の人生の思い出とともに。
銀座が繋いでくれた思い出の味。