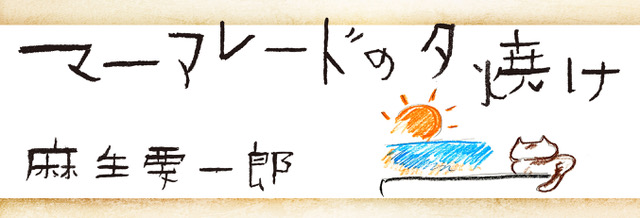第5回 「トアロードのデリカテッセン」
僕の養親の姉妹は、思い付いた事を主語もなく、唐突に話しはじめるので、いつも話の内容を理解するのに時間がかかった。どこかへ旅行した話、誰かとのちょっとした思い出、それもまるで先週の出来事のように、平気で60年くらい前の話をする。子供の頃に、父親に連れられ神戸へ出かけ、フロインドリーブでパンを買ってから、トアロードを歩いてデリカテッセンに行ってハムを買って「商店街の福引で特賞の七面鳥が当たったんだけどね、他所から来たのが特賞持っていったら悪いからねえ、辞退したのよ」なんていう話をしてくれた事があった。前後にもう少しストーリーがあったような気もするが「トアロードのデリカテッセン」という響きが印象に残っていた。
このマンションに引っ越して来て、姉妹の養子になる少し前、初めて一緒に買い物に出かけたのは、麻布のニッシン(日進ワールドデリカテッセン)と広尾のフロインドリーブだった。出会った頃も、十分におばあちゃんと呼べる年齢だったけれど、二人にはそう言わせない独特のオーラがあった。お化粧は舞台に出るのかと思う程にきっちり、時代がかったカールラガーフェルドとかジョルジオアルマーニの服を纏い、大きなサングラスをかけ、重ためな香水をぶっかけるようにして(上品にシュッではない)、時にはエルメスのスカーフをまちこまき。一緒に街に出ると、古き良き時代のファッション写真の切り抜きが、現代にコラージュされていくような感覚に陥る。ニッシンのチーズ売り場で、「こんなのすぐ食べちゃうわよねえ」と言いながら、一番大きな円形の箱に入ったブリーチーズを買っているのを見て驚いた。僕にも、肉の塊を豪快に一本、カートを山盛りにした挙句、園芸コーナーでレモンの実が幾つか実っているレモンの木も買ってくれた。その後、フロインドリーブに寄って、チーズケーキのホール、パン、クッキー、僕が小さいシュトーレンを選ぼうとすると「もっと大きなの買いなさいよ」と言われて、一番大きなバットみたいなサイズのシュトーレンを買ってもらったのも、つい先日のように鮮明に覚えている。その時、フロインドリーブのおばさんと親しげに会話をしていた。東京にお店が出来る前に、神戸の主人から「若いものが東京にお店を出すのでよろしくお願いします」と頼まれたと言っていた。姉妹は、まだ新しく出来たお店を僕に紹介するような感覚で話してくれたが、現実はもっとしっかりとした時を刻んでいて、高齢化を理由に広尾のお店は閉じられた。その時に、フロインドリーブは神戸に本店がある事を知った。姉妹が家で常用していたお菓子、モロゾフやユーハイム、それも神戸が本店だという事を認識したのは、その頃である。ケータリングの仕事で大皿が必要だという話をした時、彼女達は真剣に考えた後に、洋皿ならば神戸のあたりに探しに行くと良いわね!と、言っていた。大筋では合っているのかも知れないが、ちょっとズレてる感じもする。どことなく、時間や時代が止まっている、本人達には言えないけれど、いつもそういう感じがあった。
介護が忙しかった事もあり、京都くらいまでは行けたとしても、神戸まではなかなか行けなかった。愛猫チョビもいるので、大体のところへは日帰りで行くと決めている。友人が芦屋に書店を出したので、お祝いを兼ねて姉妹の思い出を辿る旅へ家人と出かける事にした。旅のお供に選んだガイドブックは「神戸の味」(カラーブックス・昭和49年)、随分前の本なので、役に立たない事は理解しているが、少し前の視点で旅をしてみたかった。姉妹の会話から耳にした店をガイドブックから見つけて、インターネットで検索するという根気のいる作業を繰り返し、行きたい場所をノートに書き写した。日帰りなので、お昼は一回、夕食一回、お茶をするにしても何にしても、時間的な制約がある。新幹線は思ったより混雑していて、家人とはバラバラに座った。到着すると、新神戸駅から歩いてフロインドリーブへと向かう。彼女達が行っていたのは、神戸の震災前の店舗で、現在は移転して教会の建物を利用した趣のある佇まいが“映える”と人気、到着後のコーヒーをここでと気軽に考えていたら、それは甘かった。店の外まで、2階のカフェスペースから行列が続いていた。早々にコーヒーを飲む事は諦めて、1階の売店で、シュトーレンやパン、焼き菓子を購入した。真っ白な空間はどこか現代的で、想像していた雰囲気とは違ったが、広尾店の印象をもとに、かつての姿を思い浮かべながら店を後にした。
お昼は、知人に教えてもらった中華料理のお店で食べようと、歩いて向かう。普段の暮らしでは徒歩15分とグーグルマップに出た途端、タクシーを捕まえたくなるが、旅先では散策を兼ねて歩きたくなる。トアロード沿いの「施家菜 點心坊」というお店、その名の通り點心が美味しく、大根餅も美味だと教えられる。季節のおすすめメニューに、ご当地の名物である明石のタコを活かした「タコ焼売」というメニューもあった。食べ過ぎないよう気をつけながら、オーダーをした。カリカリに皮を焼いた豚バラ肉、食感の良いタコ焼売、上海蟹の味噌が入った春巻き、大根餅、海老ワンタン麺、デザートにタピオカの入ったマンゴースープ。ワゴンで運ばれてくる感じも、香港を旅しているような風情があった。トアロードの雰囲気も、どこか異国情緒を感じるような佇まいのお店や建物が並んでいる。歩いて三宮駅を目指す道すがら、トアロードのデリカテッセンに立ち寄る。お店の佇まい、店名のフォント、今の時代には出せない良さがある。とうとう来たという思いで、車道を挟んだ反対側からよく眺めてから、お店に入る。入り口のワゴンには、ハムやサーモンを使ったサンドイッチが並んでいた。ショーケースには、ずらりとハムやテリーヌが並ぶ。物珍しい様子で眺める僕と家人が何を選ぼうか迷っているうちに、「いつものハム、スライスして」そんな感じで、馴染みのご年配のお客様が入れ替わり立ち替わり次々にやって来る。お店とお客様の信頼関係がしっかり築かれている事が垣間見えるやり取りを、嬉しい気持ちで眺めた。切り落としのハムを何種類か選び、姉妹の会話の中だけで聞いていたお店が、今も地元の人々に愛されて、同じ場所に健在である事がわかり、とても嬉しい気持ちでお店を後にした。
今回の目的地、芦屋にオープンした友人の書店「R-books」はJRの芦屋駅から、すぐの桜並木沿いにあった。大きな窓、そして低めにつくられた本棚の前に置かれた小さな椅子。遠慮がちに腰を屈めて本棚を眺めていたのを、小さな椅子に座ってみると、本を選ぶのに丁度良い高さなのが分かった。たくさんの本の中から、幸田文の『しつけ帖』を選んだ。また桜の綺麗な頃の再訪を誓い、阪神本線の芦屋駅へ向かう。駅前のパン屋とスーパーに寄って、電車を待った。駅のホームから眺める、芦屋川がきれいだった。通学の高校生を眺めながら、この街に暮らすイメージを膨らませた。ちょっとの間、神戸に暮らしてみたい気持ちになった。元町に戻って、散策中に今日が休みだと思っていた、「エビアン」(喫茶店)の前を通ったのでコーヒーを飲んだ。BGMが流れていない無音、蛍光灯の灯り、昔ながらの濃い目のコーヒー、家人は近所の古本屋を見に行ったので、珈琲を飲みながらぼんやりと一人で過ごす。こういう喫茶店が街に根付いて残っているのは、関西の魅力の一つだなあと思う。東京の喫茶店とは、佇まいがどことなく違う。
旅に出かけると、スーパーや百貨店の地下へ行くのが好きである。買わずとも、その土地の暮らしを垣間見える感じが楽しい。阪急の地下へ寄ると、和菓子屋さんで、老紳士にお店の方が「お元気でしたか?お久しぶりですねえ?」と声をかけると、おっとりとした感じの関西弁で応じていた。同じ状況では、東京だともう少しピリッとした感じになるし、お互いに急いでいる感になってしまう。その前の洋菓子店でも「もうこれ売り切れたんかいな?」「今日はお客さんいっぱいで、早かったですねえ」というような会話をしていたのだが、これも東京だと、もうちょっとクレーム的なやりとりに発展しそうな感じがした。どこか、おっとりしている、人々のトーンも、街の空気も。東京という街の忙しさ、息苦しさに、慣れているけれど、ちょっと疲れているのかも知れないと思った。そして、神戸も東京の百貨店も、洋菓子店の顔ぶれはあまり変わらないけれど、そのほとんどは神戸が本店という事を改めて思い知っては感心し、ありがたみすら感じてしまう。
日帰りなので、のんびりはしていられない。早めの夕食は、知人に教わった「蛸の壺」という明石焼きのお店に出かけた。明石焼きを中心に蛸と、中華のエッセンスも交えたお店。歴史を感じる懐かしく安心感のある佇まい、大きなテーブルの右端の席に案内される、左の端ではご婦人方の会合が開かれている。神戸らしいなと思ったのは、その中にシスターがいらした事である。明石焼きを口に入れながら、聞かずとも聞こえてしまう会話が耳に入る。シスターは学校の先生、周りを囲んでいるのは随分昔の教え子達という関係性のようだった。ベールを被ったシスターが、焼酎を呑んで、明石焼をつつきながら、昔話に花を咲かせ、頬杖をついて関西弁でくだをまいていた。帰り際、さっきまでとは声のトーンを変えてお店の方に、丁寧にお礼を伝えていた。明石焼きの味が記憶に残らない程、シスターの様子に釘付けになっていた。一部始終が、昭和のホームドラマを見ているような感覚で心地良かった。
気が付けば電車の時間が迫っていた、乗り遅れては一大事、タクシーで新神戸の駅へと向かう。新幹線乗り場の側の土産物店はまだ親切に開いていて、売れ残っていた「赤福」を買った。赤福は家人の好物、12個入り、8個入り、どちらを何個買うかで悩んでいる。結果、お菓子を他にもたくさん買ったので、12個入りを1箱という事で決着が付いた。翌日の午前中に打ち合わせをする編集者への手土産に8個入りも一緒に購入して、家路を辿る。最終の新幹線、家に着いたのは24時を過ぎた頃。玄関のドアを開けると、愛猫チョビが切ない声で出迎えてくれた。トイレを交換し、ごはんを用意、擦り寄せてくる頭を撫でる。ほっとして、お茶を飲みながら、赤福の蓋を開け、1個食べて、家人も1個。明日も早いからとベッドでチョビを抱えて眠りについた。
翌朝、目覚めると、赤福はすっかり空箱になっていた。エビアンのコーヒー豆、フロインドリーブのパンで朝食の支度をする。旅の思い出を、日常に折り返していくのが、僕にとっては何よりの幸せである。またどこかへ短い旅に出たい。