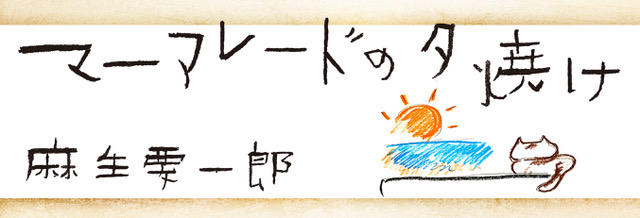第9回 桜の花が咲くころに
桜の季節になると、普段は静かな我が家の周りは、新宿御苑へと向かう人の列で賑わう。花見にまつわる思い出は、人それぞれあるだろうが、僕は敷物を敷いて、お弁当持って、皆で桜の木の下で宴をするような花見を実はあまりした事がない。
何年か前、お重に唐揚げや卵焼き、おにぎりを詰めて、ワインを抱え、仕事終わりのパートナーと西麻布の公園で夜の花見をした。小さな児童公園に咲いた夜桜を愛でながら食べるお弁当は、なかなか風情があった。その近く、青山墓地の桜も綺麗。どこかへ、わざわざ見に行くよりも、日常の中で出会う桜が僕は好きである。歩いていて偶然通りかかった道沿いや、車窓から人混みと少し離れて眺めるというのが良い。特に東京はそういう、見どころが多いように感じる。しかし、桜の花を見上げる時、僕は亡くなった母を思い出す。
母の乳がんの再発が見つかったのは、今から9年程前の年の瀬。呼吸が苦しく内科へ行くと、胸水が溜まっているから、このまま大きな病院で検査を受けるようにと医師に言われたのがきっかけ。手術をしてから、もう15年も経っての事であった。その時、僕は友人のお店の立ち上げを手伝っていて、年末年始にも帰れずにいた。母は忙しいからと僕に気を遣い、何も告げずにいた。年が明け、少し経ってから来た連絡は「チョビ(猫)を少しの間、預かってくれない?」という内容だった。母が可愛がっている、チョビを預けてどこか旅行へ行くなんて事は、絶対にあり得ない。不審に思いながら大丈夫だよ、と伝えるが、LINEの返事はなかった。成人の日を過ぎた頃、母から電話があった。「今から…そっちへ…車でチョビを、連れて…行くから…」母の呼吸が乱れている。どうしたのと確認すると、口籠りながら「私ね…癌が、再発したの…だから入院しないといけないから、チョビの事だけお願いしたいの」そう言った。僕はびっくりして、一瞬返事ができなかった。車で水戸から黒磯までは2時間以上かかる。呼吸も苦しいというのに、行かないといけないのは僕だよ、そう思った。「水戸に帰るよ」と伝えると、電話の向こうで気丈な母が涙をこぼした。「ごめんね、大事な時に邪魔してごめんね」そう言っていた、自分が辛くて泣いているんじゃない、僕の事を思って泣いていた。
母の好きな、パンとコーヒー豆を買って、急いで帰る支度をした。僕がいない間、きっと母はたくさんチョビに話しただろうなと、帰り道に思った。母がお風呂に入ればチョビはバスタブの蓋の上に寝ていたし、トイレに行けばトイレの前で待っていた。きっと、チョビの事だから、母をしっかり支えてくれたに違いない。家に着くと、玄関で待っていたのはチョビだった。大変だったんだよ、そういう表情で。母は少し痩せたような気もしたけれど、手術をしたら治ると、僕は思っていた。しかし翌朝、母が好きなコーヒーとパンで朝食をと思った時に「ごめんね、コーヒーとパン、今は無理なのよ」と言い、おかゆを食べていた。えっ、と手が止まる。前に入院した時は、病院までコーヒーとパンを毎日差し入れしたのにな、身体の変化や病気の重さを心配したが、それでもまだ手術をすれば治ると信じていた。病院へ一緒に行くと、主治医から簡単な説明があった。母は車椅子でレントゲンを撮りに行き、僕が椅子に座っていると、ドラマのように、また先生に呼ばれた。「単刀直入に言います、お母様にはまだ可能性としか伝えていませんが、乳がんの再発です。リンパ、脳、骨、肝臓にも転移、胸水も溜まっていて、抗がん剤をしても副作用の方が強く出てしまうし、手術も同様です。余命は長くて半年、もっと早いと覚悟していて下さい。今後についてご本人様にどう伝えるか、ご相談させて下さい。」そう言われて呆然としたが、いくら精神力が強くても、そんな事実を告げられては希望がない。そこで、胸水の様子を見ながら体調を回復させてから、抗がん剤等の治療をするという、やんわりとした告知の方針を決めた。きっと、誰よりも、母自身が体を通してその事実を把握していただろうけど。
薬を投与して様子を見るが減らない胸水、先生と相談、本人は苦しいのはもう嫌だと言う、リスクはあるが胸水をひくと、すぐに黄疸の症状が出た。美人な母、辛いだろうなあと思ったが、鏡を見ても表情ひとつ変えずに身支度をする様子は、本当に強さを感じた。病院で一カ月くらい過ごした時、母は「やる事がなければ、もう私は家に帰ります」先生にきっばり伝えた。本人の強い意志に、先生も折れた。「あとは私一人で大丈夫だから、あなたも元の生活に戻ってね」と言うが、そんなわけには行かない。家で待っているチョビは毎日、窓から外を眺めていた、母の帰りを待つように。母は久しぶりに自分の家に戻った。チョビは嬉しそうに、お腹の脇にピッタリくっついて、母の顔をじっと見つめている。「私が苦しそうにしていた時、顔を覗き込んでねぇ…」、撫でながらそう話していた。そこから自宅での闘病になったが、気分が良い日には一緒に出かける事も出来た。無理をせず静かに過ごした。夜、母が寝室に向かうと、チョビはニャァニャァ言いながら心配そうについて行く。母が眠りにつくのを見守って、しばらくするとリビングで仕事をしている僕のもとへ来て、早く寝なさいと言わんばかりにリビングのドアの前に座る。片付けはじめると階段の下へ移動しニャアと鳴く、洗面所へ行って歯磨きをしていると階段の踊り場でまたニャアと鳴き、ベッドに入ると僕の胸元付近にどっしりと乗り、ちゃんと寝るんだよと言わんばかり。夜中に母の寝室、僕の寝室を行き来している、心配なのだろう。朝も、ちゃんと起こしてくれた。
一日一日、小説が終わりに近づくかのように、何かが小さく終わって行く感じがあった。一緒に過ごしていると、それがショックだとか、悲しいとかじゃなくて、その事を受け止める以外に仕方がない、もうよく頑張ったよ、そんな感じになる。ある時、買い物に出ていたら、母から意味がよく分からないLINEが来た。心配になり、電話をすると「間違えたの、ごめん」と言うが、その後のLINEは既読にならなかった。帰宅すると母はソファーに座って、夕方のニュース番組を見ていたが、様子が変である。何も聞かず、様子を伺っていると、エアコンのリモコンをいじっているが手元ではなく、本体の光る部分を見ていた。ひょっとすると、目が見えないという程ではないが、焦点が合わないような、そんな感じなのだろうかと悟った。「ちょっと暖房暑いよね」と言って、僕はエアコンの電源を切った。しばらくして、母はトイレへ立ったのだが、その様子から目はあまり見えていない感じもした。介助しようとするが、大丈夫と言われたので、何かあったら支えられるような位置にずっといたが、しばらくすると母は自分でベッドへ戻った。おそらく、ベッドから扉まで何歩、そこからトイレまで何歩というのを事前に確かめていたのだろう。何かの症状が進んだことは確かだが、念のため病院へ行くか確認すると首を横に振った。翌日、朝から母は呼びかけると目を開けるが、そうでない時はほとんど寝ていた。水分くらいはと思うが、要らないというので、濡れたタオルで口元をふいた。ひょっとすると、時が来たのかもしれないと覚悟した。チョビは母にぴったりくっついていた、母の手は、力なくチョビの額の辺りに置かれていた。最後、母に届いていたのは、チョビのぬくもりである。その日はどこへも出かけず、側にいた。僕は親孝行に思われがちだけど、好き勝手を繰り返して来た、愚息である。その事を、枕元で詫びた。夜になり、母が目を開けた、いつもの表情で、僕の目をしっかり見つめて「私は大丈夫だから、もう休みなさい」と。チョビとしばらく、感謝の気持ちを伝えて、さよならかもしれないが、母の意思を尊重して寝室へ戻る。ベッドでチョビと、落ち着かない夜を過ごした、何度か様子を見に行くと、寝息が聞こえるから大丈夫、そう安心して気が抜けて僕らが寝てしまった明け方、母は亡くなった。今、思えば母は渾身の力を振り絞って、僕に最後の言葉を残してくれたのだ。
自宅で亡くなったので、警察の現場検証が入った。人の出入りが多くなるからと、チョビを僕の寝室で待たせていた。現場検証をして、僕が事情聴取を受けていた時、2階からドン、ドンと大きな音がする。現場は当然ザワザワとした空気になり、捜査員の方に猫が…と伝えると、じゃあ上の部屋で話を伺いましょうと親切に移動してくれた。ドアを開けると、チョビがちょっと怒ったように「ニャアーッ!」と鳴いた、ごめんねと抱っこすると、捜査員の方が「偉いねえ、お利口さんだねえ」と撫でてくれた。さっきの音はドアを開けよう、いや突き破ろうと、体当たりをしたのだ。そうだよね、これから2人で頑張るんだもんね。チョビを抱っこして、僕は再び聴取の続きを受けた。それが終わると自宅に、僕の友人達が続々と集まってくれた。東京からの友人も、仕事を休んで泊まりがけで支えてくれた。それまで、チョビと僕の二人三脚の日々だったけれど、こんなにたくさんの友人が、僕にはいたのかととても心強く思った。葬儀の日、斎場へ向かう道沿いの桜川の土手には延々と、満開の桜が咲いていた。誰もが、その桜の美しさに目を奪われた。僕の母は、若い時に化粧品会社のキャンペーンガールをした事もあり、その印象は変わらず綺麗な人だった。いつも凛として、花や動物が好きな人だった。戒名は、親しくしていた御住職が、麗しさに恵まれたと称し「麗恵院」と授かった。この桜は母が咲かせてくれたんだなあと思って眺めていると、皆が口々に同じ事を言ってくれたので、嬉しかった。葬儀を終えて外に出ると、しとしと雨が降っていた。帰り道に、桜の絨毯が敷かれていたのは、恐らく母の粋な演出である。桜の花を介して、ちゃんと見守っているわよと伝えてくれたような気がした。愛猫チョビは、四十九日まで遺骨の側を離れようとしなかった、人間には分からない、何か気配がそこにあったのだと思う。
桜の花が開花すると、そんな事を思い返し、母に感謝の気持ちを伝えている。それが、僕の桜にまつわる思い出である。