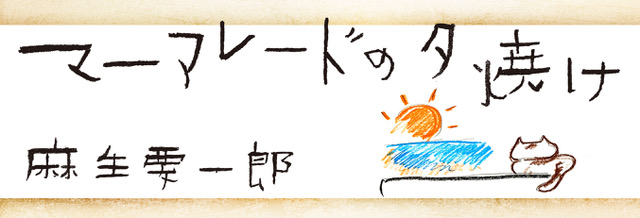第2回 マーマレードの夕焼け
今のマンションに越してきて、7年が過ぎた。
7年前の春まで、母一人、子一人、猫一匹という我が家であったが、母がもう15年も経った乳癌の再発により3ヶ月の短い闘病期間で急逝してしまった。猫のチョビを抱えて、実家にいたところでやる事はないし、地方都市の暮らしは自由に生きたいものには、窮屈であり、友人の多い東京へ戻ろうかと考えていた。しかし、明るく前向きな気持ちではない引越しでは、どこに住みたいのかさっぱり決まらず、さてどうしたものかと思っていた時、お告げをくれる友人に引っ越し先について尋ねると「北参道、千駄ヶ谷、窓が多く、線路に近い場所、古いマンション」と言われた。その3年くらい前だろうか、初めてお告げをくれた時に彼女はこう言った「あなたは、北参道、千駄ヶ谷に縁がある…それはお店をやるとか、そういう事じゃなくて、縁があるのよ、覚えておいてね」その事を急に思い出した、最初から言われていたんだった。
いざ物件を探し始めると、なかなかピンとくる物件がなかった。母の四十九日の辺りまでは、チョビはずっとお骨の側にいて、引っ越しにも乗り気ではなかった。ある日、出かけようとすると玄関に猫のおしっこの匂いがした。しかしどこも濡れていないので、気のせいなのかなあと思っていたら、出かける前に用意していた靴の中に、チョビのおしっこがしてあった。玄関先にはいくつか靴があったけれど、その中でも一番良い靴にしたのだ、目利きである。小さな身体で、強固な意思表示、そちらの都合で強行に引っ越しを進めるならば、報復行動に出るとの警告である。
それからチョビと、引っ越しの事、これからの事を、毎日きちんと話し合った。少しずつ理解してくれたようであったが、肝心の部屋が見つからない。疑う訳ではないけれど、彼女に再び連絡すると「◯日以降に、必ず出てくるのでご心配なく。おばあちゃんが見えていて、家賃はかからなくなるから条件は気にせずに」と言われた。その時に頭に浮かんだのは、玄関が1つ、一階が大家さんで、使われていない二階が僕。まるで下宿暮らしのような光景を想像したら、すこし憂鬱になった。
ある時、部屋探しと称して、都心へ向かう道中、バッグの中に財布がない事に気がついた。手帳に現金は少し挟んであるし、問題ないと言えば問題ない。家に忘れているのだから大丈夫と自分に言い聞かせるが、はっきりしないと気持ちが悪い、急遽折り返した。大した金額は入れていないにしても、無くすと困るものはたくさんある。そこから考えが派生し、実家も失くし、両親もいない、誰しもがいずれそうなるし、当てにして生きてきた訳でもないが、何もかも無くしてすってんてんになった時、帰る場所はもうないと思ったら、不安になり、同時に身の引き締まる思いがした。玄関のドアを開けると、財布がポツンと待っていた。リビングのドア陰から、チョビが呆れた様子でこちらを眺めていた。そう、僕らは二人三脚でこれから、頑張らないといけないんだよね、チョビはその事を伝えたかったのかも知れない。
毎日、毎日、日課になっていた「北参道、千駄ヶ谷、ペット可、1LDK」の検索ワード、2ヶ月くらい同じマンションしか出てこないのだが、ある日今までなかった新しい物件が出てきた。ピンと来たので、仲介を買って出てくれた不動産屋の友人に急いで連絡、その日のうちに内見に出向いた。到着して、中を見せてもらうと、古いマンション、窓も多くて、線路にも近かった、場所はもちろん千駄ヶ谷。きっとここなんじゃないのかなと、お告げの主に連絡をすると、そこだと言う。そんなに上手いことがあるのかなあと思いながら、申し込みをした。
いざ契約の折に、先方の不動産屋さんから「大家さんが会いたがっているから、引越しの時にでも、会いに行ってあげて下さい」そう言われた。契約書の貸主の欄には、女性の名前が二人並んでいた。挨拶に伺うと、和風とも洋風とも言い得ぬ、ジブリの映画に出て来る魔法を使いそうな感じの女性がそこにいた。年齢的にはお婆さんと言えば、勿論お婆さん、だけどお婆さんとは言い難い艶かしい空気がそこにはあった。お姉さんの方に玄関先で「あなた随分とご苦労なさったのね、でもここに来たら大丈夫よ」と言われて、すごくほっとした事を覚えている。妹さんには「あなた猫ちゃんいるんでしょ、これからは動物を大事にして、のんびり暮らしたらいいわよ」そう言われた。そうは言っても、お家賃稼がないといけないしなあ、なんて思った事も覚えている。その時、内藤神社の白馬の話をしてくれて、近い場所だったので、お参りに寄った。動物の力を侮ってはいけないと言うのだ。
マンションも、実家の方も、引っ越しの片付けが落ち着いて、いよいよチョビを連れてきた。島の宿と実家、広い場所にしか暮らした事がないチョビにとって、都心のマンションは随分と狭く感じたようだった。階段もないのか…そんな顔をしていた。部屋を一周してソファーに戻ってきては、困った顔をするチョビに、これでも結構頑張ったんだよと言い訳をした。一週間が過ぎた頃、姉がチョビに会いに来た。宿で育ったチョビは、堂々としたもので、ニャアニャアと愛想良く挨拶をしていて、慣れた手つきで姉はチョビの事を撫でていた。「私たち、離婚したとかじゃなくて、本当に一人なのよ、気がついたらこんな年になっちゃってね、まあお嫁に行くって柄でもないし、若い時はモテたんだからね。親戚はいるけど、ほとんど付き合いないし、貴方も一人でしょ? このマンションも貴方が継いでくれたらいいのにと話しているのよ」そう言われた。僕はキョトンとしたが、きっと皆にそう言って気を紛らわしているに違いない。今日は良いお天気ですね、寒くなりましたね、そんな会話と同じ事だろう、そんな風に勝手に理解し生返事を繰り返していた。妹にも見せたいから、この子貸してねと、まるで醤油を借りるようにチョビを抱えて行った。妹の方は、数年前のくも膜下出血で、歩くのが少しだけ不自由で、いつも座って過ごしていた。
呆気に取られながらも、あんまりすぐ上に行くのも失礼な気がして、少し間を置いて行くと、それまで時が止まっていたような家の空気が一変、急に時計の針が動き出し、時を刻み始めたような空気がそこには流れていた。妹も立ち上がり、チョビの後を追っている、とにかく二人の笑顔が、僕には嬉しかった。動物の力は凄い、チョビを誇らしく思った。しばらくしたら、疲れて飽きるだろうと思っていたが、微塵もそんな気配はなく、僕は友人と約束した食事へと出かけ、チョビはお泊まりをした。しかし、お泊まりは続いた、返してくれとも言い難いし、チョビも広い家に満足しているようだったから「もし、良かったら、僕がここに会いに来るようにしても良いですか?」そう申し出ると、嬉しそうに「良いわよ」と言われた。廊下の隅っこでチョビに「大丈夫?」と聞いたら、任せてよと言わんばかりの表情で、またリビングの方へ向かって行った。その横顔に一瞬、亡くなった母の面影を感じた。
ある日「私たち、九州の出身なの、お墓、向こうにあるんだけど、そこに入れたら行けなくなっちゃうと思ったから、パパとママのお骨まだあるのよ、私たちも歳だから、近くにお墓が欲しいんだけど、あなた車で一緒に見に行ってくれない?」そう言われた。行きの車中で「あなたのご両親のお墓は水戸なのよね? 遠いから、こっちに移しちゃえば?」と簡単に言う。うちは父と母が違うお寺の墓に入っているし、墓仕舞いは、なかなか大変なのである。真面目に返事しても仕方ないから、また生返事。見学して、再び契約に向かう日の車中「いくつ買えば良いかな?パパとママで一つ、私たちで一つ、要ちゃん用に一つ……三つかな?」なんて言っている。都市型のお墓は一つのボックスに、骨壷が二つ入るのだ。そして、何せお墓の事である、うちはいらないです……とも言い難く、まあ出たとこ勝負でと思っていたら、お寺に着くと「すいません、お墓を三つ下さい!」と、まるで豆大福かでも買うような口調でお墓をお願いしていた。三人で三つという事は、一人ずつ……と思ったのか、契約はそれぞれですか? と言われた時、事件は起きた。二人の真ん中に座って、困った表情をしている僕を指差して「契約者はこの人です」と言ったのである。そして妹がこちらを向き、薄いピンク色のクリスチャンディオールの大きなサングラスを外して、映画に出てくる女優のような仕草で頬杖をつきながら「あなた面倒臭いから、うちの養子になんなさいよ」そう言われた。「役所の手続きなんか後ですれば良いから、麻生要一郎ってそこに書きなさい」そう二人に促され、僕はああ本気だったのかと思いながら、高野改め麻生要一郎と書いた。お互い何も知らぬまま、僕はこうして、養子になったのだ。
姉は料理上手だった。手料理でもてなしてくれた時、お刺身の切り方や、お皿への盛り付け、お椀の味わい、どれも上等な料理屋のようであった。ある日、彼女たちの部屋に行くと、甘い香りが広がっていた。九州からたくさん届いたという柑橘で、マーマレードを作っていた。大きな鍋でぐつぐつやる姿は、魔女が呪術に使う魔法の液体でも作っている感じがした。使い古されたジャムか、ピクルスの大きな瓶にたっぷり入ったジャムを渡された。味見をさせてもらうと、美味しくて、何だかすごく懐かしい味がした。それは僕を、喜ばせようと思って作ってくれた家族の味がするから。昔、フランスパンが出始めの頃、平凡パンチでサワークリームとこのマーマレードを塗って食べるのを紹介した事があるのよ、やってみたら? なんて機嫌よく話してくれた。
買い物へ出かけるため、さよならとありがとうを伝えて、自分の部屋の冷蔵庫にそのジャムを大事にしまった。家の側の線路の高架下をくぐる時、夕陽が眩しい時間で、電車の窓や大きなビルの窓にも綺麗な夕焼けが反射していた。見渡す限り、黄昏色。それは、さっきもらったマーマレードの色と同じだった。普段は横切ってしまう道路を、その日はわざわざ歩道橋を登って振り返ると、線路越しにうちのマンション、姉妹とチョビの暮らしている部屋が見えた。ほんの少し前に、家族が誰もいなくなったと思ったのに、またこうして家族が出来た、そして帰る場所も。マーマレードの夕焼けの中、僕の目にうっすらと涙が溢れた。