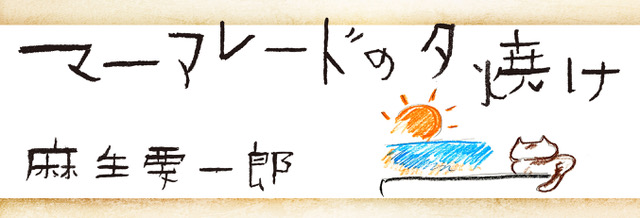第10回 京都の「粋」に触れる旅
京都へ出かける時に携えるのは『あなたと京都へ』という、片岡孝夫さん(15代目片岡仁左衛門)が84年にPHP研究所から出版した、ずいぶん昔の本。養親の姉妹の家にあったもので、片岡さんの視点を含んでの寺社や見どころ、飲食店などがエリア毎に掲載されている。最初は道中の暇つぶし程度の気持ちで持って出ていたのだが、さすが京都だけあって40年近く経っても、移り変わりの早い飲食店でさえも健在な店が多い。東京ならば、跡形もなくなってしまっていそうな喫茶店の類でも、まだまだ健在なのが嬉しいではないか。何より、折り曲げられたページ、記された店名にひかれた赤線、電話番号のメモを眺めているうち、一緒に旅に出かけよう、もう少し調子が良くなったら、季節が暖かくなったらねと言って、叶う事なく行けず仕舞いになった姉妹との京都旅、一冊の本を介し一緒に旅に出かけているような気分になる。
東京駅から乗車して、京都駅で新幹線を降り、駅のイノダコーヒーを横目に混雑する駅を抜けて真っ先に向かったのは、錦市場近くの寿司屋「さか井」である。店内には、丸椅子が3つ、長椅子が1つ、5人が精一杯の小さな店。雨の中、店先に2組が並んでいる。ガラッと開け顔を出すのは、並んで待っていますというサイン。20分ほど経って、順番が周り店内へ入った。前回来たのは、COVID-19の前、ほぼ3年ぶりだろうか。ご主人も、女将さんも変わりなく安堵する。鯖寿司、鯵寿司、ちょっとだけ握りも頼んだ。女将さんのトークも変わらず冴えている、彫りの深い綺麗な顔立ちは、フランス映画にでも登場しそうな雰囲気がある。鯖寿司は、半分の量を寿司と刺身でいただいた、他の店で食べる鯖とは違って、角のとれた丸い味、どこか家庭的な優しさが感じられるのだ。握りは、イカ、真鯛、雲丹。雲丹が美味しさだけを残し、口の中で消えていく。鯵寿司は、棒鮨で鯖とはまた違う風味があって美味。余韻に浸りたいところだけれど、鮨屋に長居は野暮である、特にこの店においては尚更、鱧の時期に再訪を誓いすぐに店を出た。初めての方は入るのに勇気がいるけれど、寿司屋のあり方、極まれりという趣があるので是非お出かけいただきたい。
穴子も食べるんだったと思いながら、錦市場へ入ると、週末という事も重なり、海外からの観光客も非常に多く進むのに時間がかかる。「麩嘉」で、いつもの蓬と粟の生麩を買い、川魚を扱う馴染みの「山元馬場商店」へ立ち寄るつもりだったが、あまりに人が増えていて断念、小道へと逃げた。美味しい鰻も八幡巻も、いつものように送って貰えば良いのだから。馬場商店は、養親姉妹の父親の代からのお付き合い。僕は関東の生まれだが、今やすっかり鰻は関西風が好みとなった。蒸してから焼く関東風は、店で食べないと美味しくないが、蒸さずに焼く関西風は、鰻の風味が引き出され、香ばしい。グリルやフライパンにのせて火を入れると、家でも美味しく食べる事が出来るので、実にお手軽である。
それから今回の旅の目的である、髙橋恭司さんの写真展『Void』の会場となる「ARTRO」へ足を運ぶ。今回の展示に合わせて、HADEN BOOKSを版元に写真集を制作した。この展示会場で、併せてお披露目となった。蔵を改装した素敵な建物、外観からの眺めは古い蔵の佇まいだが、中は蔵の構造をいかしながら、現代的に改装されていて、シンプルな白い空間に写真が映える。1階ではコーヒーも販売していて、2階がギャラリー。恭司さんと一緒に、向かいの「RUFF」というギャラリー系列のカフェでケーキを食べ、写真集の話などをして過ごした。町屋を改装した建物である事を除いたら、普段、近くの喫茶店で恭司さんとお茶をしている感覚になり、なんだか東京にいるみたいだと思った。会期中にまた来れたら良いなあと思いながら、会場をあとにした。
その時、ふと装丁家の緒方修一さんの顔が浮かぶ。彼は、この京都へ今月、居を移したばかり。緒方さんは、僕の著書二冊の装丁をしてくれた、恩人である。この連載も、緒方さんのご縁で始まったもの。本の装丁というだけでなく、色々な事を助言、可能性を伸ばしてもらった、良き先輩である。京都のどのエリアに移っているのかは聞いていなかったが、連絡して、会いに出かける事にした。二条城近くの住所へタクシーで向かうと、近くには川が流れて、その側には真面目そうな書店もあり、その事が彼らの良い暮らしをイメージする事が出来て、妙に安心した。住宅が立ち並ぶ細い路地を曲がったら、緒方邸がある。程よいバランスで、昔ながらの町家を改装した住居は、手前の土間部分を喫茶スペースにするそうで、真っ新なカウンターがお店の佇まいを想像させた。現段階では、やる事に追われつつ、これからの新しい暮らしが楽しみでもあり、ちょっと不安もあるような、しかしこれまでの人生経験に基づいた自信と希望がある、そんな感じがした。お店を始める時は、毎回そういう気持ちだったと、自分が手がけた何軒かのお店を思い出した。近々の再訪を誓い、また中心部へ戻る道すがら、川沿いを歩いて、京都に暮らす妄想をした。盛岡や松本もだけど、暮らしたいと感じる街は、中心部に生活と距離の近い川が流れている。川のせせらぎ、つがいの鴨が何かを啄む様子に、心が安らぐ感じがした。僕が小学生の頃、母が同じ年頃の時に書いた日記を、祖母にこっそり見せてもらった事がある。母の実家の側には、同じように川が流れていて、そこにいた鴨の一羽が母に懐いてピーコと名付けたそうである。母が川辺に行くと、ピーコが飛んでくる、そんな様子が書かれていた。母は生き物や植物と、交流する力があったので、子供ながらに妙に腑に落ちた事も記憶している。野良猫も警戒心なく近づき、家で飼っていたうさぎだって、母には驚くほど懐いていたし、植物も小さな苗からだってどんどん育つ。季節を告げていた母の庭の植物達も、僕が助言に従ってどんなに世話をしようとも、母が亡くなると、あっという間に弱ってしまったのは、哀悼の意を表しての事だったように思う。僕だって、植物を枯らすタイプではないのに。その日記を読んでから、僕は母が亡くなるまで、鴨のコンフィも、鴨南蛮も、遠慮して食べられなかった。母が側にいなくたって、どこか食べる事に罪悪感を抱えていたような気がする。そんな事を思い出しながら、京都の河辺に暮らす鴨の幸せを願った。
旅先のスーパーや百貨店に寄るのが好きである。京都では、大丸に寄るのがお決まり。どこへ出かけてもそうなのだけれど、地元の食材を選んで持ち帰ると、帰ってからの日常に旅の続きがある感じがして、張り合いとなる。まずは、林万昌堂で甘栗を買う。小さい頃から、甘栗は好きなのだが、以前知り合いの編集者に手土産で頂いてから、ここの甘栗が気に入っている。それから生鮮食品売場に取扱いのある「森嘉」という、嵯峨にある豆腐屋さんの飛龍頭やお揚げを、毎回購入している。片岡さんのガイドブックにも掲載があるこのお店には、ちょっとした思い出話がある。養親姉妹の姉が、若い時によく嵯峨の店先まで出かけたそうである。豆腐を求める列に並んでいると、お店の方が呼びに来て下さる。当時のご主人が「いま作りまして」と、お稲荷さんや、店先には並ばないアレンジを効かせた飛龍頭などを特別に用意してくれたそうだ。姉は美人でお洒落だったので、目を惹いたのだろう。毎日買いに来て並ばされる人からしたら、たまに東京から来る何者か分からない女性が特別扱いされていて、得体が知れず、口々に東京のごりょう(御寮)さんと言われていたそうである。姉が、そこの豆腐を扱う店の方から、自分がそう呼ばれているのを笑い話として聞いたとか。関東では馴染みがないけれど、調べてみると近代では関西方面、商家の若奥さん的な用い方で使われていた敬いの言葉である。「今は東京にも、気の利いた飛龍頭があるけど、あの頃は色々な具材が入っているものはなかったのよねえ、珍しかったのよ」と言っていた。ふんわりやわらかな飛龍頭には銀杏と百合根が入っており、少し甘めに煮つけると美味しい。僕は、大丸の地下で思い出を買っているのだ。いつか時間を見つけて、嵯峨の店にも出かけてみたいと思う。
姉妹や、姉妹のお父さんである大井広介も、美味しいものを食べようと思えば自然と関西に足が向いたそうだ。話に出てきていた店名も、後継がいなくて閉店というケースも少なくないので、この頃は時代の移り変わりを感じる。姉妹に教えられたのが、例えば松竹梅のコースがあったとして、焼き物ならば同じ魚を使って、腹、頭、尾に近い部分で提供する。一番美味しい部分、それには及ばないが味わい深い部分を提供していく、そういう目利きを、学びなさいと言われた。高いコースだからトリュフを使うとか、そういう事ではない、奥ゆかしさのようなもの。実際のところ、学べてはいないけれど、彼女達が教えてくれた、その考え方は僕の一つの指標となっている。
今回は愛猫チョビの為に、早めの電車で戻る事を決めていたので、帰りの車中で食べるお弁当を吟味して、新幹線に乗り込んだ。養親の姉妹が言うには、昔は帰り道の新幹線で食べるお弁当やお土産も、馴染みの料理屋さんやお店が駅まで届けてくれたそうである。遠い良き時代の思い出が美化されているとしても、それだけ人々の気持ちにゆとりがあって、色々な事が豊かな時代だったのかも知れない。今は新幹線の本数も多いし、それどころではないような気がするし、第一そんな事をしていたら埒があかないと思った。しかし、もてなしの心意気としては、常にそうありたいものである。
たまに訪れるのと、実際に暮らすのでは、選ぶ店、過ごし方も変わってくるだろう。いつか、短い期間でも良いから、京都に暮らしてみたいと思う。家を借りれば良いだけの事だから、便利な時代、やろうと思えば、すぐにでも出来なくはない。しかし現実は、1泊する猶予もなく日帰り、新幹線の中で予定が書き綴られた手帳を開いている。帰宅すると、玄関先で愛猫チョビが待っており「ニャアン」と鳴く、寂しかったよ、お腹すいたよ、帰ってきて嬉しいよと色々な思いを含んだ、甘い声を聞くと、妄想はどこかへすっかり吹き飛び、チョビを抱っこするのであった。
恐らく次の京都も日帰りである。