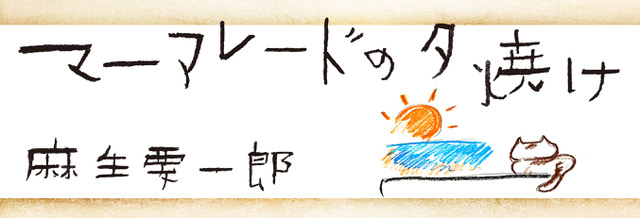第1回 力を抜いて過ごせる「時間」のために
島で宿を始めたのは、2009年の事。
ただ出会いと状況に身を任せ、島の事などは一切分からぬまま宿の営業は慌ただしく、スタートした。僕は、海がすごく好きとか、島が好きというわけでもなかった。その記憶からひも解いて行きたい。
きっかけは、友人の食事会。水戸出身という僕に「納豆が好きだ」という熱い思いを延々と話してくれる人がいた。彼は、超高学歴、マッキンゼーにも在籍していただけに、プレゼン能力が非常に高く、その話がとても面白かった。そのお礼にというつもりで、地元にしか流通していない納豆屋さんから、彼の事務所へ納豆を一箱送った。彼は想像を超える程に喜んでくれて、連絡をくれた。また会いましょうという言葉は、社交辞令と受け取りながらも、日程を合せて出かけると、これからの人生をどう生きたいか…というような話を延々と聞かれ、彼は僕を隅々まで分析した。そして唐突に「島」に興味がないかと聞かれた。行った事がない場所については、関心があるとも言えないし、ないとも言えないという事を伝えると、早速翌週に連れて行かれた。都心から近い、東京の島「ここが、東京で暮らす人達にとっての代々木公園のような存在になったら良いと思う」と彼は言っていた。僕は、ふうんと聞きながら、冬の濃青な海を眺めながら、どれくらいの深さなのかなとか、どんな魚がいるのかなとか、ここに落ちたら怖いなあ、そんな事を考えていた。
当時、僕は自分の名前が冠された家業の建設会社を背負って生きていく事に疲れて、役員を辞し時間と感情を持て余していた。自分で離れておきながら、祖父から託されたものを手放した罪悪感や一種の喪失感を感じながらの鬱々とした日々。自分がオーナーを務めるカフェもあったけれど、スタッフがたくさんいたので、僕の居場所はそこにはなかった。このままでは、しばらく立ち直れないかも知れないという焦りのようなものもあった。
家業を継ぎ始めた20代、社長だった父が早くに亡くなっていたので、僕が入社した時には、祖父の時代からの番頭さんが社長となっていた。番頭さんも、何年か社長を続けていれば、自分の会社という意識も強くなる。僕は平社員から入社したので、皆の都合が良い時にはただの平社員として扱われ、皆の都合が悪い時には急にあなたは未来の社長ですという、便利な存在だった。面倒な事は、何でも「良い経験になる」と押し付けられた。しかし、その下積みがだんだんと周りに評価され、僕は成長した。数年下積みを経験する中で、財務担当者として金融機関との良好な関係を構築する事にも成功した。まだオンラインなんていう感覚のない時代、ATMに僕が並んでいると支店長が飛んでくる。「機械にお並びいただかなくても、お茶を召し上がっていただいている間に私どもが対応させていただきます。」そう言って、どんなに混んでいる日だろうが、応接室に通され、お茶を飲んでいるうちに全てを済ませてくれた。建設会社は扱う金額も大きいので、売上が順調に伸びているうちは、良い顧客という事であり、この仕事を続けるなら、銀行でお茶が出なくなり並ぶようになったら、僕の立場は終わりだといつも思っていた。今となってはすっかり笑い話だが、銀行とは、個人に対してではなく、その立場に対してやっているだけの事だと、僕は冷静に受け止めていたから、会社を辞して、同じ銀行に出かけて長い順番待ちをしても、何とも思わなかった。
濃青の海から目を上げると、運動神経が良いとは言い難いその友人が、目の前の急な斜面をよじ登ろうとして、中途半端な位置で立ち往生していた。この島は、頭が良くてクールな人を、こういう気分にさせるのだなあと思いながら、登り切る様子を眺めていた。便利な街中でカフェを営んでいても、そこを目掛けて来てくれるのはほんの一部で、あとは近所に用事があってとか、通りがかりの方が多い、勿論ありがたいのだが、それでは当時の僕にとって生きる原動力にはならなかった。この島で自分が何かを始め、そこに来る人達は、船か飛行機に乗ってわざわざ来る訳だから、それは自分にとっても力試しというか、再起するチャンスのようにも思えた。誰も来てくれなければ、自分の力量で生きる道への諦めもつく。島で宿を始めて一年目は、友人・知人がたくさん来てくれた。ブランディングの仕事をしている女性の友人が忙しい中、家族と一緒に何泊かした際、帰り際に「あなたは外食の味じゃない、家庭の味を大切にして、いつか暮らしの本を出しなさいね」そう言った事を記憶している。とは言え、初めのうちは、お客様がどんな料理を食べたいか試行錯誤している時期もあった。イタリアンをはじめ、色々なパターンを試したけれど、結局のところ彼女の言う通り「家庭の味」に落ち着いた。それ以来、その言葉は僕にとっての羅針盤となっている。
東京で採れた良い魚は築地へと運ばれ、そうでもない魚は売られる事もなく、それぞれの家庭へ消えて行く。余所者である僕等が、島で採れた魚を買うのは簡単なようで難しく、島のスーパーの社長や、強面の飲食店の店主が応援してくれた。「赤烏賊が大量だったからとっておいたよ」「大きな鰤、良かったら使ってよ」「平目大きくていいだろう」……。彼らの協力がなかったら、何年も続ける事は出来なかったと思う。大きな鰤なんて捌いた事はなかったけれど、見様見真似で捌き方を覚えていった。毎年、ゴールデンウィークから秋口までの約半年、島で一緒に働いてくれるスタッフを見つけるのも大切な僕の仕事だった。宿を切り盛りするには、僕の他に最低2人、忙しい夏に手伝ってくれる助人も別に必要。コンセプトなんていうものはなかったけれどイメージとしては、島のおばあちゃんの家に来て、海で遊んで帰って来ると、台所から美味しそうな匂いがしていて、いつの間にか昼寝をしてしまい、気がついたら薄かけがかけられていて、外に出ると海に沈む夕焼けが綺麗だった……そんな一日を過ごして欲しい。スタッフに関しては、忙しい中、一緒に暮らして働くのだから、とにかく一緒にいて嫌じゃない人。働き者のおばあちゃんが島で切り盛りする宿を、夏休みに手伝いに行く……そんな気持ちで来て欲しかった。マニュアルも役割分担もない。それぞれの得意不得意を見出しながら、自然に割り振っていく。お客様への対応も、その人のキャラクターで接客をして欲しい。せっかく島まで来たのに、推し着せのような仕事では、提供する方もされる方も辛いものだ。僕が彼らに、良く接していれば、彼らもお客様に良く接するはずだ。台所の片隅で耳を澄ましてその様子を聞きながら、それぞれの成長を見守るのが毎年楽しかった。自分の感覚で、お客様にこうしてあげよう、そう思っている瞬間が生まれるのを見ているのが好きだった。朝食、それが終わると、買い出しに行き、お昼、8月のピーク時にはランチ営業もするし、泊まっている人が何か食べたいと言えば作り、賄いも作る、船で食べる帰りのお弁当が欲しいと言われたりもする。午後からは、夕食の支度、それも1泊目、2泊目、3泊目、肉がダメ、魚がダメ、胡瓜が嫌い、ビーガンetc、様々な条件と要望をクリアしながら、パズルのように組み立てる。それが提供し終わると、スタッフの賄い。これも日々の事だから、また別に作る。胡瓜が嫌い、肉が苦手、コロッケが好き、カレーが食べたい、毎年色々ある。銘々の機嫌をとりながら、長い1日が終わる。スタッフが寝静まる頃、予約のメールや問い合わせのメールの返事を送り、寝ようかなあと思う頃、眠れないお客様に何か飲み物をそっと出したりする。僕が台所で奮闘している間、スタッフは掃除洗濯、お客様の対応と忙しい。夜の賄いは、彼らへの労いなので、向き合ってきちんと作る、それが信頼関係にも繋がったと思っている。
島で宿をやっていたなんて言うと、羨ましがられるのだけれど、朝起きてから夜中までずっと働いて、海を眺めるのも買い出しの途中に車窓から。海に入る事はほとんどなかった。夕食の支度をしながら、台所の小さな窓に綺麗な夕焼けが差し込んできたら、休憩を兼ねて屋上へ梯子で登る。特に季節が夏から秋に移ったあたり、見渡す限りオレンジ色、息を呑む美しさ。そんな時、スタッフが屋根の上で足をぶらぶらさせながら、夕焼けを見つめていると、僕はその後ろ姿をしばらく見つめて、邪魔をしないようにそっと梯子を降りる。きっと、東京に戻ってどうしようかなあ、そんな事を考えていたのだろうと思う。心配はするけれど、自分なりの答えを導き出して欲しいから、邪魔はしない。そんな様子を見かけると、夕食の時間にその子の好きな一品を作っていた。毎年来てくれたら、それは楽に違いないけれど、半年間の営業ではそういう訳にもいかないし、毎年フーテンなのも困るので、1シーズンで終わりと暗黙の了解で決めていた。僕は、その人らしさを尊重し、半年間過ごしたら、また夢に向かって頑張って欲しいと心から願っていた。卒業しても、また翌年遊びに来たり、お互いの仕事で協力しあったり、擬似家族的な感覚もあって、その様子が嬉しかった。疎遠になる人もあるけれど、皆、ここでの時間を通して、より自分らしい事が出来ている感じがする。それは本人の努力に他ならないが、それぞれのその頃の様子を思い出しながら、クスッと思う事はたくさんある。
ある時、アメリカから来たカップルが何泊かした後に「僕は旅のコラムを書いていて、ここの事を書いてもいい?」と言うからブログか何かだろうとOKしたら、後日NEW YORK TIMESにそのコラムが掲載されていた。かっこいいロゴの下に、薄暗い座敷で彼らが喜んで食べていたイカ刺しの写真が載っていて、とてもシュールだった。僕はずっと台所にいたから登場せず、その時、細やかに対応したスタッフが主人のように書かれており、それも僕は嬉しく誇らしかった。お客様に対する気持ちが、しっかり届いていた証なのではないだろうか。すっかり人気の宿となったが、6シーズンをやり終えた冬に、建物の契約更新が叶わず、呆気なく営業は終了した。今年が最後の営業です、今夜で皆さんとお別れです、僕はあまりそういう感傷的な事は好きでないので、そんな思いをしないで済んだ事、人気の宿のまま、行こうと思っていたら無くなっちゃった、そんな終わり方が出来た事は本当に幸せだったと思っている。
島なので、偶然その場所を通りかかる事もないし、行こうと思ってもそれなりに手間がかかるので、営業が終わって片付けをしに行ったのが最後、時間が経つに連れて記憶もどんどん薄れていく。濃密な時間を過ごしたと言うのに、時折、あの宿は本当に存在したのだろうかとさえ思ってしまう。しかし、今でも仲の良いスタッフと会い、宿に泊まったと言うお客様から声をかけていただいたりすると、確かにその宿があった事を感じる。僕は台所にずっといたので、お客様と面識がなかったりするけれど、泊まりましたと言われると、懐かしい友人に再会したようなあたたかい気持ちになる。また宿をやれと言われても、忙しいのも大変なのも分かっているから、きっと嫌だと言ってしまうけれど、今の自分だったらどんな宿をやって、どんな料理を出すのだろう、そう思うとちょっとワクワクする。しかし、友人達を招いて食事会などをすると、宿をやっている時の感覚と変わりなく、僕が一番導き出したいのは力を抜いて過ごせる「時間」なのだと、洗い物をしながらいつも感じるのである。