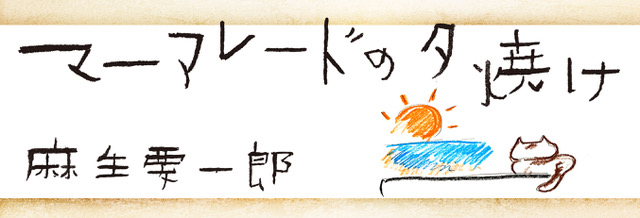第17回 家族のカタチ
家業の建設会社にいた時、フィリピンの首都マニラに出かけた。目的は、会社で新しく取引を始める建材会社の工場を視察するため。初めて訪れたフィリピンは降り立った空港から、何か危険な感じがした。税関を抜けて空港から出ると、タクシーに乗らないか? これ買わないか? と、人がどっと押し寄せてきて不安になったが、迎えに来てくれた既に顔見知りだった、穏和な表情をした台湾人社長の笑顔を見ると少し安堵した。乗り込んだ車の運転席に座っているのは、まるで少年のような現地の若者だった。
空港付近の道路は混雑していて、モノ売りの子供達が車を取り囲む。「窓を開けたらキリがなくなるから」と、僕が外に目を向けている様子を制して、工場の社長が言った。何か買ってやりたい気持ちを堪えて、視線を遠くの景色に向けていた。バラックの集落がある側に、その存在を無視するかのように、欧米のチェーン店が立ち並んでいるのは、不思議な光景だった。そういったところに住んでいる人達の生活環境を尋ねると、集落に水のシャワーが一つあるくらいで暮らしは貧しいという。チェーン店も立ち並んでいる様子からすると、貧富の差も激しいのだと思う。それでも街を行き交う人々の表情には、活気があるような感じもした。もう20年ほど前の話だから、今は生活環境が整っている事を願っている。
ついつい同情するような思いで、バラック街の様子を車窓から見ていた時、僕はハッとした。トタンに囲まれた土埃の立つ小さな路地を、陽の光の中を小さな男の子と若い母親が手を繋いでゆっくりと歩いていた様子が、とても幸せそうだったのだ。いろいろ大変な事はあるかも知れないけれど、親子が手を繋いで歩いている、その瞬間はかけがえのない幸せな時間ではないだろうかと思えた。
僕は家族のことを考える時に、よくその光景を思い出す。
あの時の少年は今、どうしているだろうか。
小学校低学年の頃まで、僕の友達はクマのぬいぐるみだけだった。親はきっと心配しただろうと思う。大人の中で育ち、ませて内気な僕は、友達と外で元気に遊ぶなんて事はせずに学校から帰ると、クマのぬいぐるみと空想の世界で遊んでいた。父は将来、この子が建設会社の後継者になれるかと不安に思っただろうし、母親も同じように心配しつつ我が子可愛さの心情の間で苦しい思いをしていたかも知れない。
しかし僕はとても幸せだった、クマのぬいぐるみは、いつも寄り添ってくれたし、優しくて、僕の味方だった。関心のない者には、何も捉えていないように見えるその目の奥、僕にはちゃんとその表情が見えていた。心配している時の目、楽しそうな時の眼差しに、いつも見守られていた。
父の帰りは遅かったし、僕にとってはお婆ちゃんだけど、少し離れたところに暮らしていた、揚げ足を取るような小言を言う厳しいお姑さんもいた。今で言う、ワンオペ育児は本当に大変だったと思う。一方、母方の祖父母は本当に優しい人達で、ぬいぐるみの存在もちゃんと認めてくれていた。父と母が外出で帰りが遅くなる日、その祖父母の家に泊まりに行く事になり、僕は早々に支度をして待っていた。母に早く行こうと急かしたのか何があったのか、今となっては記憶にないが「そんなに行きたいなら、おばあちゃん家の子になりなさい」と言われて、僕はバッグに、クマのぬいぐるみと、多分他のぬいぐるみも詰め、靴を履いてスタスタ家を出た。ちょっと離れたところで、いない事に気がついた母が涙を流して追いかけてきた事を覚えている。「要くん、ごめんね!」そう言って、抱きしめてくれた。僕は怒ったり、悲しんだわけでもない、大好きな母がそう言ったから行動したのだ。きっと母だって、いろいろあってつい感情的になっただけのこと。フィリピンで見た光景がやたら心に残ったのは、どこかその時の情景が重なるからかも知れない。
成長するにつれて、クマのぬいぐるみとは、いつの間にか離れてしまったが、少し落ち込んだ時、僕は今でも思い出す事がある。あんなに大切な存在だったのに手放し、僕だけ大人になってしまった事への僅かな罪悪感。少し前に『プーと大人になった僕』という、プーさんを愛したクリストファーロビンが大人になって、仕事のストレスもたくさん抱えて、家庭の事でも悩んでいるところに、突然プーさんが目の前に現れ失っていた大事なものを取り戻していくという映画で、何だか胸が締め付けられるような思いで見ていた。その映画のように、クマのぬいぐるみが僕を守ってくれ、何かの時には、僕がクマのぬいぐるみを何かから守っていたことがあると改めて思った。
僕の中では家族的存在である友人の、娘さん(彼女も僕の大切な友人)が、いつもハリネズミのぬいぐるみを連れている。僕はその光景を見ているのが、とても愛おしく「いつまでも一緒にいてあげてね」と、そのぬいぐるみ(この表現は怒られるかも知れないが、名前をのせるのは遠慮したので許してほしい)に話しかけている。時に、恋人、子供、友達、家族と、彼女はそのぬいぐるみに色々な感情を寄せている。恐らく彼女が初めて自分で見つけた、家族だと思う。僕にとっても、あのクマのぬいぐるみは、そういうかけがえのない存在だった。
父は僕が19歳の時に心筋梗塞により44歳で、母は僕が38歳の時に癌の再発により62歳で亡くなっている。人生100年時代と言われる現代とは思えぬ若さで、僕の前からいなくなってしまった。父が亡くなったあと、家業の会社を継ぐ関係で祖父の戸籍に入った。現在はマンションの大家さんとして知り合った麻生姉妹の、姉の戸籍に入っているが、その前に先に亡くなってしまった妹の戸籍に入っていたから、僕は人生で3回養子縁組の手続きをしている。しかし、それは紙切れ上の話、姉妹との関係でいえば知らない者同士が短時間のうちに互いに家族と感じられるようになったのは、一緒に何かを食べる事、食卓の影響が大きかったのではないかと思っている。
例えば、プリンといえばモロゾフ、ケーキといえばユーハイムのショコザーネかトップスのチョコレートケーキ、クッキーといえば泉屋(創業者が仲良しで焼き損じをたくさん下さったのだそう)、肉まんといえば維新號、パンならフロインドリーブ、お肉は日山…彼女達と過ごした時間で、共有した食の定番である。その店が、美味しいとか美味しくないとか、名店とか老舗であるとかは、どうでも良い。まるで共通言語のように、そのお店を思い浮かべる事が出来たり、お店の前を通ったら喜ぶ顔が目に浮かんだりする。入院している姉から、ケーキが食べたいわと言われたら、京王百貨店にあるユーハイムへ駆け込んだものである。他のお店が美味しいと思っても、ケーキの味には一緒に食べた思い出も含まれているから、他のお店はかなわない。思い出だって、美味しいねと一緒に食べた日ばかりではない、喧嘩をして機嫌が悪く口も聞かずに食べた日だってある。そういう何かを一緒に食べた日々の積み重ねがあって、姉妹と家族という関係性を結んでいく事が出来たのではないかと思う。姉がよく作ってくれた、牛すじ肉を使ったボルシチ、ある時に「私が死んじゃっても、貴方がボルシチ食べたら私のこと思い出したり、作ったりするのかな?」と、大きな鍋を掻き回しながら言っていて、返事に詰まった事を思い出す。今は、施設にいるので離れて暮らしているが、ボルシチには特別なノスタルジーを感じる。
現在の我が家の食卓は賑やかだ、家族のような存在の友人達がたくさん帰ってくるからだ。弟のような存在の友人が来る日には、唐揚げ、煮魚か焼魚、こんにゃく、きんぴらとなり、先述の娘さんがハリネズミのぬいぐるみと来る時には、彼女の好きな、上等な焼海苔と空豆や枝豆といった好物は欠かさず用意。そして翌日の学校のお弁当に詰められるよう、唐揚げを少し多めに作る事も忘れない。小学生の友人コンちゃんが遊びに来る時は、グラタン。たくさんミートソースを作り、パスタを敷いて、ベシャメルと合わせてチーズをたっぷりのせたグラタンが彼の好物。うちのマンションの1階に事務所を構えるささやんが来る時は、牛乳、胡瓜は避ける、白飯は多めに炊く。常君が来る時には、豆腐と玉コンを煮る。そういった具合に、僕の中には食卓を囲む面々との様々な嗜好が刻まれている。牛乳だって、どれが良いかと吟味して並べている。そして、家人のビールは黒ラベル。食卓を囲む、面々が疲れているなと思えば、酢の物を増やし、毎日誰かの顔を浮かべながら台所に立っている。
そして、僕の最も大切な家族はチョビ。ごはんは、カリカリものとウェットフード、鰹節、お水。いささか食べ過ぎ傾向にあるが、今のところ健康。年齢を考えれば、病院に行って細かく検査したら色々あるだろうが、それは人間も同じ事。お水はリビングと寝室に汲み置き、別に循環型のも用意しているが、朝昼晩と洗面台に登って水を飲むのも長年の習慣。洗面台の上でお気に入りのコップに注ぎたての水を、ゴクゴクと飲んでいる。朝食を食べていると、側にやって来てパンの味見。小さく小さくちぎったものを味見するのだが、クロワッサンのようなバターを含んだものが好み、食パンは香りを嗅ぐ程度、ちょっと身体に気を遣い雑穀や全粒粉だと匂いを嗅いだだけで、走って逃げて行く。猫がごく微量とはいえパンを食べるのが健康上の是非は別として、僕はチョビと暮らす上で、毎日の大切なコミュニケーションだと思っている。
もともと僕が経営していた宿の看板猫だったチョビは、亡くなった母とは心を通わせると、母がお風呂に入ると浴室に一緒に入って浴槽にかけられた蓋の上に寝そべって、トイレに入ればトイレの前で待っているほどで、片時も離れない感じがした。母が自宅で亡くなった時には、現場検証の聴取にも一緒に応じて、警察の方から「可愛くて、賢い猫ちゃんだね」と褒められていた。その後に麻生姉妹に出会うと、しっかり寄り添う。初めはくも膜下の後遺症で体の左側が少し不自由だった妹にぴったり、やがて妹が認知症になって姉の負担が増えると姉を気遣うようになった。僕が行き届かないところを、上手にカバーしてくれた。今は家人ともすっかり仲良し、初めて猫と暮らす彼のハートを鷲づかみにしている。もう15歳になるチョビは、人間でいえば76歳。見た目の可愛さとは裏腹に、いろいろ出てくるお年頃。忙しい日はあるにせよ、なるべくチョビとの時間を大切に過ごすようにスケジュールを調整している。ソファーやベッドで、横になっているとチョビはすぐお腹の上に乗ってきて、喉をゴロゴロと鳴らす。僕はその時間がとても幸せなのだ、お腹の上のぬくもり、ずっしりとした重さ、その眼差し。全てが愛おしい。僕らは、支え合い助け合い、お互いを信じて一緒に生きてきた。それは家族という関係に他ならない、
今日も買い物に出かける、チョビの好きなフードを選んで、パン屋さんでクロワッサンを買って、そして食卓を囲む人の顔を浮かべながら食材や飲み物を選ぶ。その時に、浮かぶ顔が僕の「家族」だ。さて、今夜は何にしようかな?