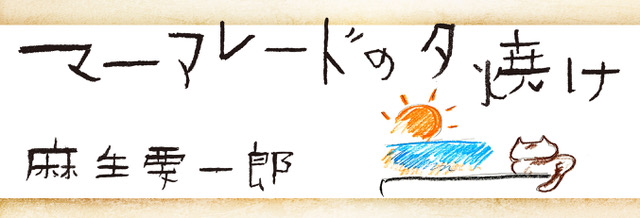第7回 僕の浅草
浅草という街に魅力を感じるようになったのは、割と最近の事である。最近では、浅草寺裏手、住宅が立ち並ぶ静かなエリアにある「annorum」というお店が、気に入っている。古い家屋に手を加えた店内には、アンティークの家具が並び、仕立ての良い洋服やバッグ、小物や本などが置かれている。店主の拘り、愛着が伝わってくる商品は、とても魅力的である。最近は、そこで購入した素材違いの同じ形のバッグ2つをよく使っているが、ブランド名などはすっかり忘れて、annnorumのバッグという事になっている。商品性もさる事ながら、そこに置かれている事で、商品の魅力が増すような、店主の目利きが冴え渡るお店である。その前後に立ち寄るのが、歩いて5分程の距離にある「ロッジ赤石」という喫茶店。喫茶店と言いつつ、食事のメニューが多く、お茶しに行くというよりは、何かを食べたくなるお店。僕は毎回「エビサンド」(海老フライが挟まっている)を注文しているが、パスタ、カレー、グラタン、ピザ、丼、定食ものなどに加え、サンドイッチ、ざっと100種類はありそうだ。パスタのページに目をやれば「パリジェンヌ風ヌイユ」とある、ついつい気になるメニュー名を目にしてしまうと、メニュー選びは難航する。これだけのメニューをどうやって捌くのかと気になってしまうが、決して広くはなさそうなキッチンで淡々とこなしている。それは創意工夫の結晶であり、下町に根付くお店の人情味が輝いている。浅草寺を抜けて、雷門へと足を向けると、人通りも多くなる。その中でも、すっかり人気者になった「亀十」のどら焼きは、自分で買う場合は白餡一つと決めている。美味しいけれど、大きいので一人で一つ食べるとちょっと多く、二人で半分ずつくらいの、もう少し食べたいという感じがちょうど良い。ちなみに、そのすぐお隣にある「龍昇亭西むら」の、羽衣というお菓子も好き。ブッセのようなお菓子で、中には杏のジャムが入っている。他にも、由緒正しき和菓子が色々と並ぶ中、羽衣だけを引き立てて申し訳ないが、好きなのだから仕方がない。最近は、亀十の行列が長い時には潔く諦めて、西むらのお菓子を色々と見繕う機会が増えている。
時代は遡り「大井広介に始めて会つたのは昭和十五年大晦日午後七時、葉書で打合せて雷門で出会つた。」と、坂口安吾が「大井広介といふ男―並びに註文ひとつの事―」というエッセイを『現代文学』に寄せている。大井広介とは、僕の養親となった姉妹の父親、即ち僕の祖父である。文芸評論家として、昭和を生き、昭和52年に63歳で亡くなっている。このエッセイの中で「こんなケタ外れの怪人物は生れて始めて見たのであつた。」と書かれている。他にも、「デタラメ」など、色々な言葉が愛情を持って投げかけられている。安吾にそうまで言わしめる御仁が亡くなるのと、すれ違いで生まれた僕は、会う事が出来なかった事が残念でならない。当時、祖父は『現代文学』という同人誌をやっていた。同人の集まりは浅草「風流お好み焼き 染太郎」で行われるのが常、名物女将だった初代・崎本はるさんが、切り盛りされていた。お店へ連れて行かれた時、まだ小さかった姉妹は、そこでホットケーキを焼いてもらったと話していた。実は姉妹の養子になった頃に、浅草を訪れた際、「染太郎」の前を偶然通りかかって、その佇まいから風情のある店だなあと気にかけて調べた事があった。当家ゆかりの店と知ったのは、それから間もなくのこと。それは、何か大井が僕に仕掛けた小さな悪戯のようにも思えた。後日、店を訪問、当時の賑わいは、店内に飾られたサインや写真などから伺い知る事が出来る。エノケンをはじめとした、当時の浅草を賑わせていたスター達も訪れていたようである。1983年に染太郎50周年と、崎本さんの米寿を記念して刊行された『浅草 染太郎の世界』(かのう書房)にも、大井についての記述が何箇所か見受けられ、その親密な関係性が伝わってくる。「大井氏は家族ぐるみで染太郎と親交があったようだが、戦争中の大井邸に大勢の作家たちがたむろしたことは有名である。現代文学を中心に集まったというより、大井氏の魅力、その家の雰囲気に人々を居心地よくさせるものがあったに違いない(中略)私の独断をさしはさむなら、大井邸すなわち浅草の染太郎ということになるのではあるまいか。そのあたたかさ、もの書きに息抜きをさせるたたずまいの共通性に於て」と、小説家の庄司肇が記している。その一文を読むたびに、僕は当時の様子を回想している。我が家にも、大勢友人達が訪ねて来てくれるのは、大井のエッセンスを僕が受け継いでいるという事なのかも知れないと考えると、嬉しくなる。
河豚が好きだった大井は、浅草「さんとも」へも足繁く通っていた。(同店は、戦後銀座に移るが、のちにお店を閉めている模様)こちらも家族ぐるみで付き合いが深かったようで、当家へもよく足を運んでいた様子。戦火が激しくなって来た時に、いよいよ東京を退避しようという前日、お酒もたくさん残っていた当家の広い防空壕で文士仲間とパーティーをしようと、浅草から料理を拵えて来てくれた時、何か忘れ物をしたとか、養親の姉がそれを取りに浅草へ行ったそうである。その時に「随分やられたなあ」と思いながらぼんやり眺めた街並みが、浅草の敗戦前の最後の風景だったと目を細めながら話してくれた事があった。翌日、大空襲で甚大な被害を受けたそうだ。東京の外れに借りた農家の離れに、たくさんの本や家財道具を預け、持っていけなかったものは、土に埋めたと言っていた。姉妹の父は、愛用していた豚毛の歯ブラシを、戦争で買えなくなっては大変だと丸善に駆け込んで在庫分を全て買い上げた。姉妹たちは、その父親の様子を回想しながら、子供ながらにもっと大事なものがあるはずだと思ったという話が僕は好きだった。庄司肇が記してくれた、当家の居心地の良さというのは、何か現実的な深刻さとは距離のある、ちょっとずれた感覚なんじゃないかと僕は思った。
養親の姉妹とも何度か、浅草へ出かけた。国際通りに面した、浅草ビューホテルの26階にある「スカイグリルブッフェ武蔵」からは、隅田川からスカイツリー、浅草の街並みがよく見渡せる。花やしきの辺りを指差しながら、染太郎で父親がおしゃべりをしている間、姉妹は退屈しのぎで花やしきのあたりをうろうろして、可愛いロバがいたという話をしていた。それが正確な情報かどうかは今となっては分からない、花やしきとなる前、昭和の初めまでは動物園的な要素があったようなので、その名残でひょっとすると、ロバがいたのかも知れない。このホテルからの眺めが気に入ったようで、何度か一緒に訪れる事が出来た。「松喜」という精肉屋へも、懐かしいからと何度か立ち寄った。大正時代からご当地浅草に店を構える、老舗の佇まい、ショーケースに並ぶお肉の美しさが際立つ。捌き方一つで、お肉の見え方は随分と変わると思い知らされる。
お肉と言えば、雷門通りから、たぬき通りへ抜ける途中の「金楽」という焼肉屋がある。たまたま家人と歩いていて見つけた、1972年創業のお店。普段は、昼から夜まで通しでやっているが、月曜日だけは夕方からの営業で、開店と同時に入店すると瞬く間に満席となる。すると、奥の席で従業員たちも賄いを食べ始めた。今の時間は注文するのをちょっと遠慮しようかという気持ちになるような、清々しい光景だった。若い厨房で働く男性が、丼飯をおかわりしていて、彼らが食べ終わったのを見計ってライスを注文した。従業員が美味しくご飯を食べていたら、良い店に決まっていると僕は思う。ハラミが評判、煙はもくもくでも大丈夫という方は是非足を運んで欲しい。その斜向かいにある、八百屋もまた良い。行く度、野菜をたくさん買っている。夏に、療養中の養親の姉がいる病院から「食欲がないので、鰻が食べたい」との連絡があった。彼女たちは、西にルーツがあるので、関東風の蒸した鰻はあまり好まない。しかし「東なら、前川」と話していた事を思い出し、隅田川沿いに佇む「駒形前川 浅草本店」まで出かけ、折り詰めにしてもらったものを届けた。せっかくだからと、自分も客席に上がり昼食に頂いたが、極上の鰻と、隅田川に挟まれて眺めるスカイツリーには、格別な下町の情緒が感じられた。もちろん、今では他にも美味しい鰻屋はたくさんあるのかも知れないが、浅草という街や地名が漂わせる郷愁の念は、その街に古くからある飲食店と同じく、何処か下町のさばさばとした感じと、ふくよかさを思い出させるのかも知れない。
かつて「ラ・シェーブル」というフレンチのお店が、田原町寄りの路地裏にあった。僕は、そこの前菜にあった「赤ピーマンのムース」が大好きだった。(メニュー名は随分前の事で詳細は失念)毎回、丼で食べたいと思っていた。メインは、鴨のコンフィを選ぶ事が多かった、今では「ガンゲット・ラ・シェーブル」という店名で、よりカジュアルなスタイルでファンを広げているようである。そこへも何度か行ったけれど、やはりあの頃の佇まいが恋しくなる。東京の街は、以前はそれぞれの街にしっかりとした街の色があったように思う。しかしどんどん便利になっていく過程で、その色の違いが曖昧になってきている。同じ店、似たような店がどこの街にも並んでゆく。それは、日々の消費活動の鏡なのだと理解し、あらゆる未来を否定するものではないけれど、自分の好きな町やお店には、足繁く通い、これからも続いていく事を願っている。ただ一人がそう願う事は、どんなに脆弱な事かは理解している。都心の家賃や物価高騰を補えるものではなく、客足をどうにも出来るわけではない。老舗と呼ばれる店が、これからも手間隙かけて続けていくのか、今が過渡期のように僕は感じている。無くなる事が決まって、惜しんでも仕方がない、好きなお店がこれからも続いていくように小さな努力を積み重ねたい。大井が安吾さんに送った当時の手紙には、どこどこの寿司が美味しかった、そんな事がよく綴られていた。浅草へ来ると、雷門の前で落ち合った大井と安吾の姿を空想する。2人が、今もそこで楽しく話をしているような気がしてならない。