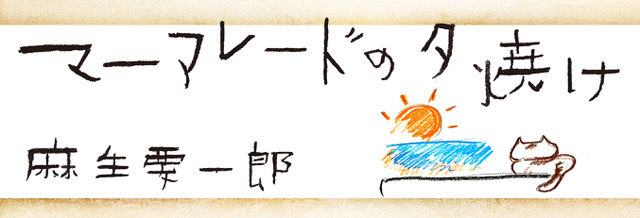第16回 恋しくなるお弁当
自分が「お弁当屋さん」になったと気が付いたのは、お弁当のケータリングの仕事を初めてしばらく経った時のことだった。
母を実家で看取ってから、愛猫チョビと東京に戻って「ごはんを作っていればどうにか生きていけるかな?」と思っていた時のこと。そうは言っても、突然仕事が沸くものではなく、暇なもの。厨房でぼんやりしていると、友人の編集者が「時間あるなら、撮影の時にお弁当作ってよ」と言う。雑誌や広告なんかの撮影現場で、お弁当の需要があるというのは素人には、なかなか分からないものである。言われるがまま、高級住宅地の立派なお屋敷のハウススタジオに、頼まれたお弁当を届けた。その時は、よくあるプラスチックの黒い仕切りがついたお弁当ケースに、普段作るようなものを詰め込んだ、地味なお弁当だった。届けたものの、評判がどうだったのか分からない。不安になっていると「美味しかったよー!」と撮影が終わった頃に、彼女から連絡があった。すると、後日その現場で食べたという方が、別の撮影現場にお弁当を頼んでくれた。そこへ持っていくと、また別の人から依頼が来る。当時は、母を看取ったあとで、気分も晴れない自信もないときだったから、その連鎖がとても嬉しかった。注文がある毎に、お弁当のケースも試行錯誤、エコっぽい素材にしてみたり、竹の皮で作ったようなものにしたり、今の長方形の入れ物に落ち着くまでには、数回変更を経ている。気がつけば、毎日のようにお弁当を作っていた。ある広告代理店からの大口の注文をいただいていた日、先輩編集者Pさんと先輩スタイリストのchizuさんから、銀座のスタジオにお弁当を2個持ってきてと依頼があり、届けに行った。大好きな2人に頼まれたので、スキップするような気持ちで届けに行くと、雑誌のページでお弁当を撮影するのだという。どんな小さな枠でも、取り上げてもらえたら嬉しいと思っていると、人気の雑誌にドーンと1ページ分を使うような大きさで僕のお弁当が掲載されて嬉しかった。それから、じわじわとまた広がり、有名なファッションブランドなどからの撮影や展示会等のお弁当注文が増えていった。
移転する前のパートナーのお店でも、お弁当の会をよくやった。栗の季節には、栗ごはんのお弁当、向田邦子のエッセイを読みながら着想した向田邦子の南青山弁当とか。そんな時に、今では南青山の母として親しむDEE’S HALL(現在は福岡DEE’S COLLECT)の土器典美さんも食べてくれて「美味しい」と褒めて下さった。それは大きな自信に繋がった、彼女は絶対にお世辞を言う人ではないと思ったから、ドンと太鼓判を押されたような気持ちになった。あるときに、美術館から海外のアーティストが来る時のお弁当を頼まれた。予め、当日配達に行く車のナンバーなどを伝えて、搬入口に行くと守衛さんが、奥の守衛さんに大きな声で叫んだのだ。「お弁当屋さんでーす」と。僕は、要一郎さんお弁当作ってよと言われて、屋号も決めないまま作っていたし、お弁当屋さんになったという認識があまりなかったから、その言葉に「お弁当屋さんだったんだ……」と、自分が心底びっくりしてしまった。だんだん介護やら、執筆やらと忙しくなってきたので、お弁当は今ではほとんど受けることが出来ないけれど、僕を育ててくれたお馴染みの方々からの依頼には可能な限り応えるようにしている。
お弁当の人気のおかずは、唐揚げと卵焼き。どちらも子供の頃、母が作ってくれたお弁当に入っていた、僕の好きなおかず。母が作る卵焼きは、関東風の甘みがある味付け。使う調味料は、醤油、味醂、砂糖。そして焼き方はちょっと焦げ目がついていて、それが見た目にも美味しそうだった。唐揚げは、醤油味。にんにくや生姜が効いて、ごはんによく合う。ひじきや、ほうれん草の胡麻和えも副菜に入っていて、彩りがきれいだった。遠足や運動会の時に、お弁当を開けると覗き込んできた友人達が「美味しそうだね」と言ってくれるのが嬉しかった。クラスの中でも大人しく、引っ込み思案な子供時代、授業参観に訪れる母はいつもお洒落できれいだった。普段は口をきかない同級生も「要一郎くんのお母さん、きれいだね」と話しかけてきた。性格的には母も、一人っ子で僕と似た子供時代を過ごしたはず。母の存在が、そうやって僕に誰かと話すきっかけや、友達を作る糸口になってくれていたのだと思う。
今、僕が作るお弁当に入れている唐揚げは、飯島奈美さんに教わってから、愛用している梅酢を使った唐揚げがお弁当にはぴったりで、冷めても美味しい。甘みのある卵焼きは、母の味。美味しいお弁当には、よくきれいなだし巻き卵が入っている。しかし、僕はお弁当には、家庭的な卵焼きが入っていて欲しいと思ってしまう。母のそれはもう食べられない味だからこそ、恋しくなるのかは分からないけれど、お弁当のだし巻きは、どこかわざとらしい味がする。前に、養子に入った高齢の姉妹がお弁当の手伝いをしたいと言って、卵焼きをたくさん焼いてくれたことがあった。それは猛烈に甘くて、形も色々になってしまっていたから、結局「ありがとう」と受け取って、自分で食べるに留めたけれど、焦げた部分が何だか愛おしく感じられた。卵焼きを焼くのが、お弁当のおかずの中で一番時間がかかるかもしれない。卵焼き器で、一回で焼けたものを4等分にしているから、お弁当を20個作るなら、五回繰り返す。煮炊きのように放って置けないから、つきっ切りで何度も卵を折り返しながら焼いていく。それはお弁当を作る前日に行って、あら熱がとれるまで巻き簾に包んでおいて、冷めたら冷蔵庫に入れて、一晩置いて味を馴染ませている。
ある企業の取材で、お弁当のおかず一つを詰めたら、コマ送りに完成までを撮影するという機会があった。僕はいつもお弁当の左上に卵焼きを入れることからスタートして、時計回りに詰めていく。定番のメニューは、卵焼き、青菜の煮浸し、切り干し大根、唐揚げ、高野豆腐炊き合わせ、ごはん、焼き魚、漬物、梅干し、茗荷の甘酢漬けという順番。しかし、他の人はごはんから詰めるらしいということを、その時に聞いて、びっくりした。僕は他の人のやり方というのに、あまり関心がいかないので気がつかなかったけれど、試しに色々な人に聞いてみると、ごはんから詰める人が多かった。お弁当をお届けする時、中身が片側に寄ったり崩れたりしていたら、蓋を開けた時にがっかりしてしまう、と言うのだ。僕は、それが嫌で、とにかくぎゅうぎゅうに詰めている。おかずを詰めてから、ごはんをぎゅっと押しこむことで、全体を安定させている。ずっしり重いとも、よく言われる。そんなお弁当が、出会いの機会を作って色々な人にも引き合わせてくれている。本当にあの時、友人が思いつきで言ってくれたことを心から感謝している。
人生で初めて自分でお弁当を作ったのは、母が最初の乳がんで入院した時。入院初日は心配だったので、付き添っていると、お昼に運ばれた食事もほとんど手をつけず、夕食もお椀の蓋を開けては中の煮物を確認して、また蓋をして、そのまま興味がなさそうに、お茶だけを飲んでいた。病気と戦うために、食べられるのであれば、食べた方が良い。体力だって、気力だって、食べて力をつけてこそだと思った。このままでは、手術に耐えられないのではないかと思った。翌朝、お医者様の許可を得て、いつも食べているようなパンと、コーヒーをポットに入れて持っていった。「いいのよ、私のことは気にしないで」と言いながら、食べていた。お昼には、重くないサンドイッチのようなものを届けて、夜にはお弁当を届けた。台所の棚を探していたら、僕が使っていたお弁当箱が出てきた。そこに、唐揚げや、焼き魚、卵焼き、ほうれん草の胡麻和えや、ひじきを入れた。ごはんの上には、梅干しを一つ。昼、夜と行くこともあれば、昼にまとめて届けることもあった。とにかく何でもいいから、食べて力をつけて欲しい。僕がすくすく育つことを願って、母が今までしてくれたように、僕は必死でお弁当を作った。毎日、ちゃんと食べてくれるのを見届けて、家に帰っていた。言葉を多く交わす親子ではなかったから、そのお弁当を介して大丈夫?とか、早く良くなってね、と、お弁当越しに労りの気持ちを伝えていたのかもしれない。
子供の頃、今はもうなくなってしまったが、故郷の水戸には仕出し弁当を手がける「鈴木屋」というお店があった。水戸黄門にあやかったご当地水戸の印籠駅弁なども手がけていて、良心的な値段、家庭と料理屋の間くらいの味がちょうど良く、我が家ではちょっとした集まりごとや、父が亡くなった時、お手伝いに来る人や僕達家族の手軽な賄いごはん、葬儀の時や後の法事まで、いつも鈴木屋の弁当が寄り添うようにあった。唐揚げ、焼き魚、程よい味付けの煮物、どれも美味しかった。駅の売店で売っていた唐揚げ弁当も学生時代にはよく食べた。僕が思い浮かべるお弁当屋さんのイメージは、その鈴木屋である。
かつては、そういう昔からの伝統を踏襲した弁当屋がどこの街にもあったのではないかと思う。今は気軽に、色々な弁当が手に入る。それは、便利なことだし、歓迎すべきことかもしれない。僕のお弁当に入れているおかずの地味なこだわりの一つは、焼き魚である。冷めても美味しいように、粕漬けにしている。塩焼きだと、冷めた時に、ちょっと臭みが出るような気がしている。冷めると少し硬くなるが、それも味わいの一つ、少し焦げ目のついた皮の部分は、カリッとして美味しい。鯖と鮭を使うことが多いけれど、粕漬けの魚は存在感があり、全体の味のバランスに大きく貢献してくれている。鮭やサバというのは、どこの家庭においても懐かしい存在ではないだろうか。
僕は、どこかの街で、誰かの暮らしや、人生に寄り添うような弁当を恋しく思っている。島で宿をやっていた頃によく出かけた、中華と焼肉を提供するお店のご主人が、その季節の営業を終えて東京に戻る僕らが船の上で食べようと頼んだ「唐揚げ弁当」をとりに行った時のこと。「俺はこのくらいしかしてやれないから、持っていけ」と、お代を受け取らなかった。普段は口の悪い豪快な主人が、休憩中の客席で吸っていたタバコを消しながら「またな」と厨房へ消えていった背中は、どこか寂しそうだった。船の甲板で、その年に宿を手伝ってくれた友人と食べた弁当はいつもより、優しい味がした。最近そのご主人の体調が、あまり良くないという話を聞いた。またいつかあの弁当を、島へ出かけて皆で一緒に食べてみたい。その時は、心配になるような優しい言葉よりは、どこか口の悪さを感じるような言葉でも、かけてもらいたいと願っている。僕のお弁当も、誰かの記憶に残っていたら、嬉しい。お弁当のことを書いていたら、駅弁を買って、どこかへ旅に出たい気持ちになった。旅の帰り道、その余韻を感じながら食べる弁当が好きだ。友人の出身地である、広島にある「むさし」という店の、おにぎりと唐揚げが入った弁当をいつか食べてみたいと思っている。