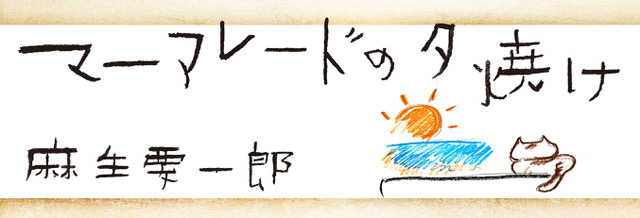第14回 島の大切な友達
僕は、息苦しいような狭い人間関係というものが苦手だ。
そりゃ、そんな関係は、誰だって望んでいないかも知れないが、下町で3世代同居の家に生まれ育ち、商売をやっているような知り合いがいる。家族や従業員、ご近所衆にはお客さん。良い距離感で、時にはぐっと近寄りながら、チャキチャキと上手にこなしている姿を見ると、あそこまでとは言わなくても、もう少し上手にこなしたいものだと思ってしまう。
故郷の小さな地方都市、会社の後取り息子として生まれ育った。ちょっと街を歩けばすぐ誰かに会ってしまい、愛想笑いを振りまかないといけない。誰かと、適当な話題を見つけて、やり過ごすというのも散々やってきたので、割合に自由な立場の今の自分には、そういう会話には意味がないと思ってしまう。「朝夕は気温も下がって、幾分涼しくなりましたね…」などと、わざわざ言うのも、白々しいと思って口が開かない。東京が気楽なのは、たくさんの人がいて、色々な街があり多様なコミュニティがあるから、そういう煩わしさや、息苦しさが全くないところではないかと思う。何かを避けようと思えばいくらでも避ける事が可能で、楽しく過ごす事が出来る。しかし小さな都市、田舎だとそうはいかないのである。避ける事は難しく、常にきちんと向き合わなければならない。そういう暮らしをやめた僕が、小さな島で宿を始めた事は、新たな挑戦だった。手入れされ過ぎていない、島の穏やかな景色、きれいな海や、夕焼けが、僕をその気にさせたのだと思う。
宿をやっていた島の人口は2,500人程、苗字もいくつかに絞られている。つまり皆、少し代を遡れば、親戚になってしまうような規模だ。僕らの場合、小学校で上手く環境に馴染めなくても、中学や高校でコミュニティを変えていく事が出来るけれど、島という環境では、幼稚園や小学校の時の人間関係がそのまま、ずっと大人まで引きずられていく。僕にしたら、考えただけでちょっとため息が出てしまう。もちろんその反面には、同じだけの良い面もあるのだと思うけれど、僕には想像がつかない。初めて訪れた島の居酒屋で、いい年の大人が酔っ払って腕相撲をして、揉めていた。その何気ない様子に、人間関係の縮図があるようにも思えた。きっと勝った方は子供の頃から勝ち続けていて、負けた方はずっと負けているのだ。逆転のチャンスがあったとしても、逆転する事ができない空気が、そこにはあった。僕は、負けたおじさんの何か言いたげな表情や、その背中にエールを送った事を覚えている。
島に行くようになって、初めて出来た友達は、僕より少し年上で、島にお嫁に来た漁協で働く素敵な女性だった。もともとは、僕の友人が当時やっていた黒猫のブログの読者の方だった。その友人の紹介で、僕らは出会う事が出来た。宿の準備のために、一人で島に行った時、船が着く時間に港まで迎えに来てくれた。エンジントラブルで船が、かなり遅れて到着して心細かったのだが、彼女が港で手を振ってくれているのを見て、ホッとした。お昼を過ぎると、島の飲食店はどこも閉まってしまうから、わざわざお昼まで用意してくれていて、そのあたたかな気持ちが嬉しかった。誰かを受け入れる、何気ない優しさや、気遣いみたいなものは、島で宿を始めるにあたり、とても良い気づきでもあった。宿を始める準備をしている時、始めてから、彼女はいつも僕を懸命に助けてくれていた。しばらく彼女が姿を見せない時があり、後日、島の人間関係で、ちょっと嫌な思いをしていた事を知った。少し経ってから彼女と会った時「せっかく新しい事を始めたのに、島の事で嫌な気持ちを持たせたくなかったから」と、涙を浮かべながら言った。常に、相手の気持ちに寄り添いながら彼女は島で生きて来たのだと感じた。彼女は、今、自分でカフェを営んでいる。僕の母が亡くなった後、閉店した宿の片付けがてら、島へ出掛けた時に、久しぶりに再会した。扉を開けると、彼女の目には涙が溢れていた。島に来た母にも会っていたし、僕の悲しみをしっかりと理解してくれたのだと思う。あれからもう、しばらく会っていなけれど、彼女は僕の大切な友人だ。
僕が子供の頃、突然友達がピンポーンとチャイムを鳴らし、遊びに来るという事があった。今は子供の世界でもそういう事は、あまりないのだろうか。大人になると、突然誰かの家に行くというのは避けるようになる。悪いとか、びっくりさせてしまうとか、遠慮する事ばかり考えてしまう。それは相手に配慮した結果なのだが、会いたい、話をしたいという純粋な思いこそ、本当は人間関係においては一番大切なのではないかと思う。
島で通信会社に勤務している彼と出会ったのは、島を訪れるようになり2回目くらいの時だったと記憶している。島で人気のバンドのリーダー、年齢も近かったのですぐに打ち解けた。その次に島へ行った時に、宿の開業準備で片付けをしているとガラッと戸が開いて、彼が姿をあらわした。連絡をしようと思っていたら、やって来たので驚いた。どうして僕が島に来たことが分かったのか尋ねると「港で見かけたから!」と笑顔で答える。突然、何の前触れもなく、家に遊びに来る感じが、とても新鮮だった。何か童心に返るような気分もあり、一気に距離が縮まるような感覚だった。彼には、本当によく助けてもらった。ある時、皆で桟橋から釣りをしていたら、通りがかった彼が車の窓を開けて「何をしているの?」と言う。桟橋から釣り糸を垂らしているのだから、釣りに決まっているじゃないかと思ったが、「釣りだよ」と答えると「そこに魚いないよ」そう教えてくれた。桟橋の上から魚が泳いでいる様子は見えたけれど、粘ったところで一匹も釣れない訳である。何かあった時、余所者の僕らに対して、客観的な視点でアドバイスをしてくれる、信頼出来る友達だった。釣りの話は、島の事を知らないと、そういう事になるという例で、島で宿を営み暮らすと、島の人たちが「そこまでは、気にしなくて良いと思う」とか、「こうした方が良いよ」と、いつでも客観的で正確なアドバイスをしてくれた。宿から漏れる音が騒がしいと近隣のお宅と揉め事が起きていた時に、酔っ払った隣のおじさんが、勢いよく宿に乗り込んで来た際、彼が割って入ってくれた事があった。僕が謝りに行こうとしたのを制して「これは俺達の仕事だから」と、酔っ払ったおじさんと話をつけるべく、彼が何人かの仲間と、毅然とした対応をしてくれた時の、格好良さを今でも覚えている。同時に、僕の管理の至らなさから起きた事、島で暮らす者同志を揉めさせてしまって、申し訳ないなと心苦しく思った。宿を閉めてもうしばらく経つけれど、今も春先に、山に入って自分たちで積んできた、新芽の明日葉を彼が送ってくれる事がある。スーパーで売っているのとは雲泥の差、春の優しい苦味がある新芽の明日葉が僕は好きだ。天ぷらにしても、お浸しにしても、本当に美味しい。もし、彼がいなかったら、僕らは何年も宿を続ける事は出来なかったかも知れないと、時折思い出しては、感謝している。
先日、「住所は変わってないですか?」と、要件だけの簡単な連絡があって、変わっていないと伝えると、数日後に大量のサザエが届いた。彼女は、当時島で看護士さんをしていたが、今は別な場所に移っている。几帳面で、真面目な性格が彼女の魅力。当時は島で数少ない移住組、僕らの良き相談相手であった。宿のお客様のごはんが終わって、さあ皆で賄いという頃に彼女がやって来て、一緒にご飯をする事が多かった。食後には、大量の洗い物もよく手伝ってもらった。食器のしまう場所などは、誰よりも把握していた気がする。メンバーが入れ替わる宿の、毎年、毎年の様子を見ているから、今年はこういう空気感なのかと感じ取って、一緒に伴走してくれていた。毎年のスタッフ達にとっても、良き相談相手だった。去年もこんな感じでしたよ、きっと大丈夫だと思います。ときちんとした言葉遣いで、スタッフ達に言っては、背中を押してくれていたような気がする。僕にとっても、当然良き理解者だった。ちょっとこれ手伝ってよと、遠慮なく言える数少ない存在。「大変ですね!」と、忙しい時期にちょっと呆れたような表情で、笑いながら彼女によく言われていた事を思い出す。彼女とは、しばらく会っていなくても、会った瞬間にその時の関係にすぐ戻れる、そんな身近さがあるような感じがしている。
僕らは、毎年ゴールデンウィーク前に島へ行き、10月の初めにはその年の営業を終えて、東京へ戻っていた。冬の間は、海が荒れる事もあって、運行する船の本数も減ってしまう。欠航する事だって、しばしばある。そこには、抗えない何か大きな閉塞感を感じる。島でずっと暮らしている面々も、ゴールデンウィーク前の海が透明で綺麗な色になる頃、そのことをそれぞれが久しぶりなんて話をしている。寒くて、風が強い時期に、内なる時間をそれぞれが過ごしているのだろう。春から秋という営業期間を決めたのは正解だった。多分、そういう内なる時間まで過ごしていたら、僕はもっと早い段階で島に疲れてしまっていたと思う。
夏になると、島で過ごした時間を思い出す。一緒に働いてくれた宿のスタッフ達はもちろんだけど、そうやって、あたたかい眼差しで見守ってくれた友人達がいてくれたからこそ、続ける事が出来たのだ。時間が経てば経つほど、その感謝の気持ちは高まっていくばかりである。またいつか、島にふらっと遊びに出かけたい。泊まった宿に、「港で見かけたから」と、また友は前触れもなく訪ねて来てくれるだろうか?