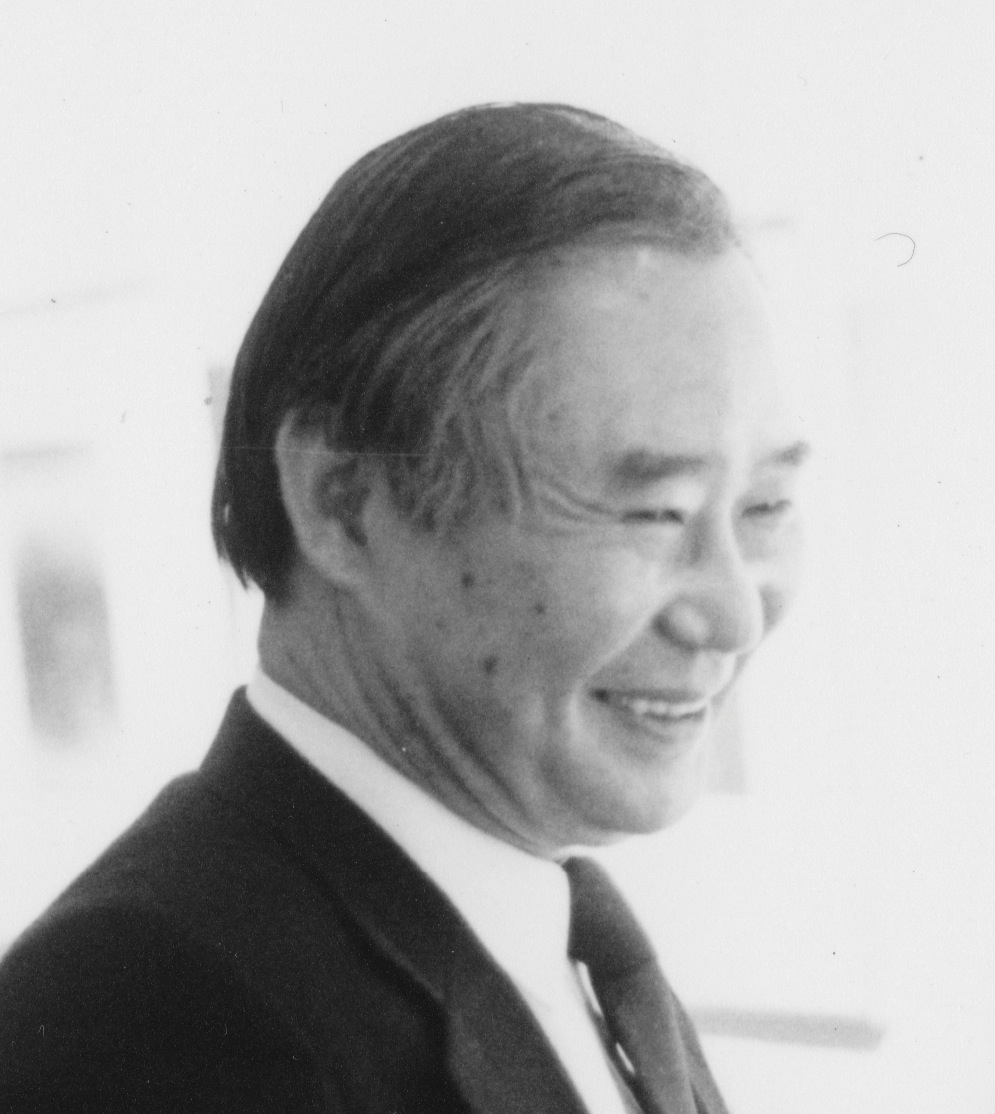第8回 東京の日々のはじまり
「フランス大使館に招かれましたので、その招待をお受けする旨返事しました。到着後3日ないし4日、泊めていただくことになります」――横浜到着の予定日時を知らせてくださったお手紙には、そういう一節もふくまれていました。あの朝、私にとっては旧知の文化部アタッシェD氏があなたの出迎えに大桟橋まで来ていたのはそのためでした。私が埠頭に着いたときには、やはり大使館差し回しのワゴン車に手荷物類がすでに積み込まれ、走りだすばかりになっていました。おくれてしまった私の恐縮は、しかし、あくまでも寛大で晴れやかなあなたの微笑のおかげで瞬時に解け消えました。しかもD氏が車のドアを開けて、あなたが乗り込むのを待っているのに、あなたは私の車で東京へ向かいたいとおっしゃったのでした。D氏の車にはジェリーが乗り込みました。パリいらい半年ぶりの再会をそのような形にしてくださったのは、友情の新しい証しでした。
あなたを招いたのは、大使館というより大使夫妻というべきでした。当時の駐在フランス大使はドフレーヌ・ド・ラ・シュヴァルリーといい、いかにも中世以来の古い家柄を思わせる名前の方でした。東京でのあなたの最初の宿は大使公邸だったわけですが、お着きになったときはほっとされたと思います。長旅が終わったからという理由は別にしても、横浜から大使館のすぐそばの天現寺の出口まで高速道路の連続でしたから、川崎あたりの工業地帯をはじめ、途中の景色はどう見ても殺風景だったからです。
公邸での滞在を到着後3、4日と考えていらしたのは、早い時期に北海道を旅したいと思っておられたからかもしれません。実際、最初の日本国内旅行としてあなたが考えていたのは、羽田から釧路か女満別まで飛行機で飛び、そこからジェリーの運転するレンタカーで北海道を回るというものでした。彼の運転の腕の確かさは私にもわかっていましたが、道路標識や案内板が漢字だけで書かれていることを考えると、どうにも無理な計画に思えましたから、率直にそう申し上げたのですが、とにかく航空路線やホテルのことを調べてみたいということだったので、いちおう東京駅構内の交通公社までご一緒しました。しかしジェリーが国際免許証を用意していなかったので、それではレンタカーも借りられないことがわかり、せっかくの計画でしたが実現しませんでした。あなたが諦めてくださったので、ほっとしたのを思い出します。
出発前にあなたが想像していらした日本は、いろいろと夢をふくらませるものだったようです。Petite Plaisanceをお訪ねしたときも、京都の東山あたりに家を一軒借りてしばらく住んでみたいとおっしゃったのをおぼえています。そう伺ったときの私の反応はもちろん否定的なものでしたが、考えてみれば私自身京都の住宅事情にくわしいわけではありませんし、もしかしたら誰か頼りになる人をご存知なのかもしれないとも思いましたので、その夢を頭からつぶすようなことは申しませんでした。もしかしたらあなたが考えていらしたのは「源氏の君の最後の恋」に描かれた庵や『方丈記』のイメージに近いものだったのかもしれません。北海道に関しても、あなたがなぜ最初に行ってみたいと思われたのか、はっきりした理由はわからずじまいでした。秋の訪れの早い土地だから早めにということなのかもとも思いましたが……。
それにたいして、歌舞伎鑑賞はすぐにも実現可能は計画でした。当時の手帳でたしかめてないたのですが、あなたが最初に新橋演舞場に足を運んだのは、到着の翌日10月5日のことでした。ちょうど授業のない日でしたから私もお供しました。出し物のひとつは「義経千本桜」の四段目「道行」でした。歌舞伎の公演ですから演目はほかにもあったはずですが、それが何だったか思い出せません。吉野で義経と別れた静御前が佐藤忠信をお供に京へ帰る「道行」の記憶だけがはっきりのこっているのは、あなたとの会話のなかで、義経や弁慶がかなりしばしば話題になり、あの出し物についても何度か話したことがあったからです。それに忠信を演じた俳優の演技がみごとだったからでもあります。佐藤忠信はいうまでもなく実在の人物であり、平泉の藤原秀衡のもとで少年期をすごした義経に郎党として仕え、最後まで忠誠を貫いた人ですが、この芝居では狐の化身ということになっています。静御前の鼓には忠信狐の母親の皮が張られており、彼が静のそばをはなれようとしないのは、ひとすら母狐恋しさからだという設定。その設定を決して荒唐無稽なものと思っておられないことは、あなたの言葉のはしばしに感じられました。
遺稿集として1991年に刊行された『牢獄巡回』は、15篇中11篇が日本滞在に関する記述ないし省察からなる本で、その表題は『黒の過程』のなかのゼノンの言葉(すくなくとも一度自分の牢獄を巡回することもなく死ぬなどという無分別な人間が誰かいるだろうか?)に由来しますが、この場合、「牢獄」は「世界」ないし「地球」を意味しています。そのなかのひとつ「歌舞伎・文楽・能」に次のような一節があります――「7回か8回にわけて、私は歌舞伎見物に42時間費やした。それでもまだ見足りなかった。新機軸でもなんでもない自称新機軸、風変わりだというだけで新しいものと信じられている演技にあきあきし、ひきつったような、あるいは傑作の背中にぐったりよりかかっているだけの自惚れにあきれはて、俳優たちの演技で満たすには程遠い空っぽの舞台にもうんざりして、私は劇場を避けていた。たとえ出かけるにしても例外的にでしかなかった。歌舞伎が私に失われた食欲を取り戻させてくれた」
あなたが現代の日本のなかに探し求めていたのが、本質的に古い日本、伝統的な日本であったことは否めませんが、それを懐古趣味とか異邦趣味などといった言葉で片づけるわけにはいかないことを、私は強く感じておりました。10月中旬の「奥の細道の旅」の際、そのことをいっそう強く心に刻まれることになりますが、その旅についてはもう少し先で述べたいと思います。
10月8日には大使公邸であなたの歓迎晩餐会が開かれました。会食者は40人ほどだったと思います。そのなかでとりわけ鮮明に記憶にのこっているのは三島瑤子夫人です。夫人の席が私の真向かいだったのです。その晩は当然いろいろと言葉を交わすことになったわけですが、実はそれが初対面ではありませんでした。以前にすくなくとも三度お会いしたことがあったのです。とはいえ瑤子夫人が私のことをおぼえておられたとは思えません。最初はマーゴ・フォンテーンとルドルフ・ヌレエフがはじめて来日したときのバレエ公演の会場で、ロビーで三島氏とご一緒のところをお見かけしただけでしたし(1963年のことです)、二度目は三島氏にインタビューを申し込んだあるフランス人の通訳としてお宅に伺ったときでしたが、訪問者とはいっても私は添え物にすぎなかったのですから。三度目は、ピエール・ド・マンディアルグがフランス語に訳した『サド侯爵夫人』を、当時オデオン座に本拠をおいていたルノー=バロー劇団が青山の草月会館で上演したときのことです。劇団とともにマンディアルグも来日していました。新宿の紀伊國屋ホールで一度だけ彼の講演が行なわれたのですが、その通訳をたのまれた縁で、三島夫人の催したレセプションに私も招かれたのでした。マンディアルグ夫妻をはじめ劇団関係者全員が顔を揃えており、私は大勢のなかのひとりにすぎませんでした。
10月末、夫人は、あなたとジェリーと私を、馬込のご自宅での晩餐によんでくださいました。その晩餐を思いつかれたのは、大使公邸の宴の際だったのではないでしょうか。夫人の席は、主賓であるあなたから見て右に3人目、私はその向かい側、横に長い大テーブルのほぼ中央に近い席でしたから、当然私の右にも左にも客はいたわけですが、それが誰だったか思い出せません。まるでスポットライトがあてられていたかのように、三島夫人のことだけが鮮明に記憶にのこっています。
『三島あるいは空虚のヴィジョン』の末尾に近く、三島が市ヶ谷の陸上自衛隊司令部であの激しい死をとげた日の家族の反応を記したくだりで、あなたは瑤子夫人についても言及しています。すくなくとも初版の次のような文章を読んだ限りでは、三島夫人にたいしてあなたは批判的な気持ちを抱いておられたように思われます。「妻の瑤子がそのニュースを聞いたのは、ある昼食会にでかけるために乗ったタクシーのなかであった。のちに質問されて彼女は、夫の自殺は覚悟していた、しかし一年か二年後だろうと思っていた、と答える(ある日三島はこういった――「瑤子には想像力がない」)。唯一感動的な言葉を口にしたのは彼の母である……」。しかし、8日の晩餐会がおたがい面識を得る機会となり、あなたの日本滞在中、何度も食事をともにしたり、京都や奈良をいっしょに訪れたりするうちに、瑤子夫人にたいするあなたの認識は改まっていったように思われます。あなたの死後1991年刊行のプレイヤード文庫版『エッセ―と回想』に収録された『三島あるいは空虚のヴィジョン』の決定版では、さきほど引用したくだりの「瑤子には想像力がない」という三島の言葉に次のような脚注がつけられているのです――「事実、日本人の想像力は外部ないし他者に向けられないことが多いのかもしれない。しかし三島は生気にあふれた若い妻のいくつかの資質を見誤っていたように思われる。一度ならず、とりわけ夫の自死の若い共犯者たちを弁護し、彼らの刑期を短縮させることが問題となったとき、三島夫人は勇気と現実感覚の持ち主であることを示した」
あなたの公邸滞在は、結局、「奥の細道への旅」に出かける10月中旬まで延長されました。大使夫妻の歓迎の意は晩餐会に集約されており、のこりの日々はいっさいあなたの自由を束縛することなく、公邸の設備を提供することにつきていたようですが、それが最大の好意の表現であったことはいうまでもありません。滞在が予定より大幅にのばされたのは、とりわけあなたにたいする大使夫人の親愛感のせいだったように思われます。『牢獄巡回』に収録された「墨絵の顔」のなかに、大使夫人について次のように述べられています――「私と同じく、なかばフランス、なかばベルギーの血筋を引く北国の女性。丁寧に探索したら私たちの共通の祖先が見つけられるようにさえ思う。私があえて言いたいのは、私たちのあいだには親愛感があったことである……」。私自身、別の機会に、ある共通の友人の病室で、大使夫人とごいっしょにいくばくかの時間を過ごしたことがあり、慈母という言葉を連想させる人柄に感銘を受けていましたので、この一節には深くうなずいたものでした。
◇初出=『ふらんす』2000年11月号