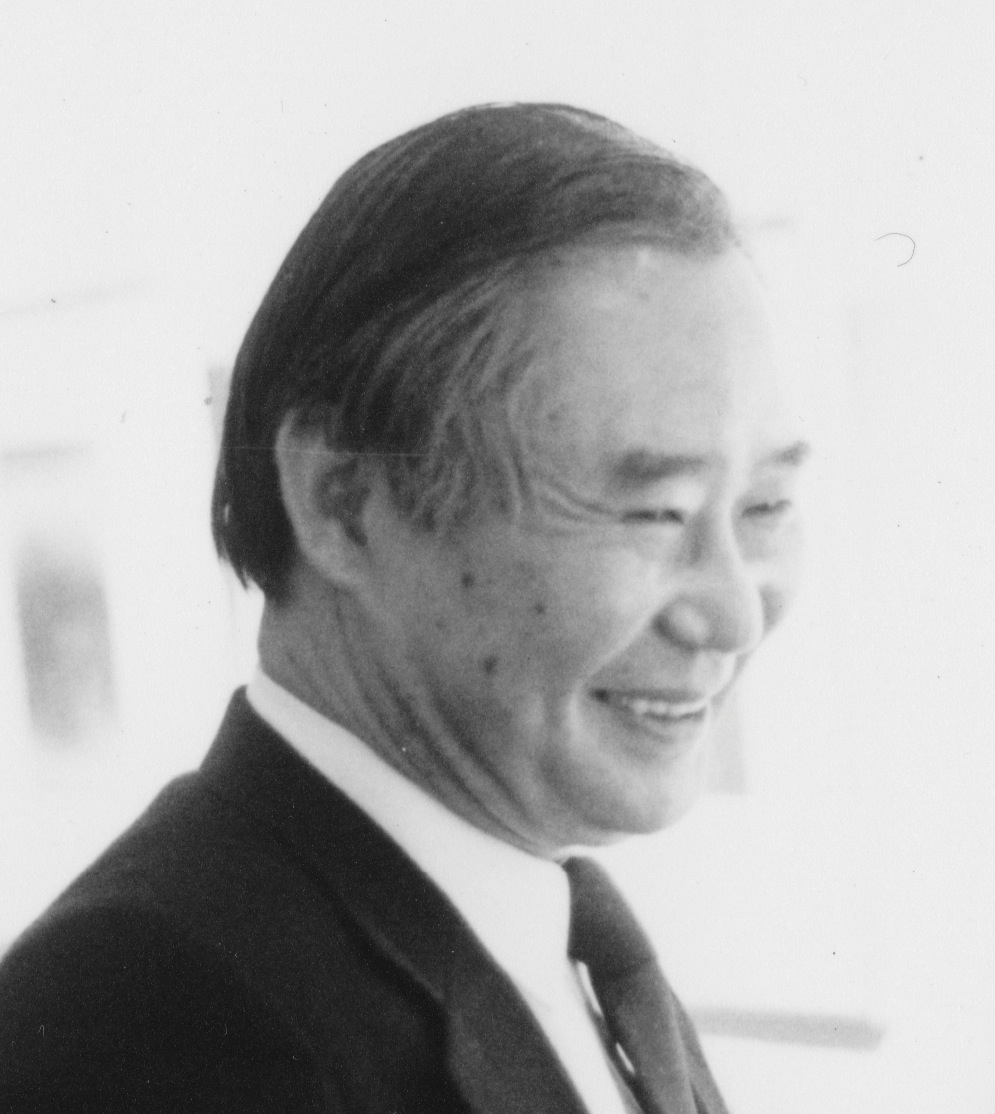第6回 パリふたたび 1981年秋ー1982年春②
ご一緒にガリマール邸の晩餐会に赴くためホテルをお訪ねした日のこと。まだ少し時間があるのでお茶でもということになり、最上階に近いお部屋まで伺いました。ホテルに限らずパリの古い建物によく見られるものですが、階段の隙間を利用してあとから設置されたエレベーターの「終点」まで昇り、さらに半階分階段を上った階の部屋でした。その短い階段を登るあなたの足取りがいかにも軽やかで、まるで若い娘のようだったのを思い出します。あの日あなたにはなにか心はずむことがあったのでしょうか。
Petite Plaisanceでお別れしたあとに訪ねたスミス・カレッジのこと、フランス人の古い友人クリスチアン・モリユーが駐米大使館文化アタシェとして勤務していたワシントンを訪れたときのこと(彼は私と一緒にモン・デゼール島を訪れる予定だったのですが、公務のためその計画は実現しませんでした)。ソールズベリーやストーンヘンジのこと、そしてやはりラルボーのことなど、あれこれ話合っているところに、外から電話がかかってきました。相手が誰なのか、もちろん私にはわかりませんでしたが、かなり立ち入ったことも話せる親しい人だったのは確かです。というのも、話題は共通の友人らしい人の病状だったのですが、その人の病気が癌であること、回復の望みはまったくないこと、それどころか命旦夕に迫っているというのが実情であることを、あなたは率直に告げていたからです。
あとからわかったことですが、その人はモーリス・デュメーといい、ジェリーの「アミ」でした。2年前グレース・フリックの存命中に、フランスのあるテレビ局がモン・デゼール島であなたの訪問インタビュー番組を制作したことがありました。デュメーはそのディレクターであり、ジェリーもスタッフの一員として取材に加わっていたのでした。80年秋、ジェリーをともなうはじめての旅のとき、あなたはデュメーの家に住んだのでした。ソールズベリーからのお手紙に公の住所として記されていたのはそのアドレスにほかなりませんでした。
あの日の電話であなたは、アメリカの医師たちとはとりわけ癌患者にたいして驚くほど率直だが、フランスでは医師以上に家族が、病人につまらぬ隠し立てをしようとして時間を無駄につぶしている、私はそういうやり方に賛成できないと話しておられました。癌の告知をめぐっては、ここ数年日本でも状況が変わってきたようですが、20年前のあのころは告知すべきではないとする医師が多かったように思います。
10年以上癌と戦いつづけたグレース・フリックに身近に接していたあなたにとって、それは当然の反応だったかもしれません。しかしあなたの場合、たとえ回復の可能性が皆無であっても医師と患者の関係は透明であるべきだという考えは、深い省察を経た上での選択だったにちがいありません。マチュー・ガレーとの対話のなかであなたはこう述べていました――「私にとって大切なのは、生から死への移行という本質的体験をしくじらないことなのです。[…]私は自分自身の死を準備する人々が好きですし、そういう人々を尊敬します。たとえある種の本能的嫌悪をともなうとしても、自分自身の死のことを、いわば友情をこめて考える必要があるのです」
あなたがある講演のなかで「わが友」と呼んだモンテーニュを連想させる言葉です。なにはともあれ人間の思考というものは、話すにせよ書くにせよ、言語化されてはじめて明確な形をとるものだと思いますが、あなたのなかには、グレース・フリックの経験やさまざまな人との対話を通して、生と死をめぐる思考がしっかりと根づいていたのだと思います。
いやむしろ、生と死の問題は最初からあなたの思索の中心を占めていたと言うべきかもしれません。事実そのことは、あなたの作品の多くが主人公の死によって終わるという事実に反映していると思います。
作品を主人公の死でしめくくるのは、ある意味で月並みな手法だといえましょう。死はすべてにけりをつけると考えることもできますから、小説を終わらせる手段として主人公を死なせるのはよくあることです。しかしあなたの場合、主人公の死は手段や技法とは完全に無縁なものだといわなくてはなりません。生から死への移行を本質的問題と考えていたということは、死がすべてに終止符を打つもの、すべてにけりをつけるものでは絶対になかったということにはほかなりません。
Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts(目を見開いたまま死の中に入ることに努めよう)という『ハドリアヌス帝』の最後の言葉が、なによりもよくそのことを示しています。「死の中に入る」という表現が私たちの注意を引きます。死はもうひとつの世界であり、決してすべての終わりではないのです。
『黒の過程』の最終章は「ゼノンの最期」と題されており、この小説もまた主人公の死によって終わります。火刑を宣告されたぜノンは、刑執行の前夜、獄屋で手首の動脈を切り、みずから生命を絶ちます。裁判官の許可を得て手元に戻された筆記用具箱の蓋の裏に、2インチにも満たない薄い刃を貼りつけていたのでした。「まわされる鍵や押し戻される錠のきしみは、彼にとってもはや開かれる扉の鋭い音にすぎなかった。そしてそれが、ゼノンの最期をたどって行きつくもっとも遠い地点であった」という最後の文章はとりわけ深い印象を残します。字面で見ればそれは、扉の下から廊下に流れ出た血溜まりに気づいた獄吏が、あわてて開く独房の扉のきしみにすぎないのですが、その扉はまた、生死の境を越えて死の世界に歩み入るゼノンのために開かれた扉でもあるからです。ゼノンの最期はもうひとつの世界に開かれているのです。
あなた自身「若書きではあるが最後まで愛着をおぼえる本質的作品のひとつ」とおっしゃった『姉アンナ…』もまた、主人公ドンナ・アンナの死の場面で終わります。「とはいえ臨終の苦悶は長く苦しかった。フランス語は忘れてしまっていた。イスパニア語の単語をいくつか、それにイタリア語をすこし書物で習い覚えていたのを自慢にしている礼拝堂付きの司祭が訪れて、ときおりそのどちらかの言葉で励ました。しかし瀕死の女(ひと)は聞いていなかったし、意味をほとんど通じなかった。もう目が見えなかったにもかかわらず、司祭は彼女のまえに十字架を差し出しつづけた。ついにやつれ果てたアンナの顔がゆるんだ。瞼がゆっくりと閉じられた。彼らは彼女がつぶやくのを聞いた。〈Mi amado…〉」
Mi amado(私の愛する人)というのは、かつてはナポリのサン・テルモ砦の分厚い壁のかげで五日五夜の激しい幸福をともにした弟のミゲルにほかなりませんが、彼女の死は、その幸福が「永遠のあらゆる片隅を反響と反映で満たしている」世界なのです。
『とどめの一撃』が女主人公ソフィーの死によって終わるのは、題名が示している通りです。またすでに述べたように『無名の男』をしめくくるのは、主人公ナタナエルが「草の枕に頭をのせ、まるで眠ろうとするかのように楽な姿勢をとった」という文章でした。あらためて考えてみれば、あなたの場合、死によって終わらない作品のほうが圧倒的に少ないことに気づきます。
受話器を置いたあなたは、私のほうを振り向いて「あなたはどう思いますか?」とおっしゃいました。あなたとの会話では不意を突かれることが多かったのですが、煙草にせよアルコールにせよ度を越していた私は「もし癌になったら、むしろ私だけに知らせてほしいと思う」と答えるのが精一杯でした。8年後、現実に三種類の癌にとりつかれることなど知るよしもない私の、いわば極楽トンボの答えでした。しかし、そういう身勝手な「覚悟」をあなたは嬉しそうに認めてくださったのを思い出します。
あなたは「どこで死のうと地球の上であることに変わりはない」と言い放つ豪胆さの持ち主でした。しかし同時に人間の弱さを知り尽くしているユマニストでもあったことをこの上なくはっきりと示すのは、先ほど引用したガレーとの対話のなかで、次のように付け加えている言葉にほかなりません――「人間は無防備なものだから、いまはのきわにめそめそしたり、恐怖に駆られたりするかもしれない。しかしそれは船酔いのように単純な肉体的反応にすぎない。重要な〈受容〉はそのまえになされているはずです」
あの年あなたが親しい人々を招いてホテルの地下室で催されたレセプションが、その後私にとって掛けがえのない友人となる人々との出会いの場となりました。その第一がファンス・フランクと森村悦子です。リュニヴェルシテ通りのホテルには、ル・モン・サン・ミシェルの騎士の間を思わせるゴチック風の地下室があり、プライヴェートな会合に供されていました。パリにお着きになって間もない日のレセプションはとりわけ強烈な思い出として残っています。ファンスと森村さんは、部屋の奥で若い中国人の訳者と話しこんでいた私のところに、まっすぐ歩み寄ったのでした。入ってすぐ左の壁際には、あなたをアカデミー・フランセーズに推挙して恒例の歓迎演説まで引受けたジャン・ドルメッソンが座っていました。しかし彼との間には電流が通じないというか、まったく会話が成り立ちませんでした。それにたいしてファンスと森村さんは、その後パリを訪れるたびに真先に連絡する親友になりました。あの日ファンスがあなたのレセプションに顔を出したのは、ひたすら私に会うためだったように感じられたのはなぜなのか、長いあいだ私には不思議に思えていました。その疑問が氷解したのは、あなたが世を去られて7年後に刊行された『友人と知己への手紙』を読んだときでした。ファンスにあてた1981年5月14日付けの手紙であなたは、日本にいる最良の友であるイワサキ・ツトムが82年7月までにフランスに滞在することになったので、日本への旅は来年まで延期することになるだろうと書き送っておられたのでした。ファンス・フランクは私とほぼ同じころフランスに留学していたアメリカ女性で、ソルボンヌで哲学を専攻した人ですが、その後陶芸の道に入り、日本でも有田や伊万里で修行したセラミスト[陶芸家]です。あなたも深く敬愛する彼女にとって、『黒の過程』を日本語に訳した人間は特別な関心の対象だったのにちがいありません。
あれから20年、ファンスと森村さんの住むボナパルト街のアトリエは、あなたを主賓とする何度かの晩餐会をはじめ、多くの人々と知り合う機会を与えてくれた場として、パリにおける私の第一の「寄港地」でありつづけています。
◇初出=『ふらんす』2000年9月号