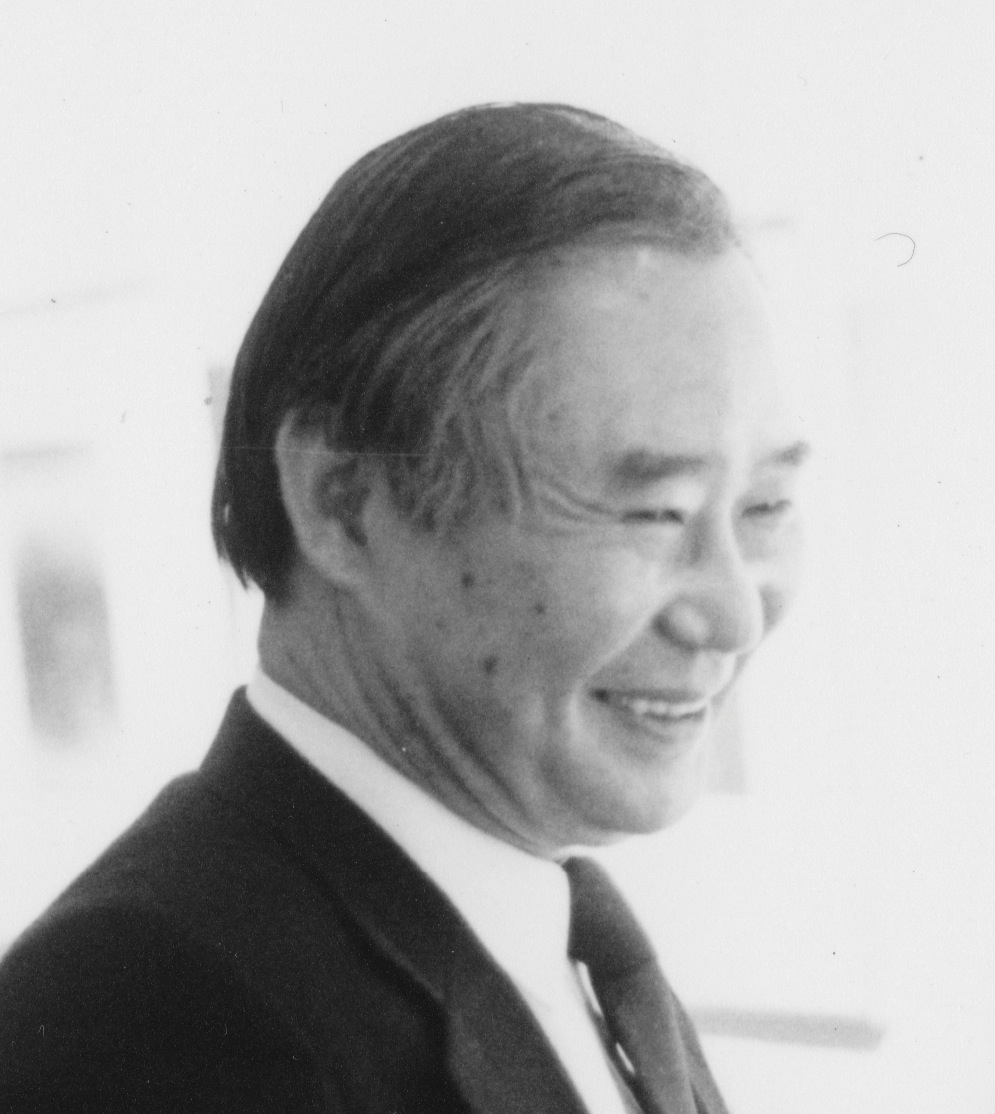第12回(最終回) 1986年秋-1987年春・パリ、ソールズベリ、最後の別れ
この思い出も、あなたとの最後の出会い、最後の別れの前後まで一足飛びしなければなりません。1986年秋から87年春にかけてのことです。
86年の10月から2年間の予定で、私はパリ国際大学都市日本館館長という激務についておりました。30年前留学生としてお世話になった施設なので、恩返しのつもりで引き受けた仕事でした。その館長室に、突然あなたからお電話をいただいたのは、12月初めのことでした。パリにいらっしゃるとは存じあげなかったので驚きましたが、会いたいというお言葉を嬉しく伺いました。「冬はモロッコですごすつもり、でもまだしばらくパリにいるので」とのことでした。翌日早速お訪ねしたのはいうまでもありません。
あの年、ヨーロッパとモロッコへのあなたの旅は、ジェリーを偲ぶ旅だったと思います。1年ほど前からエイズに苦しんでいた彼は、86年2月、パリの病院で孤独な死を迎えたのでした。短い生涯の最後の1年、ダニエル某という人物があなたと彼とのあいだに割り込んできたために、あなた自身おぞましい関係に巻き込まれたのでした。私はその男をじかには知らないので、写真や周囲の人々の証言などから推測するしかないのですが、ダニエル某はまさしくダニのような「死の天使」だったと思います。ジェリーが彼と出会ったのは、1984年9月21日午後7時、ジャコブ街とサン=ブノワ街の角だったとか。あなたの伝記にこれほどはっきりと書かれているのは、誰かのメモあるいは手紙が残っているからにちがいありません。ジェリーの「ひと目ぼれ」だったようです。そしてこの出会いが、彼の死にいたるまで、あなたと彼の関係を完全に狂わせてしまったのでした。ジェリーはもはや私の記憶に残るジェリーではなかったようです。
館長職の話がもちあがる前の86年春、50日余りの日々をミラノですごしました。帰国予定日の前後に、あなたがアムステルダムに立ち寄るはずと聞いた私は、帰国の経路にアムステルダムをふくめることにしたのでした。あなたの旅程に関して正確な情報を下さったのは、秘書役としてPetite Plaisanceで働いていたJeannie Luntさんでした。ジェリーの死からわずか1か月半後のことでした。
「ホテル・ヨーロッパ」のロビーであなたを待ち伏せする形になりました。付近を散歩していたとき、空港からホテルに向かうあなたの車を見かけ、急いで宿に引き返したのでした。たまたま目にした大型車のなかに、オランダの友人たちといっしょのあなたが見えたのです。一方通行の関係で車はかなり大きく迂回せざるをえないので、徒歩の私の方が早く着くだろうと思ったのです。ロビーの私に気づいたあなたは、驚きのあまり目を大きく見開きました。しかしその表情はすぐさまあの懐かしい笑顔に変わりました。「秘書にたずねたんですね」と一言。それでも、ロビーの椅子に腰を下ろすやいなやあなたは両手で顔を覆い、「辛かった」とおっしゃったのでした。呻くような声でした。日本滞在中ジェリーと同じく「旅の伴侶」であった私の顔を見たとたん、彼の思い出が一挙にあふれ出たのだと思います。そしておそらくはおぞましいダニエルのことも。さきほど彼のことを「ダニのような」と言ったのは悪い冗談と思われるかもしれません。しかし実感なのです。言いなりになるジェリーを通して、彼はたびたびあなたから法外なお金を搾り取っていたのです。同じころ心臓発作に見舞われたあなたはバイパス手術を受けたのでしたが、そんなあなたの微笑には、以前とは違う淋しい影が感じられました。
最後に豹変したジェリーでしたが、善きにつけ悪しきにつけ忘れがたい思い出をあなたに遺したのはまちがいありません。パリの宿をガリマール家の館に近いホテルからヴァンドーム広場のホテル・リッツに変えたのも、彼の思い出のためだったと思います。死のほんのすこしまえ、ジェリーはこのホテルの一室で自殺をはかったのでした。あとで知ったのですが、86年の秋あなたが選んだのは、ジェリーが浴槽で自殺を試みた、まさにその部屋だったとか。
冬をモロッコでとお考えになったのも、彼の思い出を追ってのことだったと思います。81年9月小型の単行本として刊行された『姉アンナ…』の「あとがき」を執筆されたのは、その年の春ジェリーとともに訪れたモロッコ町タルーダンでのことでしたから。
モロッコから帰られたあなたは、87年3月のはじめ、ふたたび日本館にお電話をくださいました。「2月初旬にはパリに戻っていたのだけれど、風邪をこじらせて静養をせざるをえなかった。しかしやっと回復したので会いたい。よければ明日の午後、お茶の時間にどうぞ」というお誘いでした。もちろん伺いました。ファンスと森村さんもいっしょでした。風邪で臥せっておられたとはいえ、モロッコにお出かけになる前に比べればはるかにお元気そうで、ほっとしました。しかしいろいろお話ししているうちに、ラバトからお帰りになったのが2月8日だったと伺ったときはとても残念に思いました。というのも私自身2月初旬にラバトにおもむき、パリに戻ったのが7日でしたので、まだモロッコにおられると知っていたら、たとえひと目でもお会いできたかもしれないのにと思ったからです。
モロッコの土を踏んだのは、あとにもさきにもあの時だけですが、私にとってあの4日館のラバト滞在は忘れがたい体験でした。そのとき私に与えられた任務は、なんとモロッコ王太子へのご進講なのでした。いまは国王になられていますが、王太子がはじめて日本を公式に訪問なさる予定があり、そのためにあらかじめ日本についていろいろ知っておきたいというご希望なのでした。大使館文化部の参事官からその依頼を受けたときは、あまりにも思いがけない話でしたし、1回1時間2回のご進講で、日本文学のあらまし、相撲のこと、歌舞伎のこともという盛りだくさんな要望だったので、とてもその任ではないと一度お断りしました。しかしぜひ受けてほしいという重ねての依頼でしたし、モロッコという、映画でしか知らなかった世界に実際にこの身をおく機会はほかにないかもしれないという気持ちも働いて、結局お受けしたのでした。日本から小林善彦さんも飛来し、ごいっしょにラバトに向かいました。
王立学校の玄関前で、校長はじめモロッコ側のスタッフ数名といっしょに王太子をお迎えしたとき、その場ではどう解釈したらいいのかわからなかったある仕種を目にしました。王太子が出迎えの人々と握手するために手をさしのべたとき、校長が急にひざまずき、その手の甲に唇をあてようとしたのです。深い敬意の表現でした。ところが王子はすっと手を引いてしまわれたのです。私には「お前にさわられるのは嫌だ」といわんばかりの反応としか思えませんでした。しかし不思議でした。その意味がわかったのはパリに帰ってからでした。ラバトで買って帰った本のなかに、その仕種の意味を説明する一節があったのです。たとえば民芸品の工房で師匠が弟子の挨拶を受けるとき、師匠は弟子にたいして同じ仕種をする。「目上のものは、相手がそれほどまで自分を卑下するのを拒否する」というのです。納得しました。
当時23歳と伺っておりましたが、王太子は飾り気のない、好感のもてる青年でした。王立学校図書室で行なわれたご進講のとき、私の席の後ろに白板が用意されておりましたが、あまりにも後ろに離れていたので、始める前に私はもっと近くに引き寄せようとしました。すると王子はご自分の席を立って私に手を貸してくださったのです。感動しました。真の高貴さは単純さのなかにこそあると思うのですが、まさにその高貴さが感じられたからです。ご進講中の率直なご質問も印象深いものばかりでした。そんな体験の場であっただけに、ラバトであなたとお会いする機会を逸したのはほんとうに残念でした。
リッツのお部屋での思い出のなかで、いまも忘れられないことが2つあります。ひとつは『黒の過程』を映画化することになっていたベルギーの映画監督アンドレ・デルヴォーにお会いして、シナリオの出来栄えに満足していらしたことです。シュレンドルフによる『とどめの一撃』には強い不満を感じておられたことを知っている私としては、とても嬉しいお話でした。デルヴォーの『黒の過程』は話をゼノンのブリュージュ蟄居にしぼりこんでおり、原作に漂う緊張感をみごとに表現していました。しかしその『黒の過程』がクランクアップしたのは、あなたが亡くなられたあとでした。あの映画はカンヌ映画祭にも出品されたのでしたが、あなたはついに見ることができませんでした。生来の映画好きにもかかわらず、館長職の2年間に私がパリで見たのはあの映画だけでした。あなたの代わりにというのはおこがましい限りですが、そんな気持ちでサン・ジェルマン・デ・プレの映画館に出かけたのを覚えています。
もうひとつは、アメリカに帰るまえにしばらくソールズベリで静養するつもりとおっしゃったことでした。激務とはいえ、復活祭には1週間ほど休暇をとれることになっておりましたので、イタリアを旅するつもりでした。あなたのイギリス行きが、私の休暇の初日と同じ日と伺ったとたん、私は休暇の前半をイギリスですごそうと決心しました。ソールズベリのあなたの定宿は、かつてラルボー巡礼のとき泊まりそこねた古い宿「薔薇と王冠」荘とわかっていましたから、すぐに予約を入れました。たとえ一晩でもいい、ずっとまえからあなたとのかかわりで一度は泊まってみたいと思っていた宿でしたから、そこでお会いできれば本望という気持ちでした。シェイクスピアの故郷ストラトフォードのそばを流れるエイヴォン川のほとり、向こう岸には、中学生のころに覚えたmeadowという単語を自然に思い出させるのどかな風景が広がっていました。あなたは私たちより1日おくれてお着きになったのでしたが、あなたを待つ時間はストーンヘンジを訪ねれば十分に埋められました。翌日、13世紀の建物という食堂で食事をともにしたとき、「秋にはハーヴァード大学でボルヘスのことを話すことになっているのだけれど、フランス語でかまわないという知らせがあったので嬉しい」とおっしゃったのを思い出します。その講演は、私たちが活字で読めるあなたの最後の文章になりました。あの宿でお別れするとき、「これからもお元気で」と申し上げたのでしたが、いま思えばあまりにも月並みなその言葉に、あなたのおっしゃった « Qui sait ? »というご返事がいまも耳に響いています。
あなたの訃報に接したのは、1987年12月18日、日本館館長室でのことでした。
◇初出=『ふらんす』2001年3月号