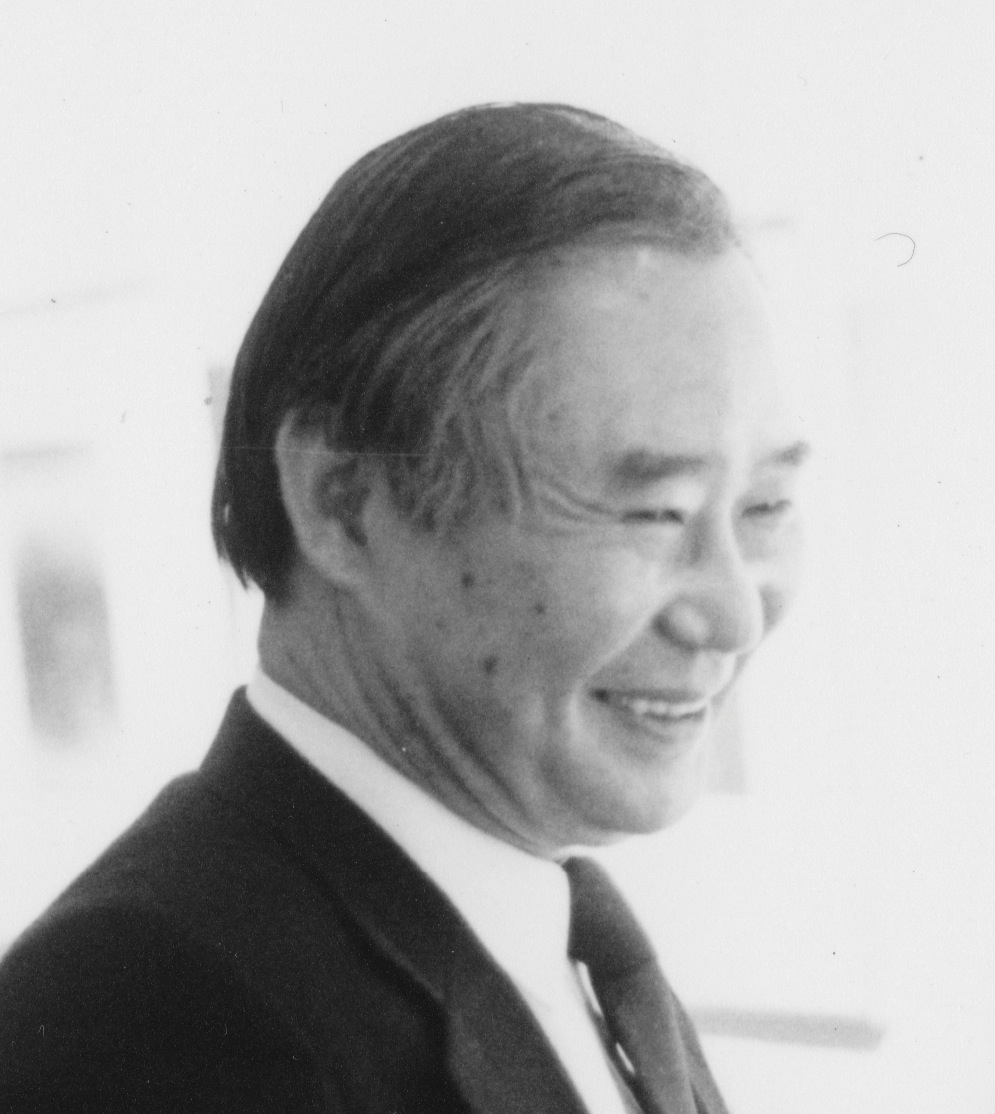第7回 パリの別れ・横浜の再会・1982年春—秋
1982年のはじめ1月から3月にかけて、あなたはジェリーをともなって長い旅に出られました。イタリア、ギリシア、エジプト、帰途ふたたびイタリア(とくにヴェネツィア)、南フランス、パリでさらに1か月ほどすごされたあと、Petite Plaisanceにお帰りになったのですが、3月末、あなたはホテルの地下広間でお別れのレセプションを開かれました。あの年のパリ滞在で3度目のレセプションでした。その会へのお招きの手紙がいまも私の手元にあります。手紙とはいっても、あのころあなたが好んで使っておられた緑色のフェルトペンで、大判の名刺の表裏に書かれた簡潔なお便りでした。中央に大文字でお名前が印刷されているだけの短い手紙に使うことも考えて作られた名刺でしたが、今見ると上下がさかさまになっています。なつかしさとおかしさが混じりあい、思わず浮かぶ笑みを抑えることができません。
あの日の話題の中心が、もっぱらこの大きな周遊の旅だったのはもちろんです。もっとも、あなたをひとり占めするわけにはいかない席でのことですから、いま記憶にのこっているのがおよそ断片的な言葉にすぎないのはやむをえません。それでもいまなお心に刻まれていることがいくつかあります。あのレセプションの前後に、モンマルトル墓地に近いコーランクール通りの静かなレストランで、あなたとジェリーと私だけの食事のひとときをもったこともありましたから、そのさいの記憶も混じり込んでいるかもしれませんが、「ヴェネツィアのあの独特なカーニヴァルをジェリーに見せてあげたかった」、「エジプトでは思いがけずアンティノエを訪ねる機会に恵まれて、ことのほか嬉しかった」、「パリへ帰る途中に通った南フランスでは、サン・ポール・ド・ヴァンスにたちよってジェームズ・ボールドウィンに会ってきた」などとおっしゃったのが忘れがたい記憶としてのこっています。
アンティノエ訪問がとりわけ感銘深い体験だったろうことは、お話をうかがったその場でも十分に想像できました。アンティノエあるいはアンティノーポリスは、ハドリアヌスの寵愛を一身に受けて旅に同行するのがつねだった、ビテュニア生まれの美青年アンティノウスが、ナイルに身を投げて謎の死を遂げた場所にほかならないからです。西暦130年の出来事でした。その死を悼んだハドリアヌスは、アンティノウスを神格化し、ローマ帝国の各地に彼の彫像を建てただけでなく、当時はベサと呼ばれていたその土地に新しい町を興し、アンティノエと名づけたのでした。
エジプトに向かったとき、あなたはアンティノエ訪問が可能だとは考えておられなかったように思います。私たちがその詳細を知ることができたのは、ブリュッセルのCIDMY(Centre International de Documentation Marguerite Yourcenar、国際マルグリット・ユルスナール資料センター)の年報第8号(1996年)に掲載されたジャン=ピエール・コルテッジャーニ氏の証言「マルグリット・ユルスナールのアンティノエ訪問」によってでした。「マルグリット・ユルスナールの旅」Voyages de Marguerite Yourcenarと題されたこの特集号は、1951年以降のあなたの旅をすべてリスト・アップし、何人かの案内者や同行者に証言をもとめたものでした。その号には私自身1982年秋のあなたとジェリーの日本滞在について思い出を寄稿しています。
コルテッジャーニ氏はあなたの愛読者でもあるエジプト学者で、当時フランス大使館文化部の活動に協力していたとのことですが、個人的に知り合ったのは、大使夫妻の主催による歓迎昼食会の席上だったとか。氏はその後、あなたをカイロ博物館に案内する機会があり、見学のあとナイル河畔のレストランで食事をともにしたさい、会話の成り行きからアンティノエ訪問の可能性があることに気づき、その場で提案したのでした。氏はつぎのように述べています――「大部分の人はルクソールからアスワンへ、あるいはその逆のコースをたどるのが普通だが、彼女はそのかわりにカイロから南に向かう長いナイル巡航を試みるつもりなのを知って、私は、もしかしたら「アンティノエ探検」ができるかもしれないとほのめかした。というのも、今はシェイク・アバダという名前で知られているアンティノエ跡は、エジプト中部、カイロから南にほぼ275キロ、ナイルの右岸に位置しているからだ。巡航日程が予定通りに守られるなら、船がミニヤに着いたとき、私が彼女とジェリーを迎えに行けばいい。その晩はホテルですごし、翌朝早く、他の人々がベニ・ハッサンの墓石群の見学にでかけているあいだ、私たちはローダに車を走らせる。そこからナイルを渡りさえすればアンティノエ。つぎの寄港地マラウィで船に追いつけるのである」「ほんとうにできるんですか?」とたずねるあなたに「できますよ」と答えると、あなたは狂喜して提案を受け入れた、とコルテッジャーニ氏は述べています。
ローダから対岸に渡る舟の上の光景は「実にすばらしく、彼女のなかの自然の恋人が外目にも明らかに満足しきっていたとはいえ、舟がアンティノエに近づいていることを忘れてはいなかった。彼女はハドリアヌスについて大いに語ったが、その話を聞いていると、まるで『ハドリヌス帝の回想』をついさきほど書き終えたばかりのようだった」――この寄り道があなたをどれほどの興奮に駆り立て、どれほどの喜びをもたらしたか、読むものにも実感できる叙述だと思います。
18世紀末、ナポレオン麾下の兵士たちがここを訪れたときは、馬や戦車の競技場、凱旋門、町の主軸をなす2本の街路の列柱などがまだ見られたとのことですが、あなたの目に映ったアンティノエは「整然とした町というより、塹壕戦の戦場跡を思わせた」とか。しかしあなたにとっては、まさに万感胸に迫る遺跡だったにちがいありません。
ローダに戻る舟が、カイロからのナイル巡航船と河の中程ですれちがったとき、あなたの見せたある印象深い行為を、案内役のエジプト学者はこんなふうに描写しています――「彼女はジェリーのほうを振り向き、預けてあったバッグをもとめて、そこから小さな財布のようなものを取り出した。厚手の布あるいはビロードの財布のようだったが、小さなわりにずっしりと重そうに見えた。ふらつく足元ながら、彼女は船の上で立ち上がった。厳粛な表情に変わり、大きく腕を動かして財布をナイルに投げ入れた。緩慢なだけに、荘重な威厳にみちた仕種だった」[…]「わざわざ遠いアメリカから携えてきたその財布に入っていたのは、彼女の説明によれば、外国滞在のあとしばしば手元にのこる小銭のコレクションだった。彼女はそれを、多くの歳月を旅にすごした皇帝の魂に捧げたのだった」
レセプションの席だったか、モンマルトルでの食事のさいだったか、この度のハイライトとしてアンティノエ訪問を語ってくださったときのあなたの表情を思い出します。文字通り輝いていたというほかありません。それほどにもアンティノエでの数刻は感動的であり、感銘深かったのだ――いまあらためてそう思います。
おふたりがパリを去られたあとも、私の滞在はつづきました。文部省在外研究員としての滞在でしたから帰国日は7月31日と決められており、1日のずれも許されませんでした。研究テーマがラルボーであることは最初から届けてありましたから、帰路の旅程にコペンハーゲンを組み込んでおりました。ヨーロッパをはなれる直前の3日間を、この街とその周辺の探訪にあてるつもりだったのです。デンマークの首都は決してラルボーと無縁ではありません。代表作の主人公バルナブースは、ヨーロッパ遍歴を切り上げて南米の故国に帰るまえ、数日をこの街ですごします。またハムレットの城が設定されたエルノシアはそこから北にわずか30キロ、普通電車でも30分とかからない距離なのですが、町外れにマリーエンリストという名前のホテルがあり、ラルボーは「日ヲ摘ミトレ」Carpe diem…と題する詩にその思い出を謳っています。
コペンハーゲンはあなたもよくご存知の町で、私がその計画についてお話しすると、中心部にはラルボーが見たままの街並みがのこっているはずですよとおっしゃって、私の探訪意欲をかきたててくださいました、そんなわけで3月末パリでお別れしたのも「それでは秋に日本で!」という心はずむ約束をかわしながらであり、日本でコペンハーゲンのことをもっと詳しく語り合えるかもしれないという望みさえありました。「愉しい別れ」だったと言えると思います。
日本に帰ってやっとすこし落ちついたころ、ノースイースト・ハーバーのあなたから英語の電報をいただいてビックリしました。ジェリーは日本のビザをパリで取得しようとしていたのですが、領事館の係員が、だれか日本人の身元保証が必要だと言っているので、彼の〈スポンサー〉になってほしい、そして大至急パリに保証書を送ってほしいという依頼の電報でした。そんな書類を、おまけに英語で書くのは生まれてはじめてでしたし、一定の書式があるのかどうかさえ知りませんでしたが、とにかく身元保証の意志だけははっきり伝わるような文面をどうにかでっちあげてパリに送りました。そんなやりとりの結果報告と、おふたりの横浜到着を予告するお手紙をいただいたのは、8月末のことでした。
「私たちの乗るロイヤル・シー・ヴァイキングRoyal Sea Viking号は、10月4日月曜日の朝8時、横浜に着きます。しかし下船・入国の手続きがいろいろとあるはずなので、あまり早起きはなさらぬように!」
私が夜行族であることをよくご存知のお心遣いがはっきりと感じられるお手紙でした。しかし私はお勧めをあまりにも真に受けすぎたようです。35年前、私自身がフランス郵船会社のカンボジア号で船出した大桟橋に、その日私が着いたのは8時15分すぎでした。船が予定より早く着いたのでしょうか、あなたはすでに埠頭に下りておられ、おそらくは出迎えの大使館員のワゴン車に積んであったのにちがいない折り畳みの椅子にかけて待っておられました。さいわいその日は快く晴れており、気温もさほど低くはなかったので、あなたは独特のマントとショールで頭と身体を包みさえすれば、風だけは避けられるようでした。半年ぶりの再会なのに、まず私は恐縮しなければなりませんでした。
◇初出=『ふらんす』2000年10月号