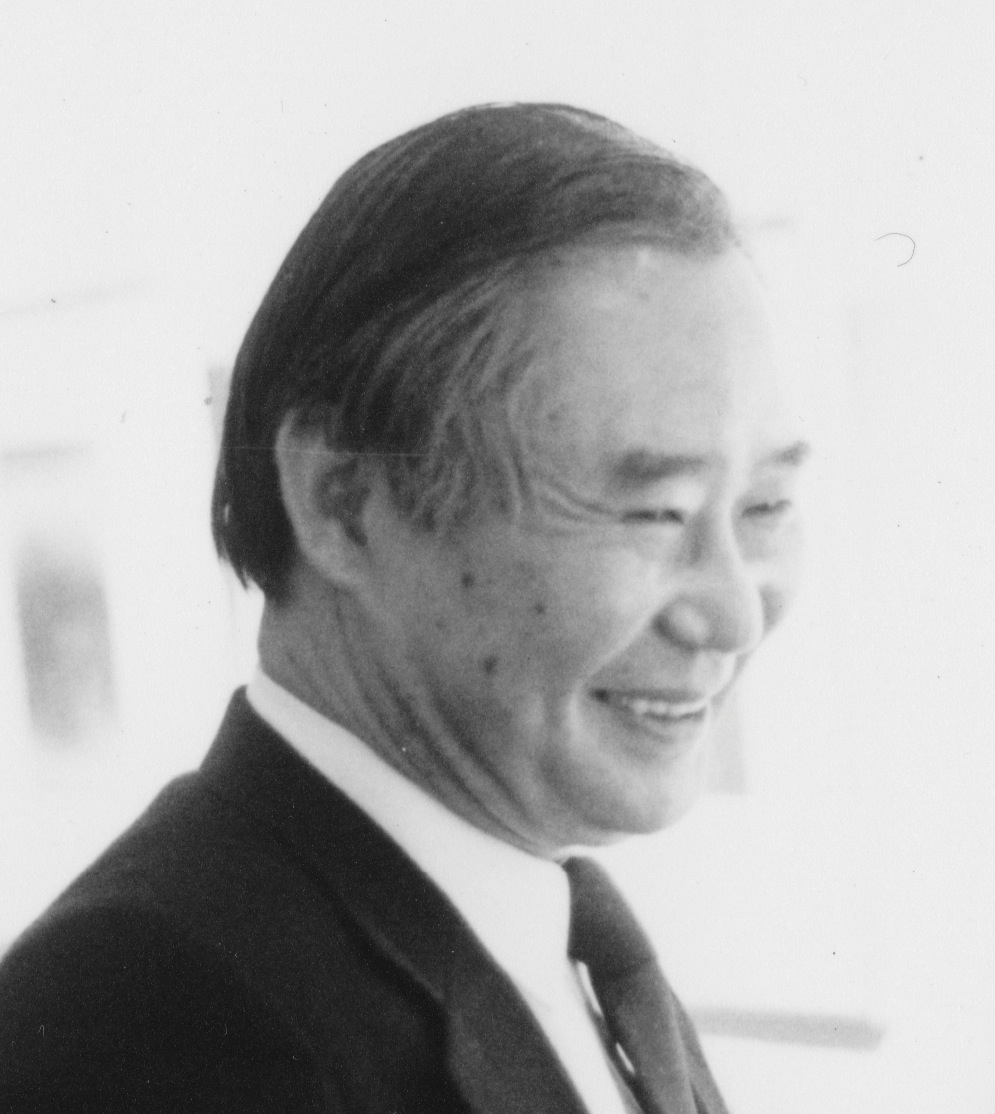第2回 〈Petite Plaisance〉を訪れる①
1981年の秋、アメリカを経由してフランスに渡り、パリを中心に10か月ほど滞在する機会に恵まれました。はじめてお会いしてから10年の歳月が流れていました。その間あなたは新作をお出しになるたびに丁寧な献辞を添えて送って下さいました。
たとえば〈世界の迷路〉三部作の第一部『敬虔な思い出』(1974、邦題『追悼のしおり』)と第二部『北の古文書』(1977)。(第三部『なにが? 永遠が』は遺著として1988年に刊行されることになります)
第一部は、あなたがこの世に生を享けたところから筆を起こし、腹膜炎を伴った産褥熱のため出産の10日後に亡くなられた母上の家系を、時の流れをさかのぼりながら遠い中世まで辿ったあと、母上フェルナンドと父上ミシェル・ド・クレイヤンクールの出会いと結婚の物語に筆をもどし、「時のスクリーンに私の顔が描かれはじめる」という言葉で結んでおられました。
第二部は逆に、太古の昔から時間の流れに沿って父方の家系を辿ったものでした。この巻もやはり、生まれて6週間目のあなたが、ベルギー国境に近い北フランスのモン=ノワールの館に父上とともに着いたところで筆が擱(お)かれています。その後数年間あなたはこの館で幼女時代をすごすことになるのですが、二巻あわせて700ページ近くにのぼるにもかかわらず、その幼女時代もふくめて、あなた自身についてはなにひとつ語られていませんでした。第二部の末尾に近く、ご自分の生涯についてこう語っておられるのに強烈な印象を受けました――「この生(というのはあなた自身の生涯にほかなりませんが)に起こったさまざまな出来事が私の興味を引くとすれば、それはなによりもまず、いくつかの経験がその生に及んだ際の通路としてである。いつかある日、暇ができ、そうしたい気持が生まれれば、それらの出来事や経験を書きとめることがあるかもしれない。しかしそうするのはいま述べた理由のためであり、そのためだけである」。遺著として刊行された『なにが? 永遠が』もふくめて、この三部作を安易に「回想録」と呼ぶわけにはいかないのはそのためです。
親から子へ語りつがれてきた家族の記憶、先祖代々の肖像画、写真アルバム、町役場や公証人役場に保管されていた古文書や証書類、祖先の遺した手紙や回想録、屋根裏部屋の木箱に残っていた文書など、2つの家系の過去を探る手がかりをすべて活用するだけではなく、家門の痕跡を残す場所にみずから足を運び、親戚や知人を訪ねて思い出を語ってもらうなどしたうえで、あなたはそれらの資料や証言を整理し、分類し、選択し、解釈して、他に類のないこの二著を書きあげたのでした。
自分はどこから来たのか? あなたを産み落としてわずか10日後に亡くなった母はどんな人だったのか? 父は? ――あなたを〈世界の迷路〉の執筆に駆りたてたのはそういうお気持だったろうと思います。しかしあなたの真の願いは、たんに両親の家系の過去を正確に知りたいというにとどまるものではなかったように思われます。そういう願いというか、あなたの真の意図を暗示するのは、第一部の冒頭に引用されている公案です。フランス語訳の形で掲げられているその公案を日本語に訳しもどせば「あなたの父と母が出会うまえ、あなたはどんな顔をしていたか」となります。「出会う前」と「生まれる前」という大きな違いがあるとはいえ、これが禅の公案のなかでももっとも有名な「父母未生以前」をふまえているのは明らかです。
「父母未生以前」という言葉は、この形のままで国語辞典にも載っているほどで、日本語のなかに完全に取り入れられているわけですが、公案集の代表的作品とされる『碧巌録』では「父母未生時如何」となっています。評唱つまり注釈のなかで、たたみかけるように浴びせられる4つの問(「問仏未出世時如何、牛頭(ごず)未見四祖時如何、斑石内混沌未分時如何、父母未生時如何。」)の最後に出てくる言葉なのですが、版本によってはいま引用した4つの問が欠けているともいわれます。その公案が私のような無知な人間の頭にもどうやら残っているというのは別様に興味深い現象ですが、それはさておくとして、自分の誕生から筆を起こし、時間をさかのぼっていく書物のモットーとしてもっともふさわしい言葉だったといわなくてはなりません。この言葉は「相対的存在にすぎない自己という立場をはなれた、絶対・普遍的真理の立場」を意味するとされていますが、あなたの目はまさにそういう立場をしっかりと見据えていたように思います。あなたが日本にいらしたときだったと思いますが――その滞在についてはいずれ詳しく振り返るつもりです――「前世も来世もあると思う」とおっしゃったことがありました。「そう思いませんか?」と問いかけられて、不意を突かれた私は返事につまったのを思い出します。一瞬後、この人の精神世界はそれほどの深さと奥行きをそなえているのだとあらためて感じたものでした。
『冠と竪琴』(1779)も圧倒的なお仕事でした。出版のことは考えずに、ひたすらご自分の楽しみだけのために訳したとおっしゃる、110人のギリシア詩人の翻訳と解釈で、1200年にわたるギリシア詩の世界が展望されていますが、選ばれたひとつひとつの作品とその作者への関心と愛着の深さが感じられる訳詩集でした。私への献辞には「ギリシアの詩人たちの観た人間の条件」という言葉が添えられていました。この言葉はあなたがつねにとりつづけた基本的な姿勢と視座を示していると思います。あなたは人間の営為と表現のすべてを「永遠の相のもとに」みる人でしたから。
いわば「おねだり」の手紙をいただいたこともありました。70年代のはじめだったと思います。「毎朝髪を梳くのに日本の黄楊(つげ)の櫛を使っているのですが、手元の最後の一本が折れてしまったので、何本か送ってもらえないだろうか」というお手紙でした。理由の明快さと依頼の率直さは、私を友人として完全に受け入れてくださったことを示しており、このうえなく嬉しいお手紙でした。しかし黄楊の櫛のことなど私にはなにもわかりませんでしたから、いろいろと詳しい人にたずねて上野界隈の専門店を教えてもらい、3本ほど買い入れて早速お送りしました。間口は狭いながらいかにも老舗という感じの店でした。
お返しということだったのでしょうか、まもなくあなたからは地元の民芸品だという室内装飾用のガラス細工が送られてきました。半透明の灰白色の、小波のような凹凸のあるガラス板を地に、雁に似た淡い褐色の鳥の飛ぶ姿をあしらったものでした。いまそれが私の宝物になっていることは言うまでもありません。
秋からのフランス行きが決定したのは81年のはじめでした。同じころの忘れがたい出来事として、あなたのアカデミー・フランセーズ入りがあります。その年すでにアカデミーの歴史は350年を越えていましたが、女性会員を迎え入れるのははじめてのことでした。それはまさに歴史的事件だったわけです。あなたの入会式が執り行われたのは1月22日のことでしたが、当然私はお祝いの手紙を書きました。その同じ手紙のなかで、秋からのフランス滞在がきまったこと、アメリカ経由で行ける可能性があること、したがってできれば10月初旬に〈Petite Plaisance〉をお訪ねしたいと思っていることもお伝えしたのでした。
〈Petite Plaisance〉(小さな楽しみ)というのは、アメリカ北東部メイン州の大西洋に面した小島にあるご自宅の名前です。いろいろな本で何度か写真を見たことがありました。19世紀中葉に建てられたものと思われる木造家屋。玄関前のテラスに通じる三段の小さな階段の上の小さな片開きの門柵がとても印象的でした。プルーストの『失われた時を求めて』の舞台のひとつであるイリエ・コンブレーの庭、プレ・カトランの奥の柵に似ていたからでしょうか。ぜひ一度訪ねてみたいと思っていたのです。
しばらくしてご返事はパリから届きました。モン・デゼール島(というのがご自宅のある島の名前ですが)の厳しい冬の寒さを避けて、入会式のあともパリ滞在をつづけておられたのだと思います。アカデミー・フランセーズに関しては、案の定なにも書かれておりませんでした。そのかわりというか、ご返事の内容は意外なものでした――「10月はじめというあなたの計画に少し戸惑いを感じています。というのも実は私自身この10月から来年1月ぐらいまで日本に行きたいと思っていたからです。私の日本滞在中あなたが不在というのはいかにも残念なので、来訪を来年の夏にしてはいただけないだろうか。もっとも、この秋ヨーロッパに用ができる可能性もないではない。いずれにせよ、まだ決めかねることがいろいろあるので、しばらく待ってもほしい」。すれちがいになるのは私としてもいかにも残念なので、私のほうの出発を1か月くらい延ばしもかまわないと申し上げたのでしたが、夏のはじめになって「お心遣いはありがたいが、結局この秋もヨーロッパに渡ることになったので、10月初旬のお出でをお待ちする。そのころにはこの島の木々も美しく色づいて、あなたを歓迎するでしょう」というお便りをいただいたのでした。
そんな経緯があったうえでの訪問でしたが、問題はモン・デゼール島にもっとも近い町バンゴアから100キロの道をどうやって行くかということでした。あなたはお手紙のなかで「レンタカーあるいはタクシー」と軽くおっしゃっていましたが、運転歴は20年をこえているとはいえ、はじめてのアメリカでレンタカーを走らせる自信はなく、といって100キロの道をタクシーでとなると正直なところ懐が心配でした。しかしニューヨークに着いた翌日、あらかじめ教えていただいた番号に電話したとき(その番号は一般の番号簿には載っていないということでした)その心配も解消しました。あなたがお手紙のなかで「旅の伴侶」と呼んでおられたジェリー・ウィルソン氏がバンゴア空港まで迎えにきて下さるというのでした。ニューヨーク・バンゴア線は、東京からは予約を入れることもできないローカル線で、古ぼけた双発のプロペラ機で飛び立ち、ポートランドという町の空港で乗り換えてやっと辿り着くという感じでした。それでも予定より15分早く着いたバンゴア空港で手荷物を待っているところにジェリーがあらわれました(呼び捨てにするのは、その後彼とも親しくなれたからです)。閑散としたロビーに人待ち顔で立っている東洋人は私だけでしたから、お互いを見分けるのはたやすいことでした。(つづく)
◇初出=『ふらんす』2000年5月号