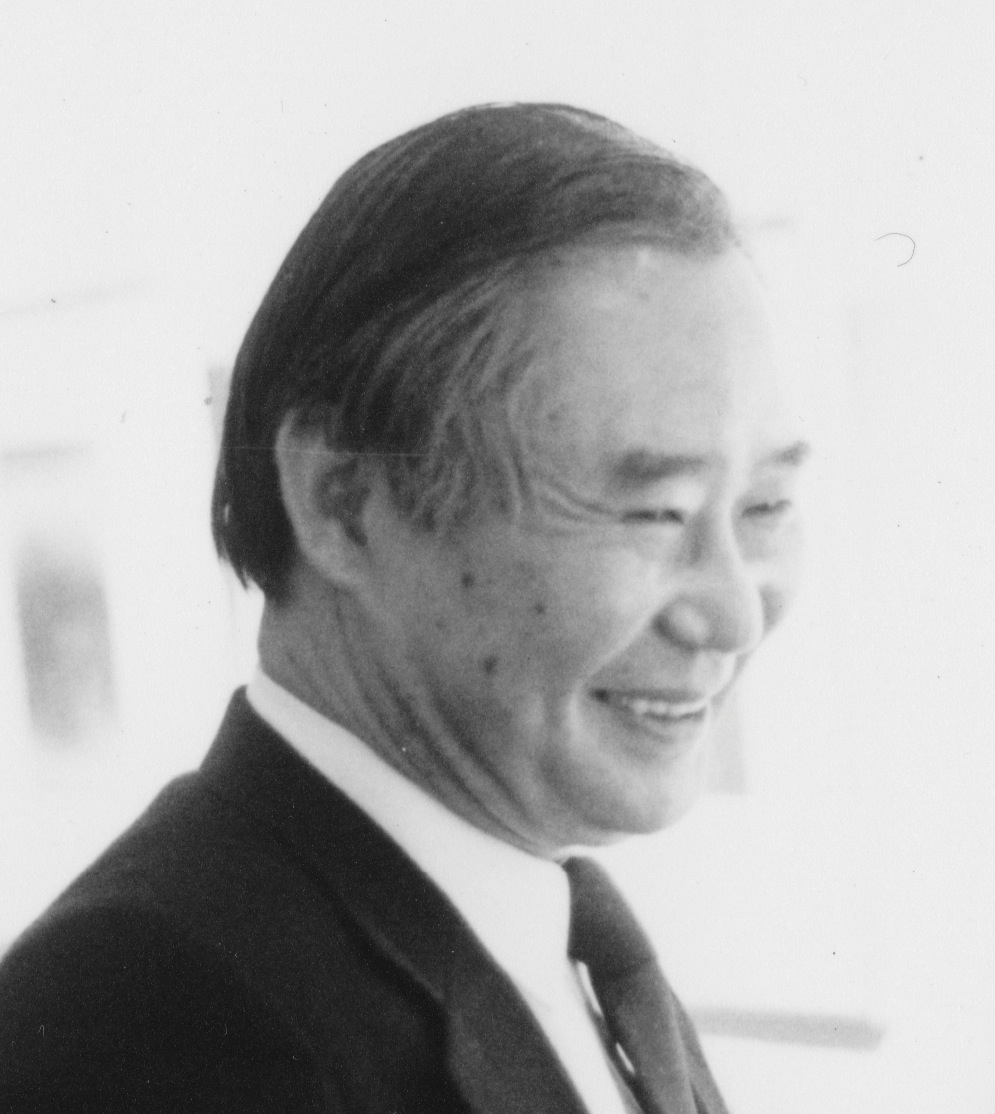第4回 〈Petite Plaisance〉を訪れる③
午後のおわり、ジェリーが車で島の中を案内してくれました。もちろんあなたもご一緒でした。いまモン・デゼール島の比較的詳しい地図にあたってみても、どの辺を回ってくれたのかよくわかりませんが、山のほうではなく、もっぱら海沿いの道だったのは確かです。Northeast Harborつまり北東港というのがあなたの町の名であることは前にも述べました。途中で小さな港のそばを通りましたから、きっとそれが町の名の由来する港だったのだろうと思います。
地図を見ると、やや横長の楕円形の島をほぼまんなかで東西に二分するように、南から北へ向けて、突き刺された剣のような細い入江が深々と入り込んでいます。あなたの町はその名の通り、入江の東岸、中央よりほんのわずか北寄りにあります。そして対岸にはSouthwest Harborという対照的な名前のもうひとつの港と集落。名前を見ただけでは、それぞれ島の北東と南西の端に位置し、外洋へ向けて築かれた港を想像してしまいますが、実は島のほぼ中央でフィヨルドをはさんで向かい合う二つの港なのでした。モン・デゼール島はロブスターの特産地としても名高いのだそうで、ジェリーが車を走らせた道沿いでも、どころどころ真っ赤なロブスターの看板をかかげたレストランが目につきました。北東港も南西港も、豊富な水揚げを誇る漁港なのにちがいありません。
10月初旬といはいえ、夜は冷え込みました。細い枯枝を焚き付けに使い、庭の奥に広がる木立のなかから拾い集めた太めの枝を燃やす暖炉のそばで夕食後の会話が続きました。森を保護する意味で、薪を買うのはできるだけ控えているとあなたはおっしゃっていましたが、この言葉はエコロジストという側面をよくあらわしていたと思います。
私の今度のフランス滞在の目的がラルボー研究であることをご存じのあなたは、会話の中でよく彼を引き合いに出しました。「ラルボーじゃないけれど、私の書棚もいくつかの〈領域〉にわかれているんですよ。この辺がインド、次が中国、日本は下の段……」というふうに。もちろんそれは、ラルボーの評論集に『英語の領域』Domaine Anglaisと『フランス語の領域』Domaine Françaisと題されたものがあることをふまえており、俳諧の「挨拶付け」を思わせる言葉の選択でした。前者はイギリスとアメリカのほか、ジョイスを中心にアイルランドの文学を論じたもの、後者はフランス文学を対象にしていますが、とりあげられた作家や詩人は、誰もが知っている大作家、大詩人ではなく、モーリス・セーヴやジャン・ド・ランジャンドなど、忘却から引き出すのにラルボーが大きく貢献した人々に関する論考を数多くふくんでいました。インドや中国の領域は仏教に関する書物で占められているようでしたが、それらの表題を見ながら、あなたが『三島論』のなかで、『曉の寺』に述べられた阿頼耶識(あらやしき)をめぐる論述が物足りないと批判しておられるのを思い出しました。仏教に関しては全くの門外漢なので、あなたの批判が当たっているのかどうか、私にはなんとも言えませんが、「私はいくつかの宗教に属している」とおっしゃるあなたが、ひとつの固定した信仰形態とは無縁でありながら深い宗教感覚の持主であり、該博な知識をふまえて、多様な信仰の根源に目を凝らしておられたのは確かです。
寝しなに枕もとに置かれていた『姉アンナ…』を読みました。黒表紙、縦長の瀟洒な小型本で刊行されたばかり、インクの匂いを漂わせていました。冒頭の一行が、ついさきほど話題にしたラルボーのことをあらためて思い出させました。「1575年、彼女はナポリにあるサン・テルモ砦の分厚い城壁のかげで生まれた。父が城塞司令官を務めていた」という書き出しなのですが、10年ほど前、はじめてナポリを訪れたとき、私はその城塞のそばを通ったことがあったからです。ナポリの北、町全体を見下ろすヴォーメロの丘の頂上近く、「拳のように置かれた」サン・テルモ砦は、淡褐色の分厚い城壁に囲まれて、いまもナポリ全市に睨みを利かせているような感じです。今でも兵営として使われているので、内部を参観することはできませんが、私がこの丘まで足を運んだのは、いわばラルボー巡礼でした。1920年代の中篇小説、ジョイスの影響を色濃く感じさせ、「内的独白」の創始者とされるエドワール・デュジャルダンに捧げられた『秘められた心の声…』は、この丘を舞台としてはじまっているのです。おまけに私が部屋をとったのは「アルベルゴ・サン・テルモ」という名前のホテルでした。その日の私のお目当ては砦のすぐ隣りにあるサン・マルティーノ僧院だったのですが、『姉アンナ…』の終わり近く、この僧院もまた小説の舞台として登場します。私は『姉アンナ…』の主要な舞台をあらかじめ訪ねていたのです。しかもラルボーの手引きによって……。
一夜明けて、まさにIndian Summerと呼ぶにふさわしい快晴の朝、館の裏の庭先でコーヒーを楽しみながら、あなたは『姉アンナ…』と『無名の男』についていろいろと話してくださいました。現にその時執筆中だという『美しい朝』についても。その場の会話の記憶はきれぎれに残っているだけです。しかし、あなたはこれらの3篇を翌年『流れる水のように』という美しい表題の単行本にまとめて刊行されるのですが、そのさいにあらためて執筆なさった「自作解説」の内容が、あの朝私に話してくださったこととほぼ重なりあっていたのは確かなので、今はそれを頼りに思い出を綴ろうと思います。
『姉アンナ…』と『無名の男』の出発点は、1935年に刊行された短篇集『死神が馬車を導く』にあります。この本にふくまれる3篇の作品は、それぞれ「エル・グレコ風に」、「デュラー風に」、「レンブラント風に」と題されておりました。あなたが遺された作品群は「書き直されたもの」、「書き直されなかったもの」、「初版のまま絶版となったもの」の3系列にわかれますが、たとえばこの中の「デュラー風に」と題された50ページほどの短篇が「書き直されたもの」の典型であり、30数年の歳月をへて300ページをこえる大作『黒の過程』に変貌します。『姉アンナ…』もまた「エル・グレコ風に」を書き直したものでした。もっとも書き直しの度合いは作品によってまちまちで、この作品については「書き直し」というより「手直し」というべきかもしれません。事実あなたはこう述べていました――「『姉アンナ…』は1935年に刊行されたテキストをほとんどそのまま再録したものであるが、そのテキスト自体、1925年、22歳の若い女性が書いた物語とほぼ同じだった。とはいえこのたび再刊にあたって、かなりの箇所で表現に手を加えたし、深く内容にかかわる変更をほどこしたくだりも12か所ほどある。[…]とはいえ執筆を思い立ったのがつい今朝であるかのように、いまでも私はこの物語にすんなり入り込めるような気がする」
それにたいして、最初「レンブラント風に」という題で書かれた『無名の男』のほうは徹底的に書き直された作品でした。同じく「自作解説」のなかであなたはこう述べておられます――「20歳ごろに書かれた以上、私の最初の作品のひとつであり、その後ほとんど手を加えられることもなく、的確さを欠くこのテキストは、まったく使い途のないものとわかった。初稿の文書はただの一行も残っていない。とはいえ、それ自体のなかに、あまたの季節を経たあげく、最後に芽を吹くことになる種子が含まれていた」
あの朝あなたが話してくださったことのなかで、とりわけ強く印象に残ったことがふたつありました。ひとつは『無名の男』の主人公ナタナエルという人物を思いついたのが、『黒の過程』のゼノンの着想をえたのとほぼ同時であったということ。もうひとつは、あなたが晩年好んで訪れたオランダで、フリースラントの島のひとつに渡り、ナタナエルがもっとも楽な姿勢で息を引きとれる場所を探しながら、あなた自身イワナシの木立のなかに横になってみたというお話でした。
第一の点、ナタナエルとゼノンの対照は私にとってとりわけ興味深いのですが、この二人についてあなたはこう述べていました――「ナタナエルという人物を最初に思いついたのは、ゼノンの着想を得たのとほぼ同じころである。その早熟さにはわれながらおどろかずにいられないのだが、非常に早いころから私はこの二人の人物を夢み、古い時代のオランダを背景に横顔を浮き立たせる二人を漠然と想像していた。ひとりは知恵の追求に激しく挑み、人生が与えてくれるものとはいわないまでも、すくなくとも人生が教えてくれるものすべてを貪欲に追い求め、同時代のあらゆる教養と哲学を身につけていながら、自分自身のものを創出するためにそれを投げ捨てる男だった。もうひとりは、忍耐強いと同時に受動的までに無頓着で、ある意味では「流れのままに生きる男」であり、ほとんど無教養ではあるが澄みきった魂の持主で、いわば本能的に、まがいものや無益なものとは無縁に生きる正しい精神に恵まれ、それまで生きてきたのと同じように、嘆きもせず驚くこともなく、若くして死ぬ男であった」。この作品をジェリー・ウィルソンに捧げたという事実は、その後彼を襲った運命を思うと、あなたの並外れた透視力を証しているように思えます。
ナタナエルの死に場所を探して、イワナシの木立のなかに横になってみたというお話も、およそどんな細部もゆるがせにしないあなたの創作態度を端的に語っていると思います。このお話をうかがって思い出したのは、あなたがベルギーの王立アカデミー会員に選ばれた際の歓迎演説で、カルロ・ブロンヌが披露した挿話でした。『ハドリアヌス帝の回想』のなかに、ある女性が古代ローマのセステルティウス貨幣を積み重ねて山を作り、金額を数える場面が描かれているけれども、当時の貨幣は碁石のようにふくらんだ形をしていたから積み重ねることなどできなかったはずだという批判を加えた人がいた。それにたいしてあなたは「いくつまで積み重ねられるか、実際に試してみた」と答えたという挿話です。相手もこれには脱帽せざるをえなかったというのですが、フランドル派の絵画を思わせるあなたの精密な描写や叙述が、確固とした裏付けをもっていたことを証してあまりある挿話だと思います。
昼過ぎには次の目的地ボストンへの飛行機に乗るために、ふたたびバンゴア空港へ走らなければなりませんでした。「今度はもっとゆっくりできるようにいらっしゃい」とあなたはおっしゃってくださいましたが、2週間後にはパリでまたお会いできるはずでした。Petite Plaisance訪問と、その後パリでともにすごした数か月の日々の思い出は、私のなかでいわば連続しています。
◇初出=『ふらんす』2000年7月号