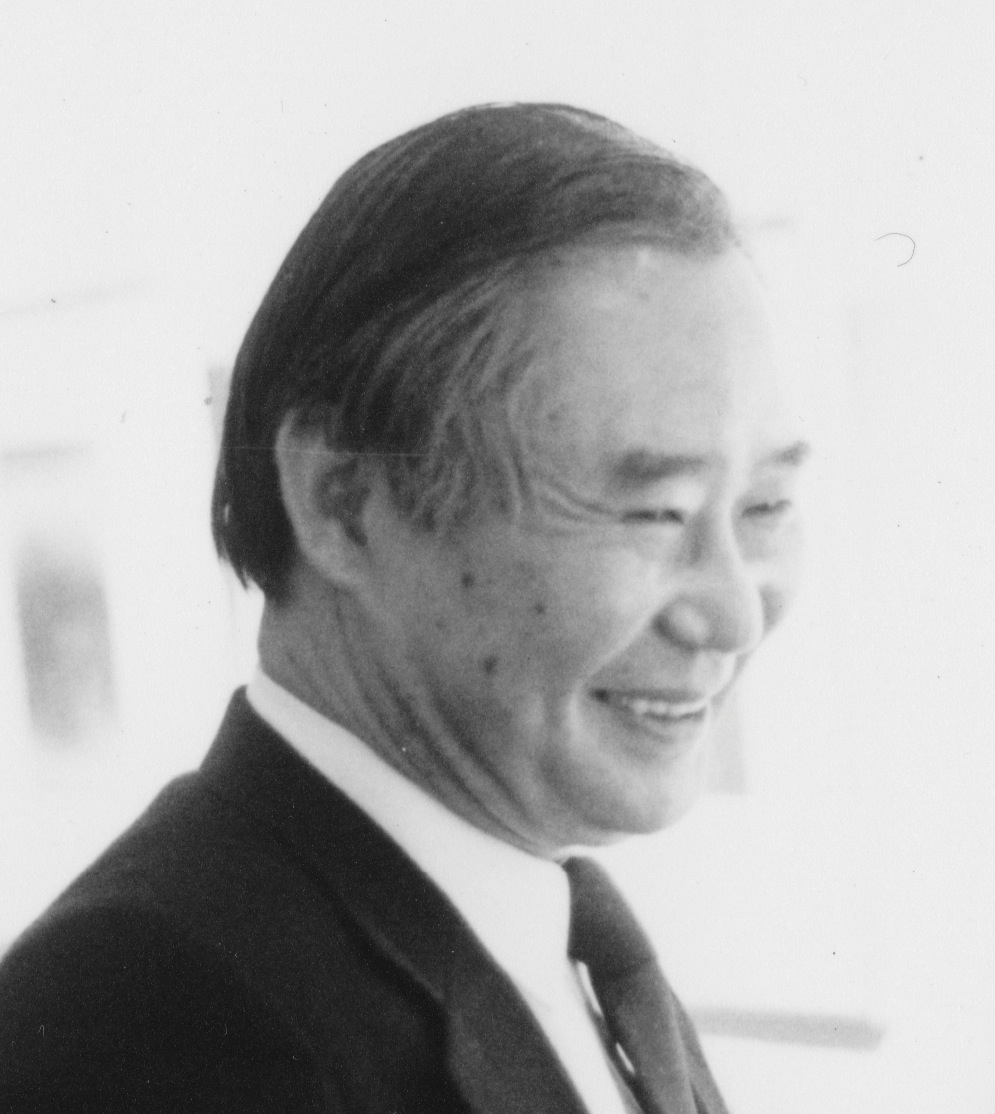第10回 三島邸訪問
「おくのほそ道」への旅から東京へ戻ったのが10月20日。あなたとジェリーは高輪のホテルにお入りになりました。喉の具合のため、2、3日お部屋で静かにしていらしたように記憶しますが、前述のように10月26日には東京日仏学院で講演という予定が組まれておりました。22日ごろだったでしょうか、お見舞いをかねて、その後の予定(とくに京都行き)の打ち合わせのためにお訪ねしました。美しい庭の眺めを楽しめるラウンジでお茶をいただいたとき、講演の組み立てについてやっとある着想がえられたと嬉しそうにおっしゃったのを思い出します。通訳することになっていた私としては、すこしでも早くテキストをいただきたい気持ちでしたが、アイデアがひらめいたのが本番の3日前とあっては、訳すのもぶっつけ本番を覚悟しておいたほうがよさそうでした。事実「空間の旅・時間の旅」と題された講演のテキストをいただいたのは前日の夜でしたから、あらかじめ全文を訳しておく余裕はありませんでした。前にも書きましたが「おくのほそ道」の冒頭の一節が最初に引用されておりました。私が準備できたことといえば、あなたが英訳をもとにフランス語で綴られたあの有名な文章を、ひとまず現代日本語に訳すこと、そして芭蕉の原文にもう一度あたっておくことぐらいでした。「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。舟の上に生涯をうかべ馬の口をとらえて老をむかふる物は、日々旅にして、旅を栖とす」というあの書き出しが「日と夜は永遠の旅人である……舟を操るものたち、あるいは老いに倒れるまで毎日野良に馬を引くものたちも、たえず旅をしている」という調子の文章になっていました。重訳されたフランス語をさらに日本語に訳し戻したわけなので、これほどの食い違いが生じるのは、けだしやむをえぬことでした。
引きつづいてあなたは、つい先日の松島、平泉、鳴子への旅にふれたあと、マルコ・ポーロ、コロンブス、ザビエル、オデュッセウスなど、具体的な例をあげながら、人はなぜ旅をするのか、そのさまざまな理由をめぐる省察を述べられました。金儲け、冒険、探検、伝道、帰郷など……次いであなたはご自分の作品の主人公とした3人の人物を取り上げ、それぞれの旅の特徴を述べていました。ハドリアヌス、ゼノン、ナタナエルの3人です。
皇帝としてローマ帝国の版図をくまなく駆けめぐったハドリアヌスは、およそあらゆる時代の旅人なるもののもっとも本質的な特徴を体現していたこと、彼にとって旅は趣味であり情熱であると同時に、ほとんど苦行ともいうべき忍耐の学校であり、異邦人の偏見と突き合わせることによって自分自身の偏見を消し去るための手段であったこと。『黒の過程』の主人公ゼノンの場合は、錬金術、占星術をも修めた医師として、旅はなによりもまず糊口の資を得るための手段であった。しかしまた、宗教的、道徳的、政治的理由による迫害をのがれるための逃避行であると同時に、あくなき探究心を満たすための知の探究の旅でもあったこと。さらに『無名の男』ナタナエルの場合は、まさしく「流れる水のように」彼を押し流す運命の力のままに、いわば意に反して余儀なくされた旅であったこと。それでも彼は、ハドリアヌスやゼノンと同じく、自分の国、自分の時代の大勢を占める思想や意見を無批判に受け入れてはならぬこと、人間の身に起こるあらゆる出来事には、共通の基盤があることを、旅を通じて学びとったことを……。
全文を翻訳しておく余裕はありませんでしたが、あなたのお話の内容にあらかじめ目を通すことができたのは幸いでした。
そのテキストをいただいたのは、大田区南馬込の三島邸でのことでした。25日の夜、瑤子夫人がご自宅で、あなたを主賓とする晩餐会を催してくださったのです。会食者はわずか5人。あなたとジェリー、三島夫人、私、そしてジュン・シラギという人。シラギ氏は私にとって初対面の人でしたが、とてもアンティームな雰囲気の晩餐でした。
10月25日という日付がどんな経緯で決まったのか、私には記憶がないのですが、東北への旅から帰った直後、あなたが三島夫人に連絡してお決めになったのかもしれません。あるいはもっと前から約束ができていたのかもしれません。いま私の手元にある招待状は、あらかじめ英語で印刷され、招待客の名前や日時など、必要事項を書き込むだけの形のものですが、R.S.V.P.(Réponse, s’il vous plaît――ご返事ください)という4文字が1本の線で消されていますから、日時についてはあらかじめお互いに了解していたのにちがいありません。消印は10月21日の午後、つまり東京へ帰った翌日のものでした。
私にとって三島邸を訪れるのは三度目でした。最初は1969年4月、当時九州大学で教鞭をとっていた詩人ジャン・ペロルによるインタビューの通訳として。招じ入れられたのは最上階の小さな円形の部屋。新築当時評判になったアポロン像のある前庭を見下ろす眺めのよい部屋でした。親しいもの同士が少人数で心おきなく語りあうのにふさわしい部屋。前庭のみならず、おそらくは南の方向に広がる住宅地の屋根の連なりを見はるかすこともできましたから、三島氏はあの部屋でちょっとした征服感をおぼえたこともあったかもしれません。
二度目は前にも述べたように、ルノー=バロー劇団による『サド侯爵夫人』の日本公演が行われたときでした。1979年のことです。三島由紀夫が澁澤龍彦の『サド公爵の生涯』に触発されて書いたこの戯曲を三浦信孝氏による逐語訳にもとづいてみごとなフランス語に訳したのはアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグでした。草月会館での公演を打ち上げたときだったと思いますが、三島夫人が訳者夫妻をはじめ劇団関係者全員を招いてレセプションを開いたのでした。初演のさいの日本人出演者も招かれていたようでした。あの戯曲は作者の生前、ドナルド・キーンによって英訳されていましたが、その後マンディアルグというこの上ない訳者をえて、いわば原語ともいうべきフランス語に訳されただけではなく、当時もっとも意欲的な活動を展開していた劇団によって日本でも上演されることを知ったら、三島氏はどんなに喜んだことでしょう。私自身あの公演には興奮をおぼえたのを思い出します。
10月25日の晩餐会で、強烈に記憶に刻まれていることが2つあります。
ひとつは三島由紀夫の書斎を見せていただいたこと、もうひとつは食事の最中にジュン・シラギ氏があなたに『近代能楽集』を仏訳してくださいませんかと言い、ほとんど唐突なその提案ないし依頼に、あなたが即座に肯定的反応を見せたことです。
1970年11月25日の早朝、三島由紀夫が『豊饒の海』の最後の原稿を入れた封筒を携えて敷居を越えたときから、そのままの状態に保たれているとのことですが、『牢獄巡回』に修められた「大作家の家」という文章のなかで、あなたはあの書斎について次のように述べておられます――「この住まい全体がキッチュだというもっぱらの評判にもかかわらず、さすがに書斎だけはその感じをまぬがれていた。この部屋もやはり手狭で、壁面は日本語と英語の本で埋めつくされている(ギリシアへの短い旅のあと、熱狂に駆られて習い覚えたほんのわずかのギリシア語をのぞけば、三島は日本語と英語以外の言語を知らなかった)。手をのばせば届くところに、私は『ハドリアヌス帝の回想』のグレース・フリックによる英訳本を見つける。フランスのジャーナリストによる彼への最後のインタビューのひとつで、三島はこの書物を賞賛したのだった。面と向かって交わす言葉は意を尽くしきれないのがつねだが、遠く離れて耳にしたように感じられる彼の言葉に、私は直接聞いた言葉に劣らぬ交感が成り立っていたような印象を抱いている」
いまふと思うのですが、三島由紀夫が『ハドリアヌス帝の回想』への高い評価を語った相手は、もしかしたら最初の訪問のさい私が通訳したジャン・ペロルなのかもしれません。もしそうだとすれば、当時の私はあなたのことをほとんど知らなかったとはいえ、この上なく大切な記憶が欠落しているわけで、忸怩たる思いを抑えることができません。あの年ジャン・ペロルは何人かの日本現代作家へのインタビューを連続的に行なっており、安部公房のときも私が同道したのでしたが、その後これらの対話は、当時まだ刊行されていた週刊文芸紙Les Lettres françaisesに連載されましたから、ぜひ探し出して確かめたいと思います。
書斎といえば、あまりにも生々しい記憶なので語ること自体無神経な行為といわれるかもしれませんが、私にとってはこの上なく深く刻まれた記憶であり、ひとりの人間が生きた証しとして否みようのない形だと思うので、あえて書いておこうと思います。あの書斎で私が衝撃を受けたのは、入ってすぐ右側の窓際の、傘立てに似た容器に突込まれていた数本の竹刀でした。柄(つか)の部分の白いズック布が、汗と手垢で薄黒く汚れていたのです。汚れていたと言ってはいけないのかもしれません。剣道に打ち込んで五段の段位まで得た彼の汗がしみ込んでいたのです。胸を突かれました。
『近代能楽集』の仏訳はCinq Nô modernesという題で1984年に刊行されました。「ジュン・シラギの協力のもと、マルグリット・ユルスナールの翻訳による」と表紙に明記してあります。原作にふくまれる8篇のうち「卒塔婆小町」「弱法師」「綾の鼓」「葵上」「班女」の5篇が選ばれていました。
Cinq Nô modernesには、13ページに及ぶあなたの序文が添えられています。この文章はプレイヤード文庫の『エッセーと回想』にも収録されていませんので、この版本によってしか読むことができないのですが、『牢獄巡回』のなかの「歌舞伎・文楽・能」にもまして重要なテキストだと思います。あなたの東京滞在中、水道橋や松濤町の能楽堂にお供した記憶は、私自身にとって十分に貴重なものですが、数度にわたる観能の体験をふまえてあなたは、観阿弥、世阿弥、元雅による原作を三島がいかに巧みに換骨奪胎したか、余すところなくみごとに解き明かしておられるからです。いまはその細部に言及する余裕がありませんが、卒塔婆とベンチ、鉢植えと庭の花の対応の指摘や、ものみなを浸す仏の慈悲の徹底的排除を三島の「近代能楽」の特徴としてあげている点など、あなたと三島のあいだには、たんに理解という言葉では律しきれない深い共感があったのだと思わずにはいられません。
◇初出=『ふらんす』2001年1月号