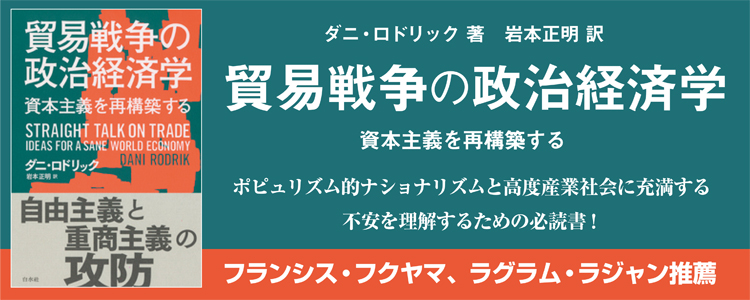「エディンバラで見た2つの「民意」の乖離とその行方」白川俊介
“Two landslides, One collision course”
英国では2019年12月12日に総選挙が行われた。その結果は、ボリス・ジョンソン首相率いる保守党の「圧勝」であった。前回選挙と比べると、保守党が66議席を増やし、365議席を獲得した一方で、ジェレミー・コービン党首率いる労働党は、42議席減らして203議席に留まった。保守党は単独過半数を獲得し、選挙後、首相が力強く宣言したように、英国は2020年1月末をもってEUから離脱することがほぼ確実な情勢となった。
無論、1月末をもって離脱するとはいえ、EUとのあいだでは諸々の交渉事があるのであって、英国が完全にEUから離脱するのには、あと数年程度はかかるであろう。ただし、少なくとも「ブレグジット」をめぐる英国政治の混乱には、いちおうの終止符が打たれたといってよいだろう。
しかしながら、これで英国政治が安定を取り戻すのかといえばそうではないように思われる。というのも、この選挙の結果を受けて、スコットランドの独立運動にさらなる拍車がかかりそうだからである。
ここでスコットランド独立運動の歴史を振り返る余裕はないが、「ブレグジット」をめぐる近年の英国政治の動きがスコットランド独立の機運を高めたのは間違いなかろう。ご存知のように、2014年に独立を問う住民投票が行われ、その際には独立は否決された。だが、2016年の「ブレグジット」をめぐる国民投票においては、英国全体としてはEUからの離脱が過半数という結果であったが、スコットランドにかぎってみれば、実に6割以上がEU残留を支持しており、イングランドとスコットランドの「民意」の違いが際立つ格好となったのである。
さらには、2019年5月に行われた、欧州議会議員選挙でも、スコットランドにおいてはEU残留派が圧勝する結果となった。これを受けて、スコットランド自治政府第一首相であり、スコットランド国民党(SNP)の党首であるニコラ・スタージョン氏は、自身のツイッターで、「歴史的な勝利だ。スコットランドは再度ブレグジットを拒絶したのだ」と述べたのである。
そのうえでの今回の総選挙である。選挙は、「英国全体としてみれば」保守党の大勝といってよいであろう。しかし、ことスコットランドにおいては、59議席のうちの8割以上となる48議席をSNPが獲得する結果となった。他方、保守党は前回より7議席も減らしている。まさにSNPの圧勝であった。
12月14日付のTHE SCOTSMAN紙の一面の見出しには、“Two landslides, One collision course”とあった。あえて訳せば、「2つの大勝利が衝突を引き起こす」ということだが、それは言うまでもなく、英国政府(保守党)とスコットランド自治政府(SNP)とのあいだの衝突のことである。今回の選挙の結果を受けて、英国全体では保守党が大勝し、過半数の国民が「ブレグジット」を望んでいるのに対して、スコットランドでは保守党は大敗を喫し、スコットランドの多くの人々がEU残留を望んでいる、ということが疑いようもなくはっきりとした。「ブレグジット」についての方向性がほぼ定まった今、この「2つの民意」をどう処遇するのか、というのが今後の英国政治における間違いなく大きな争点の1つになるであろう。
そこで以下では、こうした英国全体として示された「民意」とスコットランドにおいて示された「民意」に乖離があるという点に絡めて、2つほど若干の考察をしてみたい。
「デモクラシー」か「自決」か?
まず、単純ではあるけれども非常に深い問題として、一つの国家のなかで示された「2つの民意」のどちらを尊重すべきなのか、という問題がある。今回の総選挙の結果は、繰り返しになるが、英国全体としては保守党、すなわちブレグジット推進派かつ連合王国維持派(ユニオニスト)が大勝したわけであり、それが英国の「民意」だといえなくもない。民主的な社会というのは、「人民の意志」(people’s will)に基づいて、「人民」がみずからの運命を自分自身でコントロールし、決定できる社会である。その観点からすれば、スコットランドにおいて局所的に示された「民意」が、全体として示された「民意」に優先されることはありえないし、そうあってはならない、ということになる。
とはいえ、「人民の意志」が実のところ、押しなべて「多数派の人民の意志」である点に鑑みれば、「デモクラシー」のもとでは、「少数派」は常に不遇をかこうことになるおそれがある。それゆえ、「自由民主主義」的な社会においては通常、「基本的人権」などに基づいて「少数派」を保護し、「少数派」が「多数派」に対して常に不利な状況に置かれることがないような制度枠組みが整えられている。
ただし、ここで人権との関連で着目すべきは、いわゆる「国際人権規約」(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、および市民的及び政治的権利に関する国際規約)が、その第一条において、人民の「自決権」を擁護している点である。なぜなら、「自決権」が基本的人権の1つであるとすれば、スコットランドの「人民」の「自決」は尊重されるべきだからである。
こうして英国全体としての「デモクラシー」と、スコットランドの「自決」という対立構造が浮かびあがるのだが、「デモクラシー」と「自決」が根本的に対立するものだというわけではない。先にも述べたように、「デモクラシー」とは「人民」がみずからの運命を自分自身でコントロールし、決定できるための政治システムだからである。しかしながら、「デモクラシー」と「自決」は同義だというのでもない。とりわけ、デモクラシーを担う主体、すなわち「人民」とは誰かという点に合意のない社会においては、「デモクラシー」と「自決」は相いれない場合があるのである。英国の政治哲学者デイヴィッド・ミラーが近著で指摘しているように、「デモクラシーは、政治的単位の境界線が定まっている、すなわち「自己決定」を行う「自己」というのが定まっている場合には、うまく機能する」(David Miller, Is Self-Determination a Dangerous Illusion? Cambridge: Polity, 2019, p. 18)のである。逆にいえば、そのような「自己」が定まっていない場合には、「デモクラシー」は常に、別の「人民」による「自決」(=「デモクラシー」)の要求という挑戦を受け、不安定なものになるおそれがあるのである。
大変興味深いことに、スコットランドの独立支持派の集会に行くと、必ずといってよいほど、スコットランドの旗とともに、スコットランドと同じく独立の機運が高まりを見せているスペインのカタロニアの旗が掲げられている。そのカタロニアの独立支持派の旗には、“Democracy is not a crime”(「デモクラシーは罪ではない」)と書かれている。全くそのとおりであると思う。しかしながら、結局のところこの問題は、「デモクラシー」や「自決」を担う集合的主体とは誰であり、当該集団にはその資格があるのかという問題についての何らかの規範理論を持ちださなければ、調停できないように思われるのである。
「世界経済の政治的トリレンマ」──グローバル化と「自決」
スコットランドの「自決」が尊重され、スコットランドが英国から分離独立することになるのか、私にはよくわからない。スタージョンは2020年の後半には独立をめぐる2度目の住民投票(Indyref2)を行いたい意向を示しているが、「ウェストミンスター」がそれを簡単に認めるはずもなく、両者の妥協点を見いだすのは現状では極めて難しいと言わざるをえない。しかしながら、仮にSNPが掲げるように、スコットランドが英国から分離独立し、1つの主権国家としてEUに加盟することができたとしても、私はそのことによって、スコットランドが別の問題に直面することになるのではないかと危惧している。
スコットランドは何のために独立したいのかといえば、それはつまるところ、「自決」の要求が根本にあるように思われる。つまり、英国政府とのあいだの政治的コントロールの問題に鑑みて、スコットランドのことはスコットランドが決めるということなのである。これまで実際に「ウェストミンスター」から「ホリルード」(スコットランド議会)へと様々な権限が移譲されてきているわけだが、スコットランドが英国から分離独立するということは、これまでの限定的な自治から完全な自決権、すなわち主権を獲得するということであり、そうすることで、英国政府とスコットランド政府とのあいだの政治的コントロールの問題は解決されるのである。しかしながら、スコットランドはEUへと加盟することで、同様の政治的コントロールの問題を、今度はEUとのあいだで抱えることになりはしないだろうか。
ここで思い起こされるのは、米国の経済学者ダニ・ロドリックが提示した「世界経済の政治的トリレンマ」という議論である。その詳細については、ロドリックの著書『グローバリゼーション・パラドックス』や『貿易戦争の政治経済学』(いずれも白水社より刊行)を参照願いたいが、大まかに説明すれば、世界政治において、A:経済のグローバル化、B:デモクラシー、C:国民主権(ネイションの自決)の3つを同時に達成することは不可能であり、これら3つのうちいずれか1つを諦めなければならない、というものである。このような観点から「ブレグジット」を見てみれば、それは、端的にいえば、ヨーロッパレベルにおいて、経済統合とともに政治統合が次第に推し進められていくにつれて、国内の民主政治が縮減され、国民主権が切り崩されていくことに対する反発の表れであると捉えることができよう。
スコットランドが英国から独立し、EUに加盟した場合、スコットランドもこの「トリレンマ」から逃れることは難しいのではないか。たとえば通貨の問題1つ取ってみても、スコットランドが現行の通貨制度のまま、つまりポンドを使用したままでEUに加盟できるとはあまり思えない。英国政府がそれを認めないだろうし、EU側もユーロの採用を要求するであろう。とすれば、スコットランドは通貨発行権を失い、それは金融財政政策のフリーハンドを失うことにつながる。そうすると、スコットランドは現在、ある面ではイングランドよりも手厚い福祉政策を行っているそうなのだが、将来的にそれを維持できるかどうか、不透明になってくるのではなかろうか。そしてそれは国内における政治的不満の高まりにつながり、その要因は、EUとのあいだの政治的コントロールの問題にある、ということになるのではないだろうか。
もちろん、人口550万程度の「小国」であるスコットランドは、EUという巨大な市場に組み込まれなければ、経済的に厳しいという側面はあるだろう。しかしながら、SNPの言う “Scotland’s Choice”には茨の道が待ち受けているように私には思われてならないのである。
「ブレグジット」以後の英国政治──連合王国は解体するのか?
スコットランドにおける独立の機運の高まりは、ウェールズや北アイルランドといった連合王国を形成する他の人民にも影響を与えている。それは連合王国(United Kingdom)そのものの存続が危ぶまれる事態につながる可能性もある。実際に、総選挙の直前である2019年11月に行われたある世論調査によれば、過半数の人々が、今後10年以内に連合王国は現行のままでは存続できないかもしれない、と答えたようである(詳細は以下のURLを参照のこと:https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/public-confidence-future-union-much-lower-it-was-five-years-ago)。そして、もし仮に、スコットランドにおいて2度目の住民投票が行われ、多数が独立を支持する結果になったとすれば、それはウェールズや北アイルランドのみならず、上で少し触れたカタロニアや、バスク、フランドルなどといった他のヨーロッパ諸国における分離独立運動にも大きな影響を与えるであろう。また、ブレグジットがそうであったように、ヨーロッパ諸国におけるナショナルな少数派の分離独立要求の高まりは、ある意味で、EUという政治的まとまりに対しても一石を投じることになるだろう。
はたして一連の動きは、連合王国の解体にまでつながってしまうのだろうか。ブレグジットをめぐる喧騒にはいちおうの決着がついたが、今後のヨーロッパの政治状況を見通すうえでも、英国政治の動向からはひきつづき目が離せそうもない。
【執筆者略歴】
白川俊介
関西学院大学総合政策学部准教授、エディンバラ大学客員研究員。
1983年生まれ。九州大学大学院比較社会文化学府博士後期課程修了(博士:比較社会文化)。
日本学術振興会特別研究員などを経て、現職。
主要著書に、『ナショナリズムの力──多文化共生世界の構想』(勁草書房、2012年)。