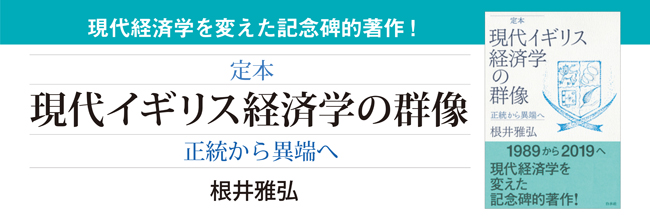根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』立ち読み(5/6)
◇根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』より
五 再びアカデミックな世界へ
ロビンズのあの経済学の定義——「経済学は、諸目的と代替的用途をもつ希少な諸手段との間の関係としての人間行動を研究する科学である」——に初めて触れた人の中には、ロビンズが経済学を自然科学のように捉えていると思った向きも少なくないようである。その代表的な例がケインズで、彼はハロッドに宛てた書簡(一九三八年七月四日付)の中で、次のように述べていた。
「ロビンズが言うところと反対に、経済学は本質的にモラル・サイエンスであって、自然科学ではありません。すなわち、経済学は内省と価値判断とを用いるものなのです(53)。」
しかし、留意しなければならないのは、ケインズがここで「経済学」と言っているものは、ロビンズにとっては「政治経済学」に当たるということである。ロビンズの考えを忠実に説明すると、彼は「経済科学」の主題に関しては、最後までそれを希少性によって条件づけられた行動によって描写する立場を堅持した。ところが、それを越えて、経済科学を政策問題に応用するに際しては、われわれは本質的に科学的証明の不可能な価値に関する仮定を導入しなければならない、とロビンズは言う(54)。したがって、ロビンズは、政治経済学なるものが実践の世界において必須なことは決して否定していないのである。それどころか、政治経済学の教育に関して、それを政治学や歴史学の教育と平行して行なうことを提言してさえいるのである。
「……われわれの教育は、もしそれを政治学と歴史学の適当なコースとお互いに並んで平行的に進められるならば、もっと実りをもたらすであろう。政治学というのは、それが政治経済学に関してはほんの付随的に生ずるにすぎない哲学的・法治的諸問題を体系的に取り扱うからであり、歴史学というのは、それが、それによって将来を予言することができるような諸法則を確かにもたらしてはくれないものの、われわれの関心を現在にのみ限定するならば伝達し損なうような行為の様々な可能性についてのセンスを実際に与えてくれるからである(55)。」
どうしてこんなことを書くのかと言えば、第二次世界大戦後のロビンズのLSEでのアカデミックな生活(一九四六-六一)の中のかなりの時間が、経済思想史の研究に捧げられたからである。経済学を自然科学のごとく考えている人が、思想史研究に何年もの年月を費やすはずがない。ここでは、彼自身に思想史研究の意義を語ってもらうことにしよう。
「わたくしが三十年前に経済学の研究を始めたころのイギリス経済学界の先達者、すなわちマーシャル、エッジワース、フォックスウェルおよびキャナンは、いずれもこの主題〔経済自由の体系〕についてはそれぞれまことに十分な学殖をもつ人びとであった。また、経済思想史にひとかど通暁していることが経済学者たるべきもののもつべき好ましい要素であると、ふつう考えられていた。しかるにその後の年月の間に、このことは一変している。研究中心地の大部分でこの種の知識はじつにどうでもよい装飾であり、化学者には化学史の知識が必須でないと同じように、経済学者にとっても不可欠なものではないと考えられるにいたっている。こうした成行きを、わたくしはいつも不幸なことに思っている。われわれの知識の程度は、純粋に分析的な分野でさえも、時代を直接同じくする人びとの命題以外はすべて乗り越えられてしまったもので抹殺していい、といえるほどけっして進んでいないと思う。応用の分野では、なおさら現代の問題と政策とを理解するため、そのもとをなした問題と政策とを知らなくてはならないと思う。われわれの知的過去に対するこのような無関心が、社会研究のこの特殊部門では一つの大きな特徴となっているけれども、自分たちの時代だけがすぐれているとするような態度は、歴史的思索的教養のみならず実践的見識をもそこなってきているのではなかろうか。(56)」
さて、ロビンズの経済思想史の分野での業績の中でまず挙げなければならないのは、イギリス古典派経済学者たちの再評価であろう。彼らは、しばしば、法と秩序の維持以外に国家に何の役割も認めなかったイデオロギー的自由放任主義者だとして非難されてきた。「死人に口なし。ここにえがき出されている泥人形はまことに悪質な人びとにされている。かれらは資本主義的搾取者の道具であり茶坊主である——これが定り文句である——。かれらは社会改革の徹底的反対者であり、かれらは国家機能を夜警国家機能以外に考えていない。かれらは、最低生活賃金を「擁護」し、労働者階級の福祉にはこのうえもなく冷淡である(57)」。
しかし、古典派経済学者たちが実は社会改革者であり、古典派の経済政策理論が社会改革の理論であったことを悟らなければ、その歴史的位置を見誤ることになるという。彼らは、教育・福祉・公共財の供給などにおける積極的な国家活動の役割を正しく理解していたのであり、彼らの経済自由の体系を自由放任のそれと混同してはならないのだ。ロビンズは言う。
「……古典学派がかれらのシステムを、当時支配的であった制限と規制の諸制度よりも人間の幸福にとってもつ意味において、はるかにすぐれていると考えた点に疑いはない。かれらが、少なくとも当時の観点からすれば、社会改革者であったことをさとらなければ、その正しい位置を見定めることはできない。経済自由の体系とは、干渉するなという冷淡な勧告にすぎないものではない。それは、束縛的で反社会的な障害と思えたものは除かねばならない、自由でパイオニア的な個人の剏意がもつ無限の可能性は解放しなければならない、という緊急の要求なのであった。そして、もちろん、じつにこうした精神からして、その提唱者たちは、実践の世界において、こうした障害の主要形態に対し、すなわち制規会社および組合団体の特権に対して、徒弟法に対して、移動制限に対して、輸入制限に対して世論を動かそうと企てたのである。自由貿易主義運動のうちにあらわれたような十字軍的感覚は、外部からきた他の影響によるところもある。しかし、ある点において、それは自発的企業心およびエネルギーを解放しようとする一般的運動の雰囲気の典型的なものである。いうまでもなく古典派経済学者はこの運動の知的尖兵であった(58)。」
どうしてそうなってしまったのか、最近の経済原論の教科書の中には、古典派経済学者の主張が市場の静態的均衡理論として矮小化されているものも少なくないように思われる。おそらく、それは、数理的な一般均衡理論の観点から古典派を再定式化しようとする試みが、戦後の一時期流行したからかもしれない。しかし、とロビンズは言う。
「経済自由の体制のメカニズムに対するかれらの概念は、これら精巧な実験室的モデルに比べて、たしかにもっと粗雑であり、かつもっと動態的で現実的なものであった。かれらの主張の要点は、市場体系というものはつねに何らかの精巧化された均衡調整に向かうものではなく、むしろセルフ・インタレストの激動的な諸力を指導し抑制しておく、大づかみの指示器なり、大づかみな規律なりを与えるものであるというにあった(59)。」
ロビンズの経済思想史の分野における業績を詳細に論じるには、『イギリス古典派経済学の経済政策論』(The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy, 1952)、および『ロバート・トレンズと古典派経済学の発展』(Robert Torrens and the Evolution of Classical Economics, 1958)という少なくとも二つの著作を研究しなければならないが、ここではスペースの関係でそのための序説にとどめるしかない。
ところで、ロビンズは、戦後になって再びstaff-student seminar を開始した。ボーモル(William Baumol)、ピーコック(Alan Peacock)、フィリップス(William Phillips)など、若き秀才に囲まれて、ロビンズは久しぶりに知的興奮を覚えたに違いない。
「特に若いメンバーの間での議論の鋭利さは、絶え間のない刺激剤であった。そして、カヴァーされたトピックスの範囲は、自分自身の私的関心事とは何の直接の係わり合いも持たないような主題の多くの流れとの接触を保たせるのに役立った。言うまでもないことだが、それはまた、スタッフの補充や昇進を求める候補者の質を観察する絶え間ない機会を与えてくれたのである(60)。」
ロビンズは、学者としての評価を措くとしても、たしかに言葉の真の意味において偉大なる教育者であったと思わざるをえない。LSEを世界でも有数の理論経済学の拠点の地位にまで引き上げたのは、彼の指導と献身に負うところ大であったはずである。したがって、彼がロンドンのFinancial Times のChairmanになるためにLSEを退職した年(一九六一年)に、高等教育に関する委員会の委員長に任命されたことについても、何の不思議もないと思う(彼は、その少し前の一九五九年に、Baron Robbins of Clare Market として上院に列せられていた)。
ロビンズは、すべて才能のある学生は自由な高等教育を有効に受けることを認められるべきである、という堅い信念を持っていた。これは、後に“Robbins principle” として知られるようになった原則である。その委員会の報告Report of the Committee (1963)を読む者は、誰もがロビンズがこの分野の活動に注いだ情熱に打たれざるを得ないであろう。彼の期待した通り、イギリスにおける高等教育は一九六〇年代を通じて飛躍的に拡大していったのだが、何とも皮肉なことに、彼のプリンシプルは、かつて彼の思想に大きな影響を与えたハイエクの哲学に強力にコミットし、公共支出の削減を図ろうとするマーガレット・サッチャー(Margaret Thatcher)の保守党政権によって非難されることになったのである。それも彼の亡くなる年(一九八四年)の出来事であった。
私は、彼の晩年の著作である『高等教育再考』(Higher Education Revisited, 1980)の中に、まだまだイギリスの高等教育の現状に満足していない彼の姿を発見した時、彼に対する尊敬の思いを新たにした。彼の書物は、ある人に言わせれば(61)、いつもeighteenth-century prose とも言うべき名文によって綴られているが、この書物のむすびの言葉もまた、素晴らしい文章である。
「実際、私は、危険な対外的不安定および国内の諸集団と諸目的の矛盾すべてを抱えている現代のわれわれのイギリス社会の不明瞭な見通しについて熟考する時、どうしても次のように論じようと心が向いてしまうのです。すなわち、将来における見通しの改善の主な希望は、高等教育機関によってなされうること、そして時にはそれによって育成されることに存する、と(62)。」
ロビンズの生涯について語る時、彼の経済学者としての経歴を述べるだけでは、片手落ちであるかもしれない。彼は、ロイヤル・オペラ・ハウスのディレクターやナショナル・ギャラリーの保管人という経歴に見られるように、芸術の分野でも立派な仕事をしたからだ。しかし、この章では、その分野での彼の活動は割愛せざるをえなかった。関心のある方は、彼の自伝を参照して頂きたい。
とにかく、ロビンズが教育と知識の発達に対して誰よりも考慮を払った学者であることは、決して忘れてはならないであろう。彼は、『経済思想史における経済発展の理論』(The Theory of Economic Development in the History of Economic Thought, 1968)という著書の中の一章を「教育と知識の発展」に充て、これ以上「知識が経済発展の諸過程にいかに重要なものであるかについて強調せねばならないことは、ほとんどなにも残されていない(63)」として、マーシャルの言葉を引用している。かつて、彼は、若き日において、マーシャルの「代表的企業」の概念に正面から嚙みついた論文(64)を書いたけれども、年とともにマーシャルに対して穏やかな見解を持つようになったようである。そこで、ここでも、その言葉を引用することにしよう。
「観念は、芸術と科学のそれであると、実際的な道具に具体化されたそれであるとを問わず、各世代が先人から受け継いだ贈物のうちで、もっとも「実質的」real なものである。世界の物質的な富は破壊されるとしても、それを造った観念が失われないならば急速に再建することができるであろう。しかし富は失われないとしても観念が失われるならば、富は減少し、世界は貧困に逆戻りするであろう。単なる事実の知識の大部分が失われるとしても、思索の建設的な観念が残っていれば、急速に回復できるであろう。もし観念が消滅すれば世界はふたたび暗黒時代に戻るであろう(65)。」
(53) The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 14, 1973, p. 297.
(54) Lord Robbins, Economics and Political Economy (1981), in An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 3rd edition, 1984, p. xxxi.
(55) Ibid., pp. xxxi-xxxii.
(56) L・ロビンズ『古典経済学の経済政策理論』(市川泰治郎訳、東洋経済新報社、一九六四年)一ページ。〔 〕内および傍点は引用者による。
(57) 前同、四ページ。
(58) 前同、一六-一七ページ。
(59) 前同、一四ページ。
(60) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 219.
(61) Mark Blaug, Great Economists since Keynes, 1985, p. 206.
(62) Lord Robbins, Higher Education Revisited, 1980, p. 112.
(63) L・ロビンズ『経済発展の学説』(井手口一夫・伊東正則監訳、東洋経済新報社、一九七一年)一一〇ページ。
(64) Lionel Robbins, “The Representative Firm”, Economic Journal, September 1928.
(65) Alfred Marshall, Principles of Economics, 8th edition, 1920, p. 780. 永澤越郎訳『経済学原理』 第一巻(信山社、一九八五年)三一一ページ。