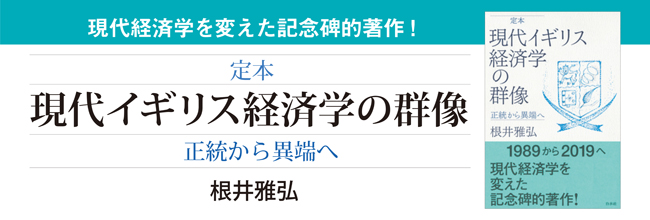根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』立ち読み(3/6)
◇根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』より
三 一九三〇年代のLSEと『経済学の本質と意義』の出版
どこの世界でも同じだと思うが、人材というのは、誠に得がたいものである。それなのに、いつも羨ましく思うのは、一九三〇年代におけるLSEの状況である。一体、どうして、あの時期にあれだけの才能が集まったのであろうか。それは、単なる偶然であったのかもしれない。しかし、これから話していくことは、やはりロビンズのリーダーシップを無視しては、真実から外れるのではないかと私は思うのである。
一九二九年、教授に就任するや、彼はLSEの経済学部門の間の交流を図るために、自分の部屋を提供し、毎週一度ティー・タイムに各部門のスタッフが集まって会合を開くことにした。それとともに、毎週、彼の司会の下でお互いに関心のある主題について研究者が議論し合うゼミナールも始めた。
そして、そのゼミのもう一人の中心人物となるのが、一九三一年にLSEのトゥック経済科学・統計学講座教授に就任したハイエク(F. A. von Hayek)なのである。「一九五〇年に彼がシカゴでの研究職を引き受けるために、われわれのもとから去っていくまでのほとんど二十年間、ハイエクは経済学部門とLSE全体の双方において、思想への主な刺激剤であった。彼の学識は計り知れなかった(19)」。
ロビンズとハイエクは、実践的判断の問題において、しばしば意見を異にしたけれども、自由な社会の理念が現代において危機に陥っていることを懸念している点において、彼らの見解は完全に一致していた。そういう二人の主導の下に、ゼミナールが進行することになったのである。ヒックス( John Hicks)の評伝で述べたように、彼もこの研究会で頭角を現わした一人である。カルドア(Nicholas Kaldor)もまたそうである。他に、アバ・ラーナー(Abba Lerner)、ロナルド・コース(Ronald Coase)、アーサー・ルイス(Arthur Lewis)等々、これらの若き俊英が切磋琢磨する光景は、ロビンズとしては、教師冥利に尽きるものであったろう。
ところで、この時期のLSEについて語る人は、よくそれとケンブリッジとの対抗関係を強調しがちである。たしかに、双方にライバル意識があったのは確かだろうが、そこからただちに両者の間は相互不信と極度の敵意の状態が続いたと即断するのは誤りである、とロビンズは言う。なぜなら、両者の違いは、グループ間のそれというよりも、個人間のそれの場合の方がしばしばであったからである。たとえば、イギリスの旧平価での金本位制復帰に賛成したのは、キャナン(LSE)とピグー(ケンブリッジ)であり、反対したのはケインズ(ケンブリッジ)である、というように。
しかも、ロビンズによれば、LSEとケンブリッジのスタッフは、London and Cambridge Economic Serviceの月一度の会でお互いに顔を合わせる場を持っていたのであり、他のイギリスのどんな大学間の関係よりも、両者は緊密な関係にあったのだという(20)。そうでなければ、カルドアの評伝で述べたように、ロビンズとハイエクの影響を強く受けていた彼が、ケインズの思想に触れて、後にケインジアンに転向する道も開かれなかったであろう。物事はあまり単純に考えてはいけないものだ。
さて、われわれは、これまで一九三〇年代のLSEの雰囲気を概観してきたのだが、次に、その時期に出版されたロビンズ自身の著書について述べなければならないであろう。それこそ、まさに『経済学の本質と意義』(An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1932, 2nd edition, 1935)である。
すでに述べたように、ロビンズの名前は、大部分の経済学者にとって、この書物の中の一文——「経済学は、諸目的と代替的用途をもつ希少な諸手段との間の関係としての人間行動を研究する学問である」——と結び付いている。しかし、以前から、私は、この文章だけを取り出して、彼を理解しようとすることほど、誤解を招きやすいものはないと思ってきた。
人間の書いた書物を読んで理解するのは難しいもので、初めは何度読んでも意味不明だったり、どうしてここにこんな文章が出てくるのか分からなかったりするような箇所も少なくない。ところが、そんな箇所も、それを書いた人間の生涯を知ることによって、突然、明快に理解されることがある。私がかねて疑問に思っていたのは、ロビンズが諸目的達成のための物質的手段が希少であることを論じているところに出てきた次の文章であった。
「われわれは楽園から追放せられた。われわれは、永久の生命ももたず、また欲望充足のための無限の手段ももたない。どちらを向いても、われわれは自分が一つのことを選択する以上、事情さえ違っていたら断念したくないような他のことを断念するほかない。異なった重要性をもつ諸目的を充足するための諸手段が希少であるということは、人間の行動のほとんどいたるところに存在する条件である(21)。」
だが、彼がかつて自ら社会主義運動に身を投じ、その過程で深い幻滅を味わった事実に照らしあわせるならば、この文章が何を言おうとしているか、われわれは明確に理解することができるであろう。人間の価値を、わずか一冊の書物によって判断してはならない、と私が主張する所以である。『経済学の本質と意義』を読む時、その書物は、社会主義運動をくぐり抜け、社会経済における「有限な資源の配分」の重要性を悟った一人の人間によって書かれたという事実をつねに念頭に入れておかねばならない。
ところで、あの経済学の定義自体は、何ら独剏的なものではなく、ロビンズも認めるように、オーストリア学派とウィックスティード(P. H. Wicksteed)の研究から自然に生まれたものであった(22)。彼は、学生時代に読まされたキャナンの『富』(Wealth, 1914)が、経済学の主題を物質的厚生のタームで定義していることにかねて不満だったという。現実の世界には、物質的厚生とは何の関連もなくても、経済的側面を持つような諸活動が存在するではないか。たとえば、「料理人のサーヴィスもオペラのダンサーのサーヴィスも、需要との関連において限られており、かつ代替的用途にあてることのできるものである(23)」というように。
しかし、経済学の定義を並べて、それらの優劣を論じてみても、あまり生産的とは思われないし、ロビンズがその書物の中で論じようとしたことも、もちろん、それに尽きるものではない。彼の主張は、大きく分けて次の二つに分けることができるであろう。一つは、効用の個人間比較は価値判断であり、科学的根拠を持たないということ、もう一つは、「である」を含む命題(存在命題)と「べき」を含む命題(当為命題)はまったく別の次元にあるということである。
まず、第一の論点だが、彼がなかんずくその科学的根拠を問おうとするのは、いわゆる「限界効用逓減の法則」である。その法則によれば、人は何かをより多く持てば持つほどその追加単位をますます小さく評価する。それゆえ、人は実質所得が多くなればなるほど所得の追加単位をますます小さく評価する、換言すれば、富める者の所得の限界効用は貧しい者の所得の限界効用よりも小さいという。そこで、もし富める者から貧しい者へ所得の移転がなされ、しかもこれらの移転が生産に不利な影響を与えないならば、総効用は増大するであろう。それゆえ、そのような移転は、「経済学的に正当化」されると主張される。
一見したところ、この議論はもっともらしくみえる。だが、ロビンズは、その命題が「異なった個々人の経験を科学的に比較しうるか否かという形而上学的大問題を、証明なしに暗に仮定して論じている(24)」ことを鋭く突いた。ところが、実際には、われわれは、Aの満足をBの満足と比較して、その大きさを検査する手段を全く持っていないのだ。したがって、このような非論理的な限界効用逓減の法則の拡張に基づいた議論は、科学的根拠に欠けると言わねばならない。ロビンズは言う。
「交換の理論は、わたくしが、一塊六ペンスのパンのわたくしに対する重要さと、市場の機会によって示された他の代替物に費やされた六ペンスとを比較しうると仮定する。そしてそれは、このようにして示されるわたくしの選好の順序が、パン屋の選好の順序と比較されうると仮定する。けれどもそれは、いかなる点においても、わたくしが六ペンスをパンに費やすことによって得る満足を、そのパン屋がこの六ペンスを受け取ることによって得る満足と比較することが必要であるとは仮定しない。この比較は全く異なった性質の比較である。それは、均衡理論において決して必要とされないところの、そして均衡理論の仮定に決して含まれないところの比較である。それは、必然的にいかなる実証科学の範囲にも属しない比較である。Aの選好は、重要さの順序においてBのそれよりも上位にたつ、と述べることは、Aはmよりもnを選好しBはmとnを異なった順序で選好する、と述べることとは全く違う。前者は慣例的な価値判断の分子を含んでいる。したがってそれは本質的に規範的である。それは純粋科学の中に全くあり場所をもっていない(25)。」
第二の論点は、存在命題と当為命題の混同に関係している。いま、仮に「異なった経験の通約可能性」「満足享受能力の均等性」などの仮定を承認したとして、この基礎の上に、われわれがある種の政策は「社会的効用」を増加させる効果を持つと証明するのに成功したとしよう。しかし、たとえそうだとしても、それはそのような政策が実施されるべきであるという推論を何ら正当化しない。なぜなら、そういう推論は「この意味における満足の増加がはたして社会的にどうしてもやらねばならぬことであるか否か、という問題全体を、証明なしに暗に仮定して論じている(26)」からである。すなわち、ロビンズは、「べき」を含む命題は、「である」を含む命題とは全く異なった次元にある、と主張するのである。
「経済学は、究極的な価値判断の妥当性については意見を述べることはできないのである(27)。」
ロビンズの主張に対しては、当然のことながら、反論が起こった。一九三八年、英国学術協会F部会の会長講演において、ハロッド(R. F. Harrod)がこの問題を取り上げたのである。ハロッドによれば、限界効用逓減の法則は、人間の経験に基づくものである。しかも、その経験は、「市場や価格の研究が恵んでくれたそれよりもはるかに広く、人間の自覚的生存のもっとも最初の段階にまで㴑るような経験(28)」であるという。詳しくは本書の第六章で論じるつもりだけれども、ハロッドは、終生、演繹の限界と事実観察の重要性を主張し続けたので、彼がロビンズの書物に敏感に反応して、経験と帰納の論理を改めて強調する気になったのは、十分に予想のつくところである。
ハロッドによれば、ロビンズによる限界効用逓減の法則の拡張への批判が重要となるのは、経済学が成熟した精密科学である場合に限られるという。「しかし、実際は、経済学の成果も、ある限られた範囲の外では、経済学者がそのような思い上がった態度をとるのがことによると滑稽に思えるような問題によって四方取り囲まれているのである(29)」。
そして、さらにハロッドは、アリストテレスの次の言葉を引用して、追い討ちをかける。「教養のある人間なら、各研究部門の性質が許す程度の厳密性を得ることを期待すべきである(30)」と。
ハロッドにしてみれば、もし効用の個人間比較が不可能ということになれば、厚生学派の政策勧告のみならず、すべての政策勧告が排除されてしまうので、ロビンズの主張は精密科学ではない経済学にとって危険性を含む思想のように思えたのであろう。
ただし、ここでロビンズに公正を期すためにも、彼が経済学者に対して倫理上の諸問題に関して意見を述べることを決して禁じたわけではない、ということを指摘しなければならない。たしかに、彼は抽象的で価値自由な経済学(ロビンズに忠実に、「経済科学」economic science と呼んだ方がよいかもしれない)の独立を主張したのだけれども、それは何も彼が倫理や政治に関係する「政治経済学」の存在を否定したことを意味しない。ロビンズが要求したのは、ただ両者を峻別することであった。彼は言う。
「……以上すべてのことは、経済学者は倫理上の諸問題に関して意見を述べてはならない、ということを意味するものでは全くない。それはあたかも、植物学は美学ではないという議論が、植物学者は庭園の設計について自分自身の見解をもってはならない、ということを意味するものではないのと同様である。それどころか、経済学者が、これまでこれらの問題について長い間広範囲にわたって思索を重ねてきたことはむしろきわめて望ましいことなのである。というのは、こうすることなしにはかれらは、解答を求められている諸問題に含まれている所与の諸目的について十分その意味内容を理解することができないであろうからである。われわれは「もし人が経済学者である以外にはとりえのない人であったら、その人は立派な経済学者でありそうもない」というJ・S・ミルに同意しないかもしれない。けれどもわれわれは、少なくともかれがそうでない場合ほどには有用でないかもしれない、ということに同意してさしつかえないのである、われわれの方法論上の公理は局外者の興味の禁止を全く含んでいない! われわれの主張するところは、一般法則のこの二つの型の間にはなんの論理的関連もないということ、そして一方の結論を強めるために他方の是認に訴えてみてもなにものも得られない、ということにつきるのである。(31)」
ロビンズの考えは、一九三八年のハロッドの論文に対するコメントとして発表された短い文章(32)を読めば、さらに明確になるであろう。それによれば、ロビンズの政治的行為の諸問題に対する態度は、つねに暫定的な功利主義ともいうべきものであったという。彼はベンサム流の極端な功利主義者ではなかったけれども、各人を1とカウントし、その仮定の上に、どのような方法が最大満足をもたらすかをつねに考えてきた。経済学の研究に向かったのも、こういう功利主義的な関心からであった。
その当時のロビンズを引きつけたのは、ピグーの『厚生経済学』(The Economic of Welfare, 1920, 4th edition, 1932)であった。政策の錯綜した反響を通じて利益と損失を巧妙にバランスさせるというピグー流の考えに彼は魅了された。
ところが、時が経つにつれて、このような政治と経済分析の間の完全な連続性の存在に対する彼の信念が動揺してきた。それは、彼がSir Henry Maine の書物を読んでいた時のことである。インドの官吏がインド四姓の第一階級たるバラモンに対してベンサム主義を説明したところ、バラモンが次のように反駁したという話が出てきた。「しかし、それはとても正しいとは言えません。私は、あそこにいる不可触民の十倍の幸福享受能力がありますから」。
ロビンズは言う。「私はバラモンに賛成することはできなかった。しかし、人間がすべて等しい満足享受能力を持つと見なすことを私が選び、そして身分の上下によってその能力に違いがあると見なすことをバラモンが選ぶ場合、われわれの間の意見の相違は、社会的判断の他の領域において用いられるのと同じ論証方法で解決しうるようなものではないという確信から私は逃れることはできなかった(33)」。
そして、『経済学の本質と意義』を書く頃までには、伝統的経済学の諸命題を、それらがすべての人間が平等な満足享受能力を持つという特殊な仮定を含むか否かによって分類するという習慣が確立していたのだという。今や、彼は、効用の個人間比較を含む命題は、それを含まぬそれとは違って、観察や内省による検証の不可能な命題だと考えるようになった。なぜなら、その仮定は、検証可能な事実についての判断というよりは、科学の外部にある一つの価値判断だからである。
だが、ロビンズは、自分とハロッドの間の違いを強調し過ぎるのは、誤解を招きやすいと考える。というのは、両者とも、実践の上では、そういう仮定が置かれなければならないという点では一致しているからである。ただ、平等の仮定が経済学の一部だと主張するハロッドに対して、ロビンズは、それは外部から来たものであり、科学的というよりも倫理的なものだと考える点で異なるだけである。ロビンズの言葉を聞いてみよう。
「われわれの論争は、定義と論理的地位に関するものであって、人間としてのわれわれの義務に関するものではない。とにかく、行為の領域においては、本当の意見の相違は、科学的という形容詞をもって呼ばれるべき正確な範囲について論争する人々の間にあるものではなく、人間は平等であるかのように扱うべきであると主張する人々と、そう扱うべきではないと主張する人々との間にあるのだ(34)。」
ところで、ロビンズによれば、『経済学の本質と意義』の第一版(一九三二年)の中には、彼がどうしても満足することのできなかった部分があったという。すなわち、経済学の一般命題の性質を論じたところがそれである。当時、彼はオーストリア学派のa priori tradition(先験的伝統)に深く影響されながら、経済学の一般命題の妥当性を結局のところ事物の本質に求め、それは検証や反証の影響を受けないものであるとした。つまり、経済理論の内容は、観察・歴史・心理学などから帰納的に導き出されるものではなく、人間行為が服さねばならない諸制約に関しての普遍的な真理だというのである(35)。
しかし、そういう本質主義に満足できなかったロビンズは、第二版(一九三五年)において、それを改め、経済学の一般命題を導いた諸仮定は現実に存在していることが直接に知られるのだから、そこから演繹される一般命題が現実に合致しているのは当然であると主張するようになった(36)。ところが、こういう変更も、ロビンズを結局納得させることができないでいた。もともと、ロビンズの考えは、「事実にそれ自ら語らしめる」というベヴァリッジや素朴な計量経済学者たちに対する反発から生まれたものであったが、ようやくカール・ポッパー(Karl Popper)の科学方法論(反証主義)が提示されて初めて彼も一応の解決を得たように思ったようである(37)。そういえば、ポッパーをLSEに招聘したのは、彼の同僚ハイエクであった。
さて、われわれは幾分長いスペースを費やして、ロビンズの主張を追ってきたけれども、もう一度、彼の書物は社会主義的組合運動の非合理主義に幻滅した一人の人間によって書かれたという事実を振り返っておくことにしよう。私は、初めて彼の『経済学の本質と意義』を読んだ時、どうしてもそのむすびの言葉が気になっていた。しかし、彼の経歴を知ったいま、ようやくその意味も明瞭に理解できるようになってきた。経済学の書物の中には、どう見てもそのむすびが尻切れとんぼに終わっているものが少なくないが、ロビンズのそれは圧倒的な名文である。そこで、本節も、その言葉でもって区切りを付けることにしたい。
「もし非合理的なことが、もし時々刻々の、外界の刺激と調整されていない衝動、という盲目的な力に身をゆだねることが、他のすべての善にまして選好さるべき善であるならば、経済学の存在理由がなくなるということは事実である。そしてこの究極的な否認、すなわち、意識的となってきた選択の悲劇的な必然性からのこの逃亡、を支持せんとする人々が現われてきたことは、血にまみれて同胞相争い、当然知的指導者たるべきであった人々によってほとんど信じられないほどに裏切られた、われわれの時代の悲劇である。すべてのかような人々に対してはいかなる議論もありえない。理性に対する反逆は、本質的には生それ自身に対する反逆である。しかしながら、いっそう積極的な価値を依然として肯定する人々に対しては、他のいかなるものにもまして、社会的配置における合理性の象徴であり護衛であるところのこの知識の分野は、来るべき憂慮される時代において、それが表わしているものに対する右の脅威がまさに存在するという理由によって、特殊のそして増大した意義をもたねばならぬのである(38)。」
(19) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 127.
(20) Ibid., p. 134.
(21) ロビンズ『経済学の本質と意義』、二四ページ。
(22) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 146.
(23) ロビンズ『経済学の本質と意義』、二五ページ。
(24) 前同、二〇七ページ。
(25) 前同、二〇八—二〇九ページ。
(26) 前同、二一四ページ。
(27) 前同、二二一ページ。
(28) R. F. Harrod, “Scope and Method of Economics”, Economic Journal, September 1938, p. 387.
(29) Ibid., p. 396.
(30) Aristotle, Ethica Nicomachea. 1094b., quoted in Harrod, op. cit., p. 396.
(31) ロビンズ『経済学の本質と意義』、二二五—二二六ページ。傍点は引用者。
(32) Lionel Robbins, “Interpersonal Comparison of Utility: A Comment”, Economic Journal, December 1938.
(33) Ibid., p. 636.
(34) Ibid., p. 641.
(35) Cf., Norman Barry, Lionel Robbins, in Thinkers of the Twentieth Century, edited by E. Devine, M. Held, J. Vinson, and G. Walsh, 1983, p. 480.
(36) 「経済理論の諸命題は、すべての科学的な理論と同様に、一連の仮定から演繹されたものであることは疑問の余地がない。そしてこれらの仮定のうちの主要なものはすべて、財の希少性——これがわれわれの科学の主題である——が現実の世界に実際に現われる表現形態についての単純にして明白な経験的事実をなんらかの形で含んでいる仮定である。価値論の主たる仮定は、個々人がその選好をある一定の順序にならべることができるという事実であり、そして実際そうしているのである。生産理論の主たる仮定は、生産要素が一つ以上存在するという事実である。動学理論の主たる仮定は、われわれが将来の希少性について確かでないという事実である。これらの仮定は、ひとたびその本質が十分に理解されるならば、現実におけるその対応物の存在が広範囲の論争を許すような仮定ではない。われわれはそれらの妥当性を確立するために管理された実験を必要としない。すなわち、これらの仮定は、あまりにもわれわれの日常経験していることがらであるから、われわれはただ、それらは明瞭と認められる、と述べさえすればよいのである。実際、危険なことは、それらの仮定があまりに明瞭であるために、それらをさらに立ち入って検討することによってなにも意義あることが演繹されえない、と考えられるかもしれないということである。しかも実際、この種の仮定にこそ高級な分析の複雑な諸定理が結局依存しているのである。そしてそれらが仮定する諸条件が現実に存在することから、経済学のいっそう一般的な諸命題の一般的適用可能性が引き出されるのである。」(ロビンズ『経済学の本質と意義』、一一九—一二〇ページ)
(37) Robbins, Autobiography of an Economist, pp. 149-150.
(38) ロビンズ『経済学の本質と意義』、二三七—二三八ページ。