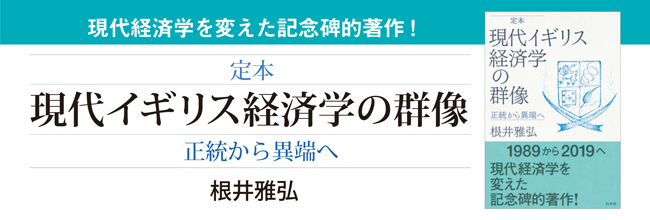根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』立ち読み(1/6)
◇根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』より
第四章 破れた夢——ライオネル・ロビンズの生涯
日頃、研究に携わりながら考えるのだが、研究者にとっての要件とは一体何なのだろうか。その学問を窮め尽くした大家であれば、その問に対して一応の解答を与えることができるのかもしれないが、これからまさに研鑽を積もうとする若い研究者にとっては、それはつねに気になる怖い問題である。
まだ、大学院に入る前の頃、そんなことを思いながら、私はある経済学者の自伝を読んだ。そして、その問に対する唯一のとは言わないまでも有力な解答の一つを得たような気がした。すなわち、それは、研究者にとって「知的正直」ということが大切なのではないか、というものである。
その『一経済学者の自伝』(Autobiography of an Economist, 1971)を書いた人こそ、まさにライオネル・ロビンズ(Lionel Charles Robbins)である。
ロビンズの名前は、わが国の経済原論の書物の中では、たいてい第一章に彼による有名な経済学の定義——「経済学は、諸目的と代替的用途をもつ希少な諸手段との間の関係としての人間行動を研究する科学である(1)」——とともに、ほんの一瞬登場するだけのようである。ロビンズを語る場合に、その定義を持ち出すのは、決して的外れではない。しかし、まるで彼にはそれ以外に業績がないかのごとく、ほんの数行で片づけてしまってよいものであろうか。私は、人間の価値を、たった一冊の書物、それもわずか一文によって判断するのは誤りだと思う。そのことは、彼の生涯を見ていけば、誰の目にも明らかであろう。そこで、この章では、ロビンズの学識を深く尊敬する一人として、彼の生涯と思想を追ってみたい。
一 第一次世界大戦の衝撃
「一九一四年八月における戦争の勃発は、私の家族全体にとって、青天の霹靂のごとく登場した(2)。」
ロビンズは、第一次世界大戦の与えた衝撃を、右のように語り始める。彼の家族は、戦争は、国際紛争を解決する手段としては全く不適切であり、しかも国際関係の発展は戦争をますます起こりにくいものにしつつあると信じていた、あのリベラリズムの流れに属していた。それにもかかわらず、戦争が勃発してしまったのだ。
ロビンズは、一八九八年十一月二十二日、イギリスのミドルセックスに、父親ローランド・リチャード・ロビンズと母親ローザ・マリオン・ロビンズの間に生まれた。父親は、ヴィクトリア時代の様式に対する確固たる理想と原則に対する断固たる献身を持ち合わせていたが、長年President を務めたNational Farmers’Union 全体が後の一九三〇年代に保護貿易に傾いていくのをみるや、自発的に身を退いたような人であった。
ところが、戦争の進展を見て、彼は、この戦争が数年続かざるを得ないだろうと判断した。そうなれば、自分の息子も兵隊に取られる歳になって、戦場へ送られてしまうであろう。そうならないためにも、息子をできるだけはやく大学に進学させ、一年でも二年でも大学での勉強を経験させておいた方がよい。彼はそう考えて、一九一五年秋、乗り気を示さぬ息子をユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)に強引に入学させたのである。
いつの時代でも、親は子供の将来を自分の思うように設計したがるものだが、それが成功する例はほとんどないし、たとえ成功したとしてもその子供が本当に幸福になるかは疑問である場合が多い。ロビンズも、大学に入って、人文科学を専攻することになったのだけれども、どうしても次第にイギリスに不利になっていく戦局のことが頭から離れず、学業に没頭できないでいた。
「もし父が、私をユニヴァーシティ・カレッジに置いておけば、軍隊に入るべき歳に達するまで、私を戦争から引き離すことができると考えたのであれば、それは悲しくも誤っていた(3)。」
彼はつねに戦争のことを、そして自分がそれに参加していない事実のことを考えた。なんとかして、自分の本当の歳を誤魔化さずに軍隊に入ることはできないのだろうか。彼は両親を説得するのに苦労した。しかし、とうとう父親は降参せざるを得なかった。彼は、ロビンズ家の事務弁護士のWar Office に勤める友人の計らいで、一九一五年のクリスマス直後、入隊に成功するのである。
軍隊に入ってみて、彼は初めて兵士たちの猥雑な世界を知った。「軍事状況において、普通の人間がいかに話し、考え、そして生きるかを発見することは、私の家庭での生活(または学校での生活でさえ)の中の何物も微塵も用意してくれなかった何かであった(4)」。ところが、その彼らが、戦場において、いかに勇敢に戦うかも知った。そして、ロビンズも、西部戦線におけるactive service で自らに傷を負う。彼はもはや戦時勤務に適さないと判断され、イギリスへ傷病兵として送還されるのである。彼を徹底的に鍛え直した三年間の軍隊生活は、こうして終わりを告げた。
一九一八年十一月、第一次世界大戦が終了した時、ロビンズは大学に復学して学問を続ける意欲を失っていた。もう学問など、どうでもよかった。「私は、現存秩序の批判と根本的変化のための諸提案を受け入れるような気分の中にいた(5)」。だが、共産主義やマルクス主義は、どうしても好きになれなかった。そういう時、彼の心を捕えたのは、ギルド社会主義であった。
ギルド社会主義の思想の先駆者は、ペンティ(A. J. Penty)やオレージ(A. R. Orage)であったが、その思想を体系化したのは、ホブソン(S. G. Hobson)のNational Guild(1912)であると言われている。この運動そのものは、短期間しか続かなかったけれども、一九二〇年代のイギリスでは多数の支持者を集めた社会主義の一派である。そして、その特徴は、簡単に言えば、社会主義とフランスのサンディカリズムの結合であった。ロビンズは、このような社会主義運動に身を投じようと決心したのである。
彼は父親と喧嘩し、家庭を離れた。色々な組合に就職しようとしたが、どこからも断られた。そんな彼を拾ってくれたのは、のちに労働党の政治家となるアーサー・グリーンウッドであった。ロビンズは、彼に付いてThe Labour Campaign for the Nationalization of the Drink Trade のために働くことになった。
初めは、たしかに未知の分野であり、面白かった。ところが、時間が経つにつれて、まもなく始まるに違いないと思った社会改革は非常に遠いものであり、また社会主義運動の指導者たちが経済問題に全く無理解であるのを知って、彼は運動に幻滅を感じるようになるのであった。
「根本的な仮定は、至るところで、経済問題は現実には存在しない、というものであった。すなわち、必要なすべては、財産を国有化し、産業の統制を労働組合の手に握らせることであった。私は、これを少し不満に思うようになり始めた(6)。」
社会主義のプロパガンダの文献には、社会経済の根本的事実が無視されている。人々の要求を満たすためには、まず資源が必要であり、しかもその資源は必ず有限である。社会主義者たちは、どんな社会にも存在するこの「有限な資源の配分」という根本的事実を忘れているのではないだろうか。運動に身を投じて一年経つ頃までには、彼は自分をそこへ駆り立てた衝動のイデオロギー的基礎に疑問を抱くようになっていた。
その頃、彼は短い休暇をパリで過ごすことにした。彼は孤独であった。「私は、誰も知らなかった。私は、ウェイター、ホテルの使用人、ある大通りの売春婦——彼女の申し出を、私は丁重に断った——以外には、誰とも話さなかった(7)」。だが、ルーブル美術館だけは別だった。彼が特に気に入っていたのは、印象派と後期印象派の作品を集めたカモンド・コレクションであった。
「ここに、私は来る朝も来る朝も座って、セザンヌの「青い瓶」をうっとりして眺めたものだった。それは、私にとって、色を通じて感情を伝えようとする可能性の啓示であった。また、ドストエフスキーの『悪霊』の悲惨なページを読みながら、しばしば私は涙を流したものであった。……私は、自分のしていることが、何らかの現在価値または将来価値を持っているとは、もはや信じなかった。……それは、私が自分の以前の信念に対して背を向けてしまって、突然現状の肯定者になってしまったということではない。それはむしろ、すべての事実とすべての議論を手に入れた上で、率直な知性によって冷静に到達された結論に基づいているどころか、それらの信念が、事実上、感情的反応と希望的観測の副産物であり、そして私の知っているうちの誰もそれらをさらに吟味しようとしなかったからなのであった。私が自らを大学での訓練とそれが開くであろう多様な経歴の可能性から断ち切ったのは、こんなことのためだったのだ。何と馬鹿なことをしたのだろう。パリを去るようになる頃までには、私は一つのことを確信していた。すなわち、私にできる最善のことは、なるべくはやく運動から足を洗うことである、と(8)。」
ロビンズは、再び大学に戻って、学問に専念したいと思った。しかし、父親と喧嘩して、家庭を離れた彼には、お金がなかった。そんな時、彼はロンドンのある喫茶店に入ろうとしたところ、何と奥のテーブルに父親が座っているではないか! 父親は息子の学問への意欲を見抜き、即座に七五〇ポンド(年二五〇ポンド)の小切手を書いてくれた。ロビンズは、その瞬間まで株式仲買人にでもなって、まず、お金を貯めなければならないとさえ考えていたのである。父親の言葉は、彼の人生を変えたのだ。
「次の朝、私はロンドン・スクール・オブ・エコノミックスまで出かけて行って、この次の学期のための学生登録をしたのである(9)。」
註
(1) L・ロビンズ『経済学の本質と意義』(辻六兵衛訳、東洋経済新報社、一九五七年)二五ページ。これは原著第二版(一九三五年)の邦訳である。
(2) Lionel Robbins, Autobiography of an Economist, 1971, p. 33.
(3) Ibid., p. 37.
(4) Ibid., p. 38.
(5) Ibid., p. 56.
(6) Ibid., p. 65.
(7) Ibid., p. 68.
(8) Ibid.
(9) Ibid., p. 71.