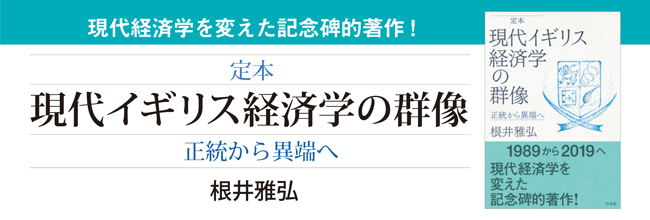根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』立ち読み(2/6)
◇根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』より
二 LSEでの勉学時代から若き教授へ
初めて経済学の書物を繙いて、ロビンズの経済学の定義に触れると、たいていロビンズという学者は冷たい男だという印象を持つようである。経済学部の学生から、そんなことを聞く度に、一人の人間を一冊の書物で判断することが、いかに危険であるかを改めて感じないわけにはいかない。ところが、前に見てきたように、ロビンズは意外にもかつてやむにやまれず社会主義運動に身を投じた一人の若き熱血漢なのであった。
彼の若き情熱のことを思う度に、どうしても私はシェイクスピアの作品の中から引用したい衝動に駆られてしまう。
甘いものほどとりすぎるとすぐに飽きがくる、
そして胸が悪くなるほど見るのもいやになる、
また異端の教えはいずれ人に捨て去られる、
そして欺かれていたと知ったものに憎まれる。
シェイクスピア『夏の夜の夢』第二幕第二場より
(小田島雄志訳、白水uブックス、一九八三年)
しかし、今や、彼の情熱は、LSE入学とともに、学問の方へ向かうことになった。そこで、ロビンズが入学した頃のLSEがどういう状況にあったかを簡単に見ていくことにしたい。
さて、LSEが、シドニー・ウェッブ(Sidney Webb)やバーナード・ショウ(Bernard Shaw)などの尽力によって設立されたことは、今日ではよく知られているが、その事実ゆえにこの学校の特徴が少しく誤解されてきた嫌いがあると思う。というのは、いまだに当時のLSEのことを、社会主義者の温床であったと信じている人がいるからである。
ところが、ロビンズが明確に述べているように(10)、LSEは、剏立当初から、自由な研究と知識の前進のみに捧げられた真の独立の機関であったし、人事においても、特定の政治的立場に立つ人を優遇するようなことは決してしなかった。その証拠に、ロビンズ自身、ウェッブとは政治的信条を異にするにもかかわらず、ウェッブも委員の一人である委員会によって後に教授に指名されるのである。
そのことは、当時、LSEのスタッフにどんな人物がいたかを見ればさらに明らかであろう。政治学部門のHead であったグラハム・ウォラス(Graham Wallas)、彼はフェビアン主義者と絶縁した人である。貨幣・銀行論の教授のフォックスウェル(Foxwell)は、トーリー党の社会改革者であり、左翼の敵を自認していた。統計学の教授のボーリー(A. L. Bowley)は、ほとんど保守主義者と言ってよかった、等々。
とにかく、政治的立場がどうであれ、そこでは自由な研究が奨励されたのである。その知的雰囲気を伝えるのに、ロビンズは“Rerum cognoscere causas——to know the causes of things” という表現を用いている。「これは、私が以前に知らなかった何かであったが、ほとんどただちに私が自分の求め続けてきた精神的家庭であると感じた何かであった(11)」。
LSEでロビンズが教えを受けた先生の中でも、まず最初に挙げなければならないのは、ヒュー・ドルトン(Hugh Dalton)とハロルド・ラスキ(Harold Laski)の二人であろう。
ドルトンは、後の政治家としては、必ずしも優れた才能を発揮しなかったかもしれないが、経済学者としての彼は、ケンブリッジでピグー(A. C. Pigou)とケインズ(J. M. Keynes)の訓練を受けた後、第一次世界大戦の前には、LSEのキャナン(Edwin Cannan)の下で研究を積んだことが、その教えと思想に独特の特徴を与えていた。ドルトンは、自分が面白くないと思う人々に対しては、しばしば無礼な態度をとることもあったらしいけれども、自分の気に入った人々には、惜しまず、そして党派的差別なく、激励を与えたという。
ロビンズが、ドルトンに対して尊敬の念を抱くのは、ドルトンがアカデミックな誠実さにつねに忠実であったことである。たとえば、ロビンズはこんな話を紹介している(12)。ドルトンは、資本課税の支持者として、労働党のために小冊子を書いたのだが、授業において、それを喧伝して終わるような不誠実な行為を決してしなかった。彼は次のような授業をしたという。「たった今、私は資本課税に賛成する議論に関する私の見解を披露しました。それで、今度はそれに反対する議論について皆さんにお話すべきであろうと思います」。
もう一人、ロビンズとの因縁が深いのは、ラスキである。当時のLSEでは、学士号を取るためには、経済学、政治学、歴史(経済史および政治史)に関する三つの論文と、二つの外国語から翻訳する能力の証明が必修であったが、ロビンズはその中の政治学のテーマに政治思想史を選んだために、必然的にラスキの指導を受けることになった。ところが、ロビンズは広範な文献に通暁し、明快な表現力を持ったラスキを尊敬しつつも、最初からどうも馬が合わない感じを拭い切れなかったようである。ラスキと会ってまもなく、ロビンズはこんなノートを残していたらしい。
「今日、ラスキに社会主義について語る。ほとんどは期待外れ。彼は経済学をほとんど全く知らないと確信する。彼が今日言ったことから判断すると、彼はほとんどセンティメンタリストの一人に数えられるかもしれない。彼の言回しには奇妙に不満な響きがある。あまりに総合的で、あまりに大袈裟だ。それは、彼の驚くほど鋭い分析装置の背後に、ほとんど幼稚な個性——ほとんど痛々しい感情的バランスの欠如——を暗に示しているようだ。奇妙なことと言えば、彼の理論的(すなわち、集産主義的)先入観にもかかわらず、彼がこれまでに私の会ったうちでもっとも個人主義的人間の一人だということだ。それは、彼が普通の人よりもはるかに個性的だという意味ではない。滑稽なほど、彼には個性はないと思う。つまり、彼は子供のようにいまだに模倣好きなのだ。しかし、教育のある人間で、彼ほど体系的なチームワークまたはリーダーシップの才能を持っている人はほとんどいないだろうと想像する。彼はつねに友人たちに囲まれた孤独な人物——感嘆する傍観者の間の恐るべき子供——なのだろう(13)。」
出会ってまもなく、こんなに鋭利な刃物のような眼で見られる先生の気持はどんなものか、とつい考えてしまうけれども、ロビンズとラスキは、その後、石炭産業の国有化をめぐって明らかに対立することになる。その頃、かつてロビンズを拾ってくれたアーサー・グリーンウッドが、完全な国有化以外は十分ではない、という見解を表明していた。そこで、ロビンズはこの問題に関する自分の見解をペーパーにしてラスキに提出した。ロビンズの見解というのは、完全な独占企業よりも、競争に服する小グループの集産主義的企業の方が、ほとんどつねに効率的ではないのか、というものであった。
ところが、ロビンズがその論文を読んでいくうちに、ラスキはますます不愉快な顔つきになって、最後に冷たくこう言った。「うむ、それは非常に反動的立場の優れた報告だ」。そして、ただちにラスキは話題を変えてしまった。ロビンズは、もはや何の抗議もしなかった。しかし、そのことで、自分の以前のドグマとは縁を切ることができたように思ったという。
その他のLSEの先生としては、今日ではほとんど読まれなくなったものの学識豊かだったキャナンと、誰よりも教師として優れていたウォラスをロビンズは挙げているが、ここではそれを指摘するにとどめよう。
「こうして、卒業するようになる頃までには、私は自分のドグマティックな過去との関係をほとんど断ってしまった。私は、自分がどこへ行きたいのか、まだはっきりと確信できなかった。しかし、少なくとも、私は何の主義にも縛られない自由な精神となっていたのである(14)。」
* * *
さて、LSEを一九二三年秋に卒業したロビンズは、職を捜さねばならなかった。色々と当たってみたが、当時は今と違って社会諸研究は人気のある学問ではなかったので、なかなか職も見つからなかった。ところが、ロビンズが困っているという噂を聞いたドルトンが、ベヴァリッジ(William Beveridge)——彼はLSEのディレクター(Director)であった——に対して、ロビンズを一年間助手に雇って、彼の本Unemployment:A Problem of Industry(1909)の改訂の仕事の手伝いをさせるように計らってくれたのである。
それは、たった一年間の仕事であったけれども、ロビンズは、その間、周囲を見渡すことのできるbreathingspaceを与えられたような気がした。しかも、時間的余裕もあったので、さらに経済学を勉強することができた。卒業した次の年の夏には、アイアリス・ガーディナー(Iris Gardiner)と結婚、この頃のロビンズは、将来への希望に燃えて、日夜研鑽を積んだに違いない。
一年間の助手を終える頃、ロビンズは誰かの勧めで新しく剏設されたRockefeller Travelling Fellowships に応募し、それにほとんど採用が決定しかけた。ところが、ちょうど同じ時期、オックスフォード大学ニュー・カレッジのSenior Tutor が、一年間の臨時のチューターを引き受けてくれないか、とロビンズにアプローチしてきたのである。彼は迷った。しかし、アイアリスと慎重に熟慮した末、彼はニュー・カレッジに行くことに決めたのだった。
ニュー・カレッジでは、初めのうち緊張し過ぎて、仕事が終わると、彼は食欲もないほど疲れたようだ。しかし、彼には、幸い、若さと快活さがあった。しかも、優秀な学生に囲まれて、彼は結構幸せであった。
一年間の臨時の職を終えようとする時、ドルトンが再びロビンズに会いにやって来た。彼は、ロビンズをLSEの講師として迎えるための交渉を持ち込んだのである。ロビンズはすぐさま承諾した。「ギャンブルは成功したのだった。私は、今や、アカデミックな階級序列の上に深く位置したのである(15)」。
LSEでの一年目(一九二五—二六)、キャナンは教授としての最後の一年を過ごしていた。しかし、二年目(一九二六—二七)に入っても、キャナンの後継者が決まらないばかりか、ドルトンがますます政治活動に忙しくなったので、ロビンズはLSEの行政的責任をほとんど一人で負う羽目になった。
だが、そういう仕事に忙しい中にも、彼の研究は着々と進んでいった。ここで、指摘しておかなければならないのは、ロビンズが、この頃、ヨーロッパ大陸やアメリカの経済学を熱心に勉強したことである。カッセル(G. Cassel)、フィッシャー(I. Fisher)、フェッター(F. A. Fetter)、それからオーストリア学派の学者たちの著作を貪るように読んだ。
特に、ロビンズが影響を受けたのは、ミーゼス(Ludwig von Mises)である。彼は、今や、過去の自分のイデオロギーとはきっぱりと縁を切った。そして、個人の自由と経済的効率は、集産主義体制下よりも市場経済体制下の方が維持しやすいという考えを受け入れるようになった。彼は、おそらくミーゼスに没頭したのであろう。一九七一年の時点でも、彼は次のように書いている。
「……何らかの種類の価格体制がなければ、複雑な集産主義社会は必要なガイダンスを得られないということ、そして、そのような社会の一般的枠組内で、ダイナミックな文脈において意味とインセンティヴを持つ価格体制を設立しようとする試みは、集産主義の主要な意図と衝突しやすいというミーゼスの主な主張は、私にとってはいまだに真理であると思われるし、その主張が提出されて以後の全体主義的社会の歴史全体によって支持されているように思われるのである(16)。」
さて、LSEでの二年目も半分ほど過ぎた頃、再びオックスフォードのニュー・カレッジから彼を引き抜く話が持ち掛けられた。今度は、フェローという安定した地位である。あまりためらうことなく、ロビンズはその申し出を受けた。そして、一九二七年の秋、ニュー・カレッジへ移るのである。
ロビンズは、オックスフォード大学自体には、何の愛着もなかったのだが、当時のニュー・カレッジの雰囲気は格別であり、彼は専門分野の異なる研究者たちとの知的交流を続けながら、いっそう経済学の研究と学生の教育に専念したという。彼の言葉を借りるならば、ニュー・カレッジ時代は、彼にとっての無事太平の日々であったのだ(17)。
しかし、その日々も長くは続かなかった。というのは、LSEから彼を教授として呼び戻す人事が進められるようになったからである。LSEは、キャナンの引退の後、アメリカのハーヴァード大学からアリン・ヤング(Allyn Young)を高給をもって引き抜いたのだが、学者としてはともかく、大学の行政官としてのヤングは、あまり有能ではなかったらしく、彼とともにカリキュラムの一新を図ろうとする計画は、一向に進まないでいた。そんな時、ヤングが急死してしまったのだ。
LSE内部は、ロビンズの教授指名に対する賛成および反対で議論が沸騰した。一貫してロビンズを支持したのはドルトンであり、強く反対したのはロビンズとの因縁が深いラスキである。問題となっていたのは、ヤングの講座が例外的な講座であるため、その後任としてロビンズを呼ぶのは不適当だということであった。何せロビンズはまだ若かった。しかし、その問題は、ロビンズについては新しく普通の講座を提供し、ヤングの講座はしばらく空席にするということで解決した。
ニュー・カレッジでのロビンズの活躍がLSEのスタッフの耳にまで到達していたとはいえ、弱冠三十歳のロビンズを教授として呼ぶのに反対があったのは当然であろう。この「事件」は、私にマーシャル(A.Marshall)が自分の後任にピグーを指名したことを思い出させる。ある人が、「若きピグーは、実績ではなく将来性によって教授に任命されたのであった(18)」と述べたように、ロビンズの場合もそうだったと思う。
だが、結果的に考えると、LSEは、その時、賢明な選択をしたと言えるであろう。LSEの近代化は、ロビンズのような若きエネルギーなしには決して進まなかったに違いない。何時の世にもあることだが、彼の教授就任に反対した人たちよりは、彼自身の方がはるかに優れていたことをその後の実績で証明したのだ。
(10)Ibid., p. 73.
(11)Ibid., p. 75.
(12)Ibid., p. 78.
(13)Ibid., p. 81.
(14)Ibid., p. 95.
(15)Ibid., p. 103.
(16)Ibid., p. 107.
(17)Ibid., p. 111.
(18)デイビッド・コラード「A・C・ピグー、一八七七—一九五九」、D・P・オブライエン&J・R・プレスリー編『近代経済学の開拓者』(井上琢智・上宮正一郎・八木紀一郎他訳、昭和堂、一九八六年)所収、一一〇—一一一ページ。