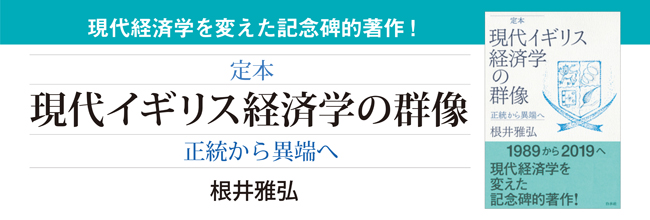根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』立ち読み(4/6)
◇根井雅弘著『定本 現代イギリス経済学の群像——正統から異端へ』より
四 ケインズとの論争と経済計画への関与
一九三二年十月十九日、『タイムズ』紙にロビンズを含むLSEの四教授(Gregory, von Hayek, Plant, そしてRobbins)連名の一通の書簡が掲載された。それは、二日前(十月十七日)の同紙に発表された「大蔵省見解」を批判する書簡(Keynes, Pigou, Macgregor, Layton, Salter, Stamp の連名)にすばやく反応したものであり、ケインズやピグーたちと異なって、不況対策としての政府による借入と支出の増大を特に批判するものであった。
もともと、ロビンズとケインズの間の対立は、彼らが一九三〇年七月二十四日、時のイギリス首相によって「経済諮問会議」の委員に任命された時にまで㴑る。両者の争点は、大きく分けて二つあったが、一つはいま述べた公共投資政策をめぐるものであり、もう一つは輸入統制をめぐるもの(もちろん、ケインズがそれを主張し、ロビンズがそれに反対した)であった。
まず、第一の争点から見ていこう。周知のように、ケインズは、『一般理論』(一九三六年)において、古典派理論全体の基礎を構成している「セイの法則」を論理的に掘り崩すことを主なねらいとしていたが、彼の伝統派理論への不満は、次の文章の中に端的に表明されているように思われる。「現代の考えは、もし人々が彼らの貨幣をある仕方で支出しないならば、それを他の仕方で支出することになるという観念に依然として深く根を下している(39)」と。
ところが、古典派の伝統を受け継いでいる人々の考えの中にも、「これとは反対の傾向や、彼らの以前の見解にあまりにも明白に矛盾する経験的事実が、あまりにも滲み込んでいる」がゆえに、「(第一次大)戦後の経済学者の中でこの立場を整合的に維持することができたものは稀であった」ことも、ケインズは同時に指摘している(40)。しかるに、ロビンズは例外であったという。
「ロビンズ教授は、ほとんどただ一人、整合的な思想体系を維持し続け、彼の実際的な勧告も彼の理論と同じ体系に属しているが、これが彼が異彩を放っている点である(41)。」
ケインズの言いたいことは、つまりこういうことである。等しく公共投資支持といっても、各論者によってその内容には差異がある。たとえば、ピグーが公共投資をあくまで循環的失業の除去のための手段として考えていたのに対して、ケインズはそれを長期的・構造的失業対策として捉えていたというように。だが、ケインズの目には、ピグーが実践の上で主張する公共投資政策は、ピグーの抽象理論から導き出される政策とは矛盾していると映ったのであろう。経済学者の実際的な勧告と彼の支持する理論が整合的な思想体系を維持できなくなったという前のケインズの文章は、そういうことを指しているのである。
しかるに、ロビンズは例外であったという。なぜ彼は公共投資政策に反対したのだろうか。それは、彼も後年書いているように、彼が「論理的首尾一貫性に関しては本質的に根拠がないわけではなかったとしても、当時展開していた状況全体に対しては妥当しなかった理論的建造物の奴隷(42)」であったからだ。妥当しなかった理論とは、もちろん、オーストリア学派の景気理論のことである。
ミーゼスやハイエクによる貨幣的過剰投資論に従えば、つまるところ、恐慌の原因が銀行の信用剏造の助けによって過剰なまでに押し進められた投資に求められるわけだから、その不況から脱出するために赤字財政による大幅な公共投資を図る政策などは、事態をかえって悪化させるだけに終わるであろう。むしろ必要なのは、貯蓄の増大と信用の引き締めである。当時のロビンズは、すでに述べてきたように、ミーゼスやハイエクの思想に深く影響されていたので、この理論に基づいて公共投資に反対したのであった。ロビンズは、自らの立場をさらに敷衍するために、『大不況』(The Great Depression, 1934)という書物まで著した。
今日では、少なくとも一九三〇年代の現実に関するかぎり、ケインズの書いた処方箋の方が正しかったことが、大部分の経済学者によって承認されているが、しかし、ここではロビンズ自身も後にその当時の自分の考えの誤りを率直に認めるようになったことに注目したい。オーストリア学派の景気理論は、当時の経済社会の現実の前に崩壊したのである(43)。ロビンズは言う。
「私は、自分とケインズの間の論争のこの側面を、私の専門的な経歴における最大の誤りであるとつねに見なすであろう。そして、その後、私が自分の態度を正当化するためもあって著した『大不況』という書物を、進んで忘れてもらいたいと思う何物かと見なすであろう(44)。」
研究者が過去における自らの誤りを認めることは、予想する以上に大変な勇気を必要とするものである。だが、ロビンズは、研究者としての知的正直に忠実に果敢にもそれを行なったのだ。私は、いつ頃から、ロビンズがそう考えるようになったのかが知りたくて、かつて彼の書物を幾つか調べてみたことがある。それは、意外にも早く、『平時と戦時における経済問題』(The Economic Problem in Peace and War, 1947)という小さな本——これは、ケンブリッジ大学におけるマーシャル講義をまとめたものである——の中に表明されていることが分かった。彼はそこで次のように述べている。
「配分の機構としての価格体制の長所について、われわれがどのように考えようとも、また相対的需要と相対的供給に関する価格および私的企業体制のいわゆる自動作用について、われわれがどのような見解を持っていようとも、総需要を合理的な一定水準に維持するための道具としては、それがはなはだ重大な限界を有していることは、私にとって全く明らかである。……実際、振り返ってみると、この点は、私が観点の変化をもっとも意識しているところだと思う。もっとも、それは戦争のゆえにそうなったのではなく、むしろ幾分新しい数量的展望に関してテストされた戦前の論争についての熟考の累積的効果のゆえに生じた変化だと思う。……私は、この非常に重要な点において、自分をドグマティックなまどろみから目を覚まさせてくれたことに対して、ケンブリッジの経済学者たち、特にケインズ卿とロバートソン教授のおかげを被っているのである(45)。」
この文章を読んで以来、私はロビンズを尊敬するようになった。しかるに、教科書や論文の中に出てくるロビンズは、相変わらず、あの経済学の定義を提示した者としての彼であり、しかもそれだけの人間である。「名誉の道は非常にせまく、二人並んで通るほどの余裕はない」(シェイクスピア『トロイラスとクレシダ』第三幕第三場、小田島雄志訳、白水uブックス、一九八五年)のだろうか。何度も繰り返すようだが、人間の価値をたった一冊の書物によって判断するのは、重大なる誤りである。ロビンズの生涯が、何よりもそれを証明するであろう。
ケインズとの論争の第二の点に進もう。留意しなければならないのは、この輸入統制をめぐる論争に関しては、ロビンズが最後まで自らの信念を貫いたことである。すなわち、自由貿易に対する確信がそれである。「実のところ、私は、財政的リフレーションに関してケインズに反対したことを後悔しているのと同じくらい、通商の統制に関してケインズに反対したことに満足しているのである(46)」。
ケインズとロビンズは、前に触れたように、「経済諮問会議」の委員に任命されていたのだが、二人の対立はケインズが保護貿易の方向に傾いた提案をするに及んで、さらに悪化していく。ロビンズは、自由貿易に対する堅い信念を持っていたので、収入関税を設けて雇用を増大させようとする提案の中に、「イギリスを偉大なものにした古来の伝統からの離反と、あまりにもかよわい国際主義の若木に対する破壊的な打撃(47)」を見た。対するケインズは、『ニュー・ステーツマン・アンド・ネーション』誌(一九三一年三月七日号)において、イギリスが資力の余裕と一息つく暇を与えられるまで、収入関税が必要なことを強く訴えた。
ロビンズは、ひとたび関税が設けられてしまえば、事態がそれをもはや必要としなくなっても、容易には撤廃できないであろうと判断した(この点、ケインズは、あまりにも楽観的にすぎたと思われるふしがある)。しかし、ケインズは、ロビンズに答えて、次のような自説を展開したのである。
「ロビンズ教授は結論で、「経済的国家主義のさもしい、ささいな方策の利益」のために「国際関係における高い、価値ある理想の利益」を放棄するものとして、私を嘲笑的になじっている。私は、彼が真剣にそう思っているということ、ならびに彼にとっては、他の多くの人々にとってそうであるように、自由貿易は国際間における基本的な理性と品位の旗じるしであり、表徴であるということを知っている。けがれなき自由貿易は、古い忠誠に呼びかけ、われわれの歴史を飾る政治的理性の最も偉大な勝利のひとつを思い起こさせる。これに対して、われわれは過去のわれわれの感覚を現在ならびに将来の感覚よりも、強いものに成長させてはならないとか、表徴のために実体を犠牲にしてはならないとかと主張することは、おそらく、下手なしっぺい返しであるだろう。しかし、私の少なくともいいうることは、私の実践的目標が、国際的な賃金切下げ競争と、それがもたらすべき社会的紛争を除去すること、わが国にわが国のみが一般的利益のために使いうる世界の金融的指導者の地位を取り戻させること、ならびに国際平和への歩みを遅らせ、インドにおけるわが国の政策を中断させるような国内の政治的反応を防止することにある、ということである(48)。」
(『ニュー・ステーツマン・アンド・ネーション』 誌、一九三一年三月二十一日号より)
この保護貿易をめぐる論争は、ケインズとロビンズの間の関係を一時かなり冷たいものにしたことは確かであろう。しかし、後に述べるように、第二次世界大戦中の英・米交渉において、ケインズは戦前の国家主義的傾向から再び自由貿易へ回帰していたので、その時はロビンズと立派に協力して働くことができたのである。二人とも大人だったのであり、両者の対立を強調し過ぎるのは、誤解を招きやすいであろう。
さて、第二次世界大戦が勃発してから、LSEはケンブリッジへ疎開することになった。ケンブリッジで、そこの学生とLSEの学生の合同聴衆に向けて講義するのは、たしかに素晴らしい経験であった。しかし、ロビンズは根っから熱血なのであろうか、ドイツがオランダ・ベルギー・フランスを侵略したというニュースを聞くや、もはやアカデミックな生活が続けられないほど、居ても立ってもいられなくなってしまったのだ。
だから、しばらくして、オースティン・ロビンソン(Austin Robinson)から、War Cabinet の仕事に参加しないかという誘いを受けた時、彼は喜んでそれを引き受けることにしたという。ロビンズの肩書は、Economic Section のDirector(一九四一︱四五)であったが、彼の仕事は戦時経済の管理に係わるものばかりではなく、英・米間の戦後の国際経済再建に向けての交渉にも重要な役割を与えられた。少し前に示唆しておいたように、この分野では、ケインズと密接に協力しながら、その仕事に専念したのである。
詳しくは、ブレトン・ウッズに至るまでの交渉過程を別の書物で補ってもらうしかないが、ケインズの「清算同盟」(Clearing Union)案は、以前の国家主義的傾向から自由貿易への回帰として、ロビンズやロバートソン(Dennis H. Robertson)などによって、広く歓迎されることになった。たとえば、ロバートソンは、ケインズ宛の書簡(一九四一年十一月二十七日付)において、次のように述べている。
「私は昨夜、あなたの改訂された「提案」を非常な感動をもって読みながら遅くまで起きていました——そしてバークやアダム・スミスの精神がふたたび地上に現われるという望みをますます強めました(49)。」
いまや、ケインズとロビンズは、来るべき戦後の国際経済再建のために、一致してアメリカとの交渉に当たることになった。ハロッドは、『ケインズ伝』(The Life of John Maynard Keynes, 1951)において、両者の協力関係を次のように描写している。
「ロビンズ教授はすばらしく練達な交渉者であることが明らかとなり、合衆国で非常な尊敬を受けた。ケインズは彼を頼りにし、彼の判断を尊重するようになった。ロビンズはしばしば調停役を勤めた。ケインズがなにごとかあまりにも鋭くいったとき、ロビンズはすぐに、彼の荘重な、十分筋の通った流暢な言葉で、問題をやや違った観点におき、ケインズのいったことが、違った角度からみれば、アメリカの立場をも具現しているものと見ることができるということを明らかにする用意があった。彼の優雅で均整のとれた言葉と重々しい態度とは、アメリカ側には穏健な哲理と円熟した判断とを反映しているもののように見えた——事実またそうであった。彼の、ケインズ経済学のみならず、一般経済学に関する学識は、彼に大きく役だった(50)。」
われわれは、今日まで、ロビンズとケインズの間の対立の話をあまりにも聞かされ過ぎたのではないだろうか。たしかに、細部における見解の相違は残ったかもしれないが、見解の相違は両者がお互いの才能を尊敬しなかったことを意味するものでは全くない。学問の世界は、本来そうでなければならないはずである。そうでなければ、ロビンズが彼の日記(一九四四年六月二十四日)に、ケインズ賞賛の言葉を綴るわけがないであろう。
「きのう午後われわれはアメリカ側と合同会議を開いた。席上ケインズが国際銀行について説明した。まったく上首尾であった。ケインズの話しぶりは明快で説得的であった。効果は文句のつけようのないものであった。このような場合に私のしばしば考えることは、ケインズがかつてこの世に生を受けた最も非凡な人物のひとりに違いないということである——敏速な論理、鳥のように急降下して飛びかかる直観、生き生きとした想像、とりわけ他の追随をゆるさぬ言葉に対する的確感、これらが結びついて普通の人間の能力の限界を数段越えたなにものかをつくり出す。たしかに、われわれの時代において彼に比肩しうる人物は首相ただひとりである。彼は、もちろん、ケインズを凌駕している。しかし、首相の偉大さはケインズの天才よりははるかに理解しやすいものである。なぜなら、結局、首相の特別の資質は崇高なまでに高められたわれわれ民族の伝統的な資質であるからである。ところが、ケインズの特別の資質はそれらすべての外にあるものである。彼は、たしかに、われわれの生活と言葉の古典的な様式を用いている。しかし、それは、伝統的でないなにものか、純粋の天才というほかはない無比の、この世のものとも思われない性質によって色どられている。アメリカ側は、神のような訪問者が歌い、金色の光がきらめくとき、われを忘れて坐していた。それがすべて終わったとき、論議はきわめてわずかしか出なかった(51)。」
ところで、ロビンズは、こういう政府の仕事に関係しながら、何を学んだのだろうか。思うに、違った世界との接触は、人間が何かを学ぶ絶好のチャンスのはずである。私は、かつてそれを知りたくて、彼の自伝を注意して読んでみたところ、やはりそのことが書いてあった。そこで、その文章を引用して、この節を終わることにしよう。
「私自身の知的・精神的進歩に関するかぎり、公的サーヴィスに従事したこの時期の有益な効果を過大評価することは、私にとって困難であろう。たしかに、私の学問のより技術的な面に関しては、私はその期間に多かれ少なかれそこでの発展との接触を失ってしまった。もっと純粋に分析的な分野においては、私がいま一度完全に安心していられるようになるまでには、それからかなり長い時間が必要であった。つまり、私は、その点では、自分の潜在力が永久に貧弱になったことに何の疑いも持っていない。しかし、ほとんど他のすべての点では、その経験はほとんど純利益を生んだのである。それは、私がその中でそれまであれほど夢中になって集中的に仕事をしてきたかなり狭いアカデミックな雰囲気から、私を引き上げてくれた。それは、私が以前に直面してきた何物ともラディカルに異なった応用の環境の中で、自分の学問の基礎を考え直す機会を与えてくれた。それは、私に政府の機関と実践的な行政のテクニックに関する内密の知識を与えてくれた。それは、多くの新しい接触と幾つかの新しい友情を伴ったし、自分の背景や見解とはしばしば著しく異なるものを持つ官吏やプロフェッショナルな同僚と互いに接して仕事をしなければならなかったために、それは私の同感と理解の範囲を拡大したのである。それは、確かに、私の生涯の中で最も貴重な経験の一つであった(52)。」
(39) J・M・ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』(塩野谷祐一訳、ケインズ全集第七巻、東洋経済新報社、一九八三年)二〇ページ。
(40) 前同、二〇ページ。
(41) 前同、二一ページの注⑶。
(42) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 153.
(43) ジョーン・ロビンソンは、次のような面白い話を紹介している。
「わたくしは、ハイエクがロンドン・スクールにおもむく途中ケンブリッジを訪れたときのことをよく覚えています。ハイエクは、その考え方をくわしく説明し、黒板一杯に幾何学的図形を書いたのです。あとになってわかったことですが、その全体の考え方は、現行の投資率と資本財のストックを混同したものだったのですが、そのときにはわたくしたちは気づかなかったのです。一般的な傾向をみると、不況が消費に起因するということを示していました。R・F・カーンは当時、投資乗数によって貯蓄と投資とが等しくなることを説明しようと試みていたのですが、ハイエクに対してどうしてもわからないといった感じでつぎのように聞いたのです。「あなたの考えでは、もしわたくしがあす新しいオーバーコートを買いにいったとすれば、失業がふえることになるというのですか?」これに対してハイエクは「そうです」と答え、黒板にかかれた幾何学的図形を指していったものです。「その理由を説明するためには、きわめて長い数学的な議論をしなければなりません。」この情けない混乱状態がさきにふれた経済学の第一の危機だったのです。」(Joan Robinson, The Second Crisis of Economic Theory, 1971, in Contributions to Modern Economics, 1978, pp. 2-3. 邦訳「経済学の第二の危機」『中央公論』一九七二年十一月号、八四-八五ページ)
(44) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 154.
(45) Lionel Robbins, The Economic Problem in Peace and War, 1947, pp. 67-68.
(46) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 156.
(47) R・F・ハロッド『ケインズ伝』下巻(塩野谷九十九訳、東洋経済新報社、一九六七年改訳版)四七四ページ。
(48) 前同、四七七-四七八ページに引用されている。
(49) 前同、五八八ページに引用されている。
(50) 前同、六一三ページ。
(51) 前同、六三五ページに引用されている。cf., Robbins, Autobiography of an Economist, p. 193.
(52) Robbins, Autobiography of an Economist, p. 185.