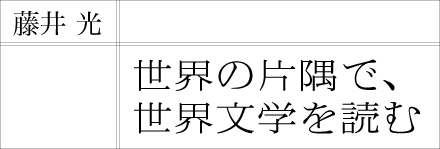第6回 翻訳とオリジナル、ソウルにて
翻訳には「オリジナル」がある。原文を眺めつつ、その言葉を別の言語に移し替えていくのだから、オリジナルがなければ翻訳はできない。当たり前のことかもしれない。
ところが、「オリジナル」と呼ばれる原文が、すでに一種の翻訳のようなものだったとしたら? 母国語ではない言語で小説を書く作家たちの場合、その問いは非常に切実なものになる。
サルバドール・プラセンシアはメキシコ生まれのアメリカ育ち。『紙の民』を英語で書いたが、母国語はスペイン語であり、登場人物も多くはメキシコ出身の移民たちである。しかも彼は、『紙の民』が母国で出版される際に、翻訳者はメキシコ人ではなくスペイン人にしてほしいと依頼している。小説があまりに「自然に」訳されてしまうのが嫌だったからだという。どうやら、彼には英語もスペイン語も、いずれかが特権的なオリジナルであるという発想はないようだ。
プラセンシアも、ブルガリア生まれのミロスラヴ・ペンコヴも、そしてペルー生まれのダニエル・アラルコンも、母国やアメリカを「オリジナル」だとはとらえず、むしろ複数性を拡散させていく。そうした翻訳的な創作のあり方がじわじわと広がっている。
そんな話をするために、僕は5月中旬のソウルに旅をした。東アジアでの翻訳研究をめぐるシンポジウムに参加させてもらったのだ。そこで気がつかされた。世界文学を名乗る文章を書いておきながら、僕は隣人である韓国の翻訳や文学の事情をほとんど知らなかったのだ。我ながら呆れるほかない。とはいえ、そんな空白地帯を少しだけ埋めるきっかけを、その旅ではもらうことができた。
何よりも、英語を東アジアの諸言語に翻訳するときは、「オリジナル」を裏切らざるをえない。その難問が逆に豊かな創作的な翻訳の可能性を生み出していることを、僕はさまざまな形で実感した。
たとえば、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』中国語版の翻訳者の場合、まず考えたのは、ジョイスの造語の数々に対し、新しい漢字を作るという案だったという。表意文字である漢字の可能性に賭けようとしたその一瞬、ジョイスが作り上げた風景はがらりと変わったにちがいない。
あるいは、シェイクスピアの『ハムレット』を韓国の韻文リズムに合わせて訳したという韓国初の試みについて、翻訳者による英韓両方の朗読を味わうこともできた。その翻訳者の方から、「君もシェイクスピアを和歌形式で訳したらどうかね」と 提案されたときは、僕も心地よいパニックに陥ったが……。
とはいえ、自由闊達なエピソードばかりではない。言語間の力関係に直面することも多かった。韓国文学の海外での翻訳は、今までも英語が中心となってきた(その次に多いのが日本語訳である)。そして政府を挙げて現在も取り組んでいるのが、韓国文学の英語訳を継続的に出版することである。グローバル化の波に乗る試みなのだが、そのなかで、母国語での出版と英語での翻訳出版との力関係が逆転しつつあるのでは、とさえ思わされた。
韓国での翻訳の歴史には、もう一つの「オリジナル」があることも忘れてはならない。初期のシェイクスピアの韓国語訳においては、翻訳者が日本の大学で指導を受けていたこともあり、おそらくは英語と日本語訳の双方が参照されていた、と僕は教えてもらった。しかし、どの程度まで日本語訳が使われていたのかは、資料の喪失によって明確には分からないのだという。
翻訳には「オリジナル」がある。ただし、そこに第二の「オリジナル」が亡霊のようにつきまとい、複数性の暴力が出現するときがある。翻訳をめぐる過去と現在が交錯し、僕はまた新しい旅路を見せてもらった。