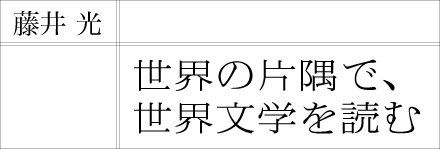第7回 アメリカと死者、「あちら側」の物語
今世紀に入ってもまた、アメリカと世界の関わりからは多くの死者が生まれた。なかでもイラクの地においては、数々の映像によって、死者が漠然とした存在ではなく、「死体」としてそこにあることが白日の下に晒された。イラク人作家による文学にも、その状況は影を落としている。
二〇一〇年に刊行され、作者自身によって英訳されたシナン・アントゥーン(Sinan Antoon)の長篇小説『遺体を清める者』(未訳)は、現代のバグダッドで、埋葬前に遺体を洗い清め、布で包む仕事を代々続けてきた一家の息子を語り手 とする。芸術家を志す主人公の青春の日々が、みずみずしい語り口で描かれていくが、やがて湾岸戦争後の経済制裁、そしてイラク戦争によって、彼の人生は大きく変わっていく。
自爆テロ事件で死者が数十名出たという状況に、どれほど彼が慣れてしまったとしても、洗い清めるときには一人一人の死者と向き合わねばならない。麻薬中毒、アメリカ軍による無差別攻撃、そして頭部だけの死体……。祈りを唱え続けながら死者の体を丹念に清めていく描写には、静謐さと威厳が満ちている。アントゥーンの物語は、死者に尊厳を回復するための試みなのだろう。
それとは全く異なる角度から死者を語るのが、イラクからフィンランドに亡命したハッサン・ブラシム(Hassan Blasim)による短篇小説集、『死体展覧会』(邦訳は白水社より二〇一六年刊行予定)である。冒頭に置かれた表題作は、謎の組織に入会した男に対して、組織の幹部が心得を語るという形式で進行する。その言葉を追ううちに、どうやらその組織は死体を「芸術作品」としてイラクの市街に展示し、その独創性を競っていることが明らかになる。この国には今世紀最大のチャンスが転がっている、とその幹部は言う……。戦争後の混乱において、市街で晒される死体のイメージを、ブラシムは見事な不条理文学として結晶化してみせている。
死者の「価値」を回復しようとするアントゥーンと、死者の「無価値」を最大限に増幅させて読者に突きつけるブラシムの作風は正反対だが、その両者はコインの裏表のようにして、死者に対する倫理という問いを追求している。そして、その背後には、アメリカ合衆国の影がある。
「死者」をめぐってアメリカと他国が対峙する構図は、隣国メキシコとの関係においてはより鮮明かもしれない。国境を挟んだ「あちら側」では、麻薬組織による犯罪が横行し、死者の日という祭日があり、国民的作家フアン・ルルフォの代表作は 死者たちの町を舞台とする『ペドロ・パラモ』なのだ……。かくして、メキシコに「死」を重ねる偏見が醸成される。
それを見事に揺さぶってくれるのが、ユリ・エレーラ(Yuri Herrera)による『世界の終わりの予兆』(未訳)である。メキシコのある村で、タフな若い女性が、弟に手紙を渡すためにアメリカに向かう。村の有力者に話をつけ、彼女は手配された通りに国境を越え、弟の行方を追う。
幻想性が排されているはずのアメリカへの旅は、独特の文体とイメージの絶妙な融合によって、冥界への下降を絶えず喚起する。そしてついに見つけ出した弟は、なんとアメリカ軍の一兵士となっている。彼は軍に入隊した若者の身代わりとなって 死の危険を引き受けているのだ。合衆国を死者の国として幻視するその想像力は、時事的な意義を越えて暗く輝いている。
死者とどう対峙するのか、それは古今東西の文学において根本的な主題の一つだった。今世紀に入っても、その問いは各地で優れた物語を生み出している。その無数の声のなかで、アメリカからの声を考え直すことは、ますます喫緊の課題となっている。