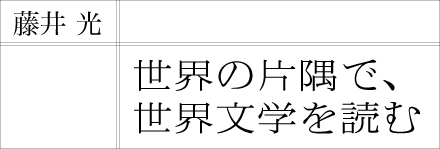第1回 グローバル化におけるダメ男の効能について
「ダメ男」という概念にとって、役割や意義といったものほど縁遠い言葉はないように思えるのだが、それでも、このグローバル化の時代にダメ男が持ちうる意義とは何かを考えさせられる小説が続々と登場している。
グローバル化にともなう「越境」がはらむ禍々しさは、現代文学における一つの軸となってきた。一九九七年の長篇小説Tropic of Orangeにて、カレン・テイ・ヤマシタは国境を越えた臓器売買ビジネスの存在を北米自由貿易協定(NAFTA)の副産物として描いていた。そして、二〇一二年に邦訳が刊行されたロベルト・ボラーニョの傑作長篇『2666』の基底を成す、アメリカとの国境沿いにあるメキシコの架空の街サンタテレサでの連続女性暴行殺人事件は、多国籍企業が安価な労働力を利用すべく建設した製品組立工場を背景としている。
レイプされて殺され、遺棄される女性たちは、NAFTAが作り上げた労働と商品の流れに乗ってサンタテレサに流入した人口の一部を成している。彼女たちを標的とする恐るべき暴力が、グローバル化なしには存在しえないという事実は、越境が日常化した世界とはジェンダーをめぐる暴力を内包した世界でもあるのではないか、という問いを突きつけている。
グローバリゼーションの進行によって世界が平等に近付いていく、などというのは、スターバックス店内とフェイスブック上だけの幻想ではないのか……。そのなかで、「男」はしばしばブラックホールのように、不気味な混沌として現れてくる。今世紀の文学、とりわけ「アメリカ」の内と外を行き来する文学を語るにあたっては、ボラーニョからのこの警告を心しておく必要があるだろう。
それでは、「正しい」男の姿を模索すべきだろうか。だが、そもそも正しい男という言葉にも、どこか歪んだ響きがないだろうか。世界中を旅して正義漢になろうとするも、ことごとく失敗する白人男性を描く、ウィリアム・T・ヴォルマンの旅行記 The Atlas (一九九六年)は、まさにその教訓を与えてはいないだろうか。かくして、ダメ男の出番となる。
かつてのダメ男とは、アウトロー的な背中に哀愁を漂わせつつ、周囲に理解してもらえない不器用なキャラを売り物にしていた、と言えるかもしれない。だが、『2666』を目撃した世紀にはそんな男はそぐわない。それは自分に「酔っている」だけであり、現在のおのれの声によってすべてを覆い尽くす、独善的な暴力と紙一重であるからだ。
むしろ、それとは隔たったところにある「ダメさ」に注目すべきなのだろう。サルバドール・プラセンシアの『紙の民』(二〇一一年)の男たちはいずれも、失恋の痛みに酔い、女性をはじめとする他者を支配しようと試みる。彼らのあがきが挫折に導かれた先に物語が垣間見せてくれるのは、おのれの声が有限であることを受け入れ、多様な声に開かれた自己のありようだった。『2666』に出現した暴力から逃れる、何らかの希望がそこにあるのかもしれない。
失恋の悲しみの「続編」を、まったく違うものとして想像すること。つまりは男の「正しさ」から外れていった先に、何らかの新たな可能性を探ること。それを目指して、プラセンシアは九年を費やして『紙の民』を書き上げたのだし、ジュノ・ディアスは十数年をかけてオスカーとユニオールの物語を紡いでいる。それだけの歳月をかけ、彼らは越境する男たちのなかに潜む支配や暴力への願望をさらけ出し、その先を夢見る物語を鍛え上げた。
つまり……ダメ男とは現在の肯定などではなく、現状に対する厳しい批判をくぐり抜けた先にある、未来の姿なのだと言えるかもしれない。この時代において、そんなダメ男に「なる」ためには、それなりの覚悟というものが必要なのである。