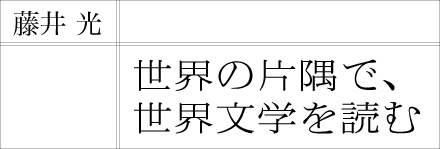第4回 英語と出会う声
二〇一四年の十月、僕は「アラブ文学との対話」というイベントに参加した。現代のアラブ作家を日本に招聘する成蹊大学アジア太平洋研究センターのプログラムに、『デニーロ・ゲーム』のラウィ・ハージが名を連ねていたため、翻訳者の僕も呼んでもらえたのである。
それはとてつもなく貴重な体験だった。国際言語であるアラビア語やイスラーム圏についてほぼ無知なまま「グローバル文学」を語るなど、鏡を前にしてお喋りしているにすぎないのではないか。僕の視野がいかに狭かったのかを痛感した。
ハージの話のなかでも、特に印象深かったエピソードは、ニューヨークに移住したばかりの頃の話だった。彼が暮らしていたのは黒人が多く住む地域であり、その街角ではヒップホップが鳴り響いていた。そこでハージはふと気付く。子どもの頃に暗唱していたアラビア語の詩と、ヒップホップはリズムが非常に似ている。おまけに、どちらも敵を倒して「のし上がる」ということが重要な主題になっている……。こうしてヒップホップに慣れ親しんだことは創作にも生かされているはずだ、と彼は語っていた。
アラビア語詩とニューヨークのヒップホップ。時と場所を隔てたその二つの声が思わぬ出会いを果たし、『デニーロ・ゲーム』という英語の小説に結実する。ある「声」が英語と出会い、そのなかに潜り込む、そんな出来事は、今この瞬間もあちこちで進行しているに違いない。
それとはまた異なる移動から、僕はイスラーム圏からの小説をもう一つ紹介することができた。パキスタン在住のダニヤール・ムイーヌッディーンによる『遠い部屋、遠い奇跡』である。パキスタンの高級官僚にして農場主の父親と、アメリカ人の母親のもとに生まれたムイーヌッディーンは、十代前半までをパキスタンで過ごし、その後はアメリカで教育を受けた。その移動が、一九七〇年代から二十一世紀まで、農場主ハールーニー一族とその使用人たちを描く連作短篇集を生んだ。
農場主だった父親は、使用人たちの人生にまったく無関心なままだった。だが、幼少のころから使用人たちと過ごしたムイーヌッディーン本人は、遠い部屋で展開する彼らの声を物語として描き出してみせた。使用人たちの話すパンジャーブ語と上流階級の言語である英語、二つの世界が混ざり合う、洗練と土着の両面を併せ持つ本が誕生したのだ。
移動する言語という英語の側面に着目し、そこに物語を乗せることで、生き延びようとする声もある。『Gaza Writes Back』(二〇一三年)は、パレスチナに住む書き手による、英語での短篇小説を集めたアンソロジーである。
ガザ・イスラーム大学英文学科の学生や卒業生たちが、この本の主役となる。その多くは以前から、英語によるブログなどを通じて、イスラエルによる封鎖の実態を訴える活動を行っていた。その英語の能力と、大学で英文学やパレスチナ文学を読んで培われた感性が、二十三篇の短篇小説として結実した。自分たちの「声」を封殺されまいとする努力が、こうして英語に登場した。
もちろん、こうした英語での創作は大河の一滴にすぎない。圧倒的な数の物語がアラビア語で書かれているのだから、その紹介がないがしろにされてはならない。英語圏では『Banipal』という雑誌があり、アラブ文学を英語で紹介するという役割を担っているように、アラビア語と日本語を直接つなぐ道は、今まで以上に重要になっている。
それぞれの「声」と英語との出会い。そこでは日々新たなものが生み出されていると同時に、その背後に広がる無数の声の存在が示されてもいる。その両者に耳をすませる技法は一朝一夕には身につかないだろうが、ゆっくりとでも学んでいきたいと僕は思う。