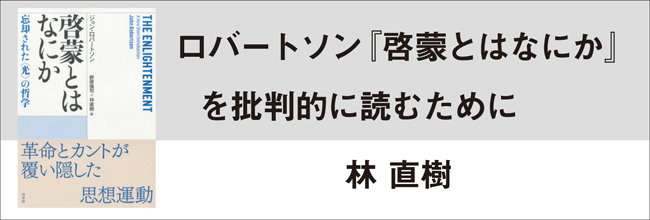【特別寄稿】「ロバートソン『啓蒙とはなにか』を批判的に読むために」林 直樹
ロバートソン『啓蒙とはなにか』第五章では,20世紀に入って「哲学としての啓蒙」に向けられた批判が集中的に検討されている。アドルノ(Theodor Adorno, 1903-69)とホルクハイマー(Max Horkheimer, 1895-1973)の共著『啓蒙の弁証法』(1944年)は,啓蒙哲学がリベラリズムの限界に対処しえないまま知識の再編を追求する過程でテクノロジーと政治の両面における「支配の新手段」を生み落とし,自由の敵をかえって伸長させたと論じた。コゼレック(Reinhart Koselleck, 1923-2006)著『批判と危機』(1959年)では,政治と隔絶した市民社会的道徳哲学とフリーメーソン=秘儀的社交に固執したせいで,「国家の権威」が「市民のあいだの平和にとっての必要条件」となりうる点を啓蒙は見失ったと難じられた。バーリン(Isaiah Berlin, 1909-97)は思想史家として啓蒙の哲学的「外観」を問題視し,啓蒙を過度に普遍的なものとして眺めることの誤りを強調するべく,ヴィーコやヘルダーの思想から文化的多元主義を読み取り,これを「対抗啓蒙」と称して啓蒙に対峙させた。知の考古学を唱えたフーコー(Michel Foucault, 1926-84)は,自然主義的ゆえに安定的とされた啓蒙哲学上の「人間本性」を,思想史上における「気まぐれな変動の産物」程度にしか評価せず,さらに『監獄の誕生』(1975年)では,暗い土牢からの囚人の解放は光の下での新たな支配手段としての自己規律の始まりであると論じることにより,啓蒙の弁証法命題に共鳴しつつ,啓蒙に隠された「権威主義」の芽をえぐり出そうとした。マッキンタイア(Alasdair MacIntyre, 1929-)著『美徳なき時代』(1981年)は中世トマス主義的な形而上学を称揚した反面,倫理の理性主義的正当化を志向した啓蒙は「人を惑わす」と主張している。また,ローティ(Richard Rorty, 1931-2007)に言わせれば道徳律さえもが後期ヴィトゲンシュタイン(Lutwig Wittgenstein, 1889-1951)流の言語論的転回の内にあり,言葉の外にある実在ではない以上,「真実の知識と倫理のための普遍的かつ合理的な準則を見出すことができるとしてきた啓蒙の信念,とりわけカントの信念は誤っている」のだった。
もっとも,フーコーは晩年,「批判」というカント的理念を権威に抗う個人の意志として再評価する動きを見せ(「啓蒙とは何か」1983年),ローティも,哲学上の基礎付け主義に対する批判の先駆を神の役割に対して啓蒙が向けた批判に求めることで,啓蒙との断絶よりも連続をほのめかした。両者は啓蒙の包括的・普遍的理性主義には相変わらず反対したが,「自由」の擁護論としての啓蒙には可能性を見たことになる。
では,ロバートソン自身はいかなる態度をもって啓蒙哲学に対するか。彼は本書において歴史文脈主義的に啓蒙を論じることで,啓蒙時代=近代と現代との連続よりも断絶を強調しているように思える。本書の結びでは「啓蒙の世界と私たちの世界とのあいだには,あまりに多くの人災が横たわっているがゆえにこそ,進歩に向けた,そして人間の境遇改善に向けた啓蒙のコミットメントは,私たちの包容力に対する挑戦ともなりうる」と語られているが,それは,18世紀の語彙で表された概念を安易に現代に適用し,特に「他者」との関係において問題含みだった「近代」ヨーロッパ世界の延長線上に現代世界を据えることへの危惧,つまり,そうした「近代」が革命,ナショナリズム,世界大戦とホロコーストを生み,社会主義論争をこじらせ,環境問題を深刻化させたことへの反省を欠如させることへの警戒を,鋭く反映した言葉であろう。「日本語版への序文」にはより明確にそのことが示されている。「啓蒙の『近代性』を祭り上げ,現代世界での宗教的極論の勃興に対して啓蒙の価値と思想を守ることが我々にとり重要と論じることが,近年のヨーロッパとアメリカでの啓蒙の説明の傾向として存在します。我々はもっと自己批判的であるべきだと私は信じます」。ロバートソンは,本書第二章で啓蒙と宗教との関わりを詳説した際,聖と俗の背反よりも相互作用を強調したギボンに高い評価を与えた。それは,啓蒙の「近代性」を非宗教的・反宗教的な武器として狭義に捉えたうえでアナクロ気味に現代社会へと持ち込み,多様な価値の共生(均衡)状態をかえって脅かしかねない危機を招く近年の啓蒙擁護論の動向に,釘をさすためであろう。穏健な啓蒙と急進的啓蒙を対立させ,後者の所産たる「革命」後の世界と現代との連続(裏返せば「革命」前との断絶)を強調するジョナサン・イスラエルの見解(邦訳として森村敏巳訳『精神の革命』みすず書房,2017年がある)が念頭に置かれているだろうことは,容易に想像される。
ただし,「自己批判的self-critical」であるためには現代において過去を手放しで礼賛する軽挙を犯すべきではないのと同様に,歴史の緯(よこ)糸すなわち共時的文脈の相互独立を言うあまり,歴史の経(たて)糸すなわち通時的文脈の持つ浸透力を過小評価し,過去の失敗を無闇に引き寄せる怠慢を放置することも許されないだろう。フーコーやローティも認めたように,啓蒙をもはや過去のものとしてトータルに否定するべき理由はなく,したがって啓蒙にとっての躓きの石を歴史の中に探し,蹉跌の還帰を防ぐ術を探ることも,もちろんそれによって得た知見の歴史貫通的・無時間的な普遍合理化は戒めるべきだとしても,無意味なことではないと考えられる。ここで一つ気がかりなのが,ロバートソンによる次の一節である。本書の同じく第五章で,先に列挙した20世紀における啓蒙哲学批判の残る一例として最後に触れられているものである。少し長くなるが引用しよう。
啓蒙に向けられた哲学的批判の伝統の累積作用は,説得力の伴う啓蒙擁護論が不足したために確実に強化されたと言ってよい。啓蒙に好意的な解説書として最もよく参照される著作はエルンスト・カッシーラーの『啓蒙主義の哲学』であり,本書はカッシーラーがイングランド,スウェーデン,合衆国へと亡命する前の1932年に,ドイツで出版された。彼は新カント派の一人として啓蒙哲学をカント以前に位置付けたにもかかわらず,啓蒙を支える原理は「理性の自律」にあると見なしていた。ナチズムから逃れたユダヤ人亡命者という身の上にあった彼の啓蒙哲学註解は敬意を払われてしかるべきだと考える人がいてもよかったかもしれない。だが実際はそうならなかった。カッシーラーは1929年のダボスでハイデガーと有名な対決を行って敗れ去ったのだと,当時ほとんどの人は思っていた。ハイデガーはナチに入党していたものの,ローティの人後に落ちないほどの多大な関心を後期ヴィトゲンシュタインに対して抱いていた。アイザイア・バーリンさえもがカッシーラーに批判的だった。『啓蒙主義の哲学』の1951年版の英訳を書評したバーリンは,同書を「うららかにして無邪気」と形容した。本書の著者は,後代に啓蒙哲学を挫折させることになった摩擦や転覆作用の数々に気がついていないと評したのである。
啓蒙史家ゲイ(Peter Gay, 1923-2015)が「繰り返し基礎に回帰するからこそカッシーラーの啓蒙哲学研究は決して時代遅れになどなっていない」「カッシーラーの本はおよそ80年前と同様に新しく,最初に出版されたときと同じく心から愉快に読むことができる」と評した名著『啓蒙主義の哲学』(ゲイの言葉は1951年版の英訳の再版であるThe Philosophy of the Enlightenment, translated by Fritz C. A. Koelln and James P. Pettegrove, Princeton University Press, 2009の序文に所収)の読者の怒りを買うのでは,と思えるほどの,強烈に批判的な言辞が並んでいる。定評を得た書物を,ここまで畳みかけるように否定せねばならないのはなぜか。好評を得ているがゆえに,逆方向に強く押し倒さねば均衡が回復しないというわけだろうか。同書には比較的早くから邦訳が存在する(『啓蒙主義の哲学』紀伊國屋書店,1962年)ものの,訳者の中野好之も「彼[カッシーラー]の理性主義的視角によって果してこの時代の非合理的なもの,主意的なもののもつエネルギーが根本的にとらえられるかという疑念をわれわれに抱かせるかもしれない。…この本に,歴史の恐るべき危機に対する著者の意識が直接には反映していないことによって,人はこの疑念を裏づけることができるかもしれない」(「訳者のあとがき」)と述べており,本書に対する物足りなさをにじませる。だがそれは,啓蒙を論じた者の側の罪なのだろうか。後代の見地からは過失に見えることも,同時代にとっては過大な責任と呼びうる場合がある。その後の悲劇は啓蒙が存在したから生じたのか,それとも啓蒙が存在したにもかかわらず生じたのか。後者が正しいとすれば,再説になるけれども,啓蒙をトータルに否定するのではなく,もちろん限界がありうるにせよ,いかにすれば啓蒙が悲劇を防ぎえたかを,歴史を題材に思考実験を重ねて検証してみる作業も間違いなく有意義であろう。
ちなみに先の引用で「有名な対決」と呼ばれているのは,1929年3月17日から4月6日までスイスのダボスで行われたカッシーラー(Ernst Cassirer, 1874-1945)とハイデガー(Martin Heidegger, 1889-1976)の公開討論のことである。両者は新旧二つの時代をそれぞれ代弁すると評され,討論は広く耳目を集めた。カッシーラーは当時ハンブルク大学哲学教授であり,この後まもなく学長に選出される。それはドイツではユダヤ人として初めての栄誉だった。彼より15歳若いハイデガーは母校フライブルク大学の哲学教授職に前年,就いたばかりであったが,『存在と時間』(1927年)の著者としてすでに有名だった。この討論で前者は後者に「敗れ去ったのだと,当時ほとんどの人は思っていた」とするロバートソンの評言については,この公開討論の出席者が残した記録を少なくとも読んでから再考してみる必要があるだろう。カッシーラー夫人は「論戦は見苦しくない形で展開され」「この討論を概観すると,ハイデガーは学生の間では勝利者となった」と回想しており,両者は互いを知らぬ仲ではなかったがゆえに,若い感性には響いたにせよ後者の完勝とまでは至らなかった様子がうかがえる。また討論記録には英訳Carl H. Hamburg, A Cassirer-Heidegger Seminar, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 25, no. 2, 1964が存在するが,その訳者序文では,ナチ礼賛に傾き,カント主義から明らかに距離をとりつつある聴衆の前で,その動向のまさに「中心kingpin」に位置するハイデガーと正面から議論したカッシーラーの「類稀な哲学的勇気」は疑いようがないと称えられている。デフォー『ロビンソン・クルーソー』の研究でも知られた岩尾龍太郎によるドイツ語原文からの邦訳も参照したい。これは,先に触れた一句を含む「カッシーラー夫人の回想抄」とともに岩尾龍太郎・真知子訳『ダヴォス討論』《リキエスタ》の会(2001年)に収録されている。
『啓蒙主義の哲学』の英訳に対するバーリンの書評(The Historical Review, vol. 68, no. 269, 1953)についても一瞥しておきたい。ロバートソンが引いた「うららかにして無邪気serenely innocent」という言葉は,書評の,ごく短い最終段落中に現れる。訳出しよう。
巧みに編まれ,巧みに翻訳され,うららかにして無邪気。最も尊敬されている思想史家の一人の手になるこの作品は,西洋思想におけるこの重要な時期についての,ビジネスライクな,すなわちもっと有用な(ice-cutting)説明の必要を痛感させる。
カッシーラーの説明に沿って進むだけでは啓蒙が分からないままだから,別の語り手を要するのだと。バーリンは確かに手厳しい。「カッシーラーの傾向は調停し宥めること,将来の中に過去を見て過去の中に将来を見ること,ルネサンスの哲学を,後代の発展,つまり18世紀や19世紀,あまつさえ20世紀の発展がその出発点においてすべて見通せており,ほぼすべて形成済みであったかのように描くこと」すなわち空間の中にも時間の上にも弁別あるいは峻別が足りないとしたうえで,「カッシーラーの一様で穏やかな黄昏の光の中ではすべての形姿がぼんやりと霞み,あまりにたやすく互いに溶け込んでしまう」から,彼は「写真家でもなければ批判的分析家でもなく,慎重な印象派」と呼びうるが,しかしそうした態度は「おそらく他の世紀以上に18世紀には向いていない」とする。次に見るバーリンの言明は,「基礎」への回帰を重んじる業績は時代を超えて色褪せないとしたゲイの肯定的評価とはまるで反対に,あるいはそれを打ち消して余りあるほど強力に,カッシーラーの方法に対し痛烈な一撃を見舞っている。
カッシーラーは,自分自身の仕事が「厳密な一貫性と精確な配置のもとに表された少数の偉大なる基礎的諸思想」を解明することにあるとしている。彼はまた,啓蒙を「皮相shallow」と見る「ロマン主義運動の評決を見直す」手伝いをしたがっている。無益な望みだ。なぜなら,説明は多いが思想は乏しいからである。…[相対的に無名の思想家たちに注意を払い,暗い四隅に見慣れない光を当てようと尽力はするものの]中心的問題は強調されないままである。バウムガルテンの思想を紹介され,この門人,あの弟子が彼のことを比類ないとか不滅だとか考えていたと告げられるが,ではなぜそう考えたのか。その代わりに聞かされるのがゲーテのバウムガルテン評である。ディドロないしルソーが「思想の型を変えた」と告げられるが,この型とやらが正確には何であり,それがいかにして変容したのかが不分明なまま,置いて行かれてしまう。
このような次第だから,カッシーラーの方法とは「明白に知覚されることなど永遠に覚束ない全体」へと各要素を没入させるようなもの,言い換えれば淡々と同じ調子で抵抗なく流れる河の上に舟を浮かべるような牧歌的なものにすぎないとされる。「すべての思想家は彼にとって,大がかりな共同事業に携わる忠実な同僚たちであった。カッシーラーの頁を繰るほどに思想家同士の相違は曖昧になっていった。彼らの間の調和が,地平が広がるにつれどんどん重要性が薄れていく束の間の意見の不一致の多数を覆い隠した」のだと。バーリンの思い描く18世紀とは,これとは逆に「鋭い対立と危機に満ち満ちており」「表層下の神秘主義mysticismと狂信fanaticism,理性主義的で懐疑主義的でロマン主義的かつ宗教的な転覆作用の数々subversive forces, rational, sceptical, romantic-religious」をこそ,見出すべき時空間であった。カッシーラーの時代錯誤を突いたはずのバーリンが18世紀の騒擾を20世紀前半の悲劇に引き比べているように見えるのは,気のせいだろうか。
カッシーラーは差異の中に調和を見るライプニッツ,教会も国家も立てるダランベールを好んだ。むろんカントの普遍主義への信頼がそこには横たわっていただろう。そしてそのことが,差異に隠れる「転覆作用」に対して彼を盲目にした。それ自体としては罪に問えない行いも,差異を分断に,分断を闘争に,闘争を殺戮へと変える時代においては罪深い側面を持つ。宥和が過ぎることは,この流れを止める抵抗力を自ら封じ込める結果を生みかねないからである。ハイデガーとの対決についてバーリンの書評は沈黙しているが,カッシーラーが仮に「敗れ去った」とすれば,敗因は,分断を力に変える狂気の時代において自ずからの連帯を過信したところに求められるべきであろう。
差異を,平和裏に続いていく人間社会と両立する要素とするには,どうすればよいか。共時的にも通時的にも差異を曖昧なまま残すのではなくむしろ明確にしたうえで,各成員のユニークさを「理解」するための能動的アプローチを不断に続けるしか道はないのではないか。ロバートソン『啓蒙とはなにか』にも,次の総括的一節が掲げられている。
私たちは,啓蒙が引き続き問題であると自らに言い聞かせるような真似は行わない方がよいのである。想像力を用いて啓蒙思想家たちの概念言語を再構成するだけで,彼らが出会った諸問題を認知するだけで,そしてそれらの問題に対する彼らの応答のオリジナリティを正当に評価するだけで,私たちは自分自身の思想をより豊かにすると同時に,人間の営為を理解する方法がいかに多様であるかをより深く自覚することができるのだから。それは思想史家たちが探し求める過去の今日性とは異なる。それは,私たちが現在使用しているものとは異なる用語法によっていかに問題が定式化され,処理され,概念化されたかを理解しようとする挑戦にひとしい。
[執筆者略歴]
林直樹(はやし・なおき)
1982年生まれ。2010年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程学修認定退学。博士(経済学)。現在、尾道市立大学経済情報学部准教授。主な著書に『デフォーとイングランド啓蒙』(京都大学学術出版会)他。