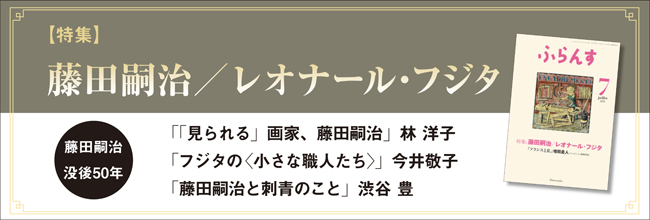特集「藤田嗣治/レオナール・フジタ」
*『ふらんす』2018年7月号から、特集の一部をご紹介します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
80年余りの生涯の半分をフランスで暮らし、晩年はフランス国籍を取得したエコール・ド・パリの寵児。没後50年、史上最大の回顧展を機に、唯一無二の画家の魅力に迫ります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
「「見られる」画家、藤田嗣治」
林洋子
画家・藤田嗣治が1968年1月29日にチューリッヒの病院で亡くなってから、半世紀のときが流れた。戦後、1949年3月10日に羽田空港から離日し、その後一度も母国の土を踏まずに欧州の土に還った。1950年2月にパリに戻る前に10か月ほどニューヨークで過ごしたが、約40年近いフランス暮らし── 1910、20年代のモンパルナス、1950年代もモンパルナス、60年代はパリ南郊のヴィリエ=ル=バクル──にもかかわらず、病院の関係でいつも、スイスで逝去と表記されるのが気の毒である。明治半ばの東京に生まれ、満81歳で亡くなった際、彼は「フランス国籍」「カトリック教徒」となっていた。墓所は、北フランス、ランスに自ら建立した小さな礼拝堂「ノートル= ダム・ド・ラペ」である。戦後、あれほど古い、19世紀的なパリを求めて描き続けた藤田が、奇しくも今年50周年というパリ五月革命より前にこの世を去り、破壊される街を見ずに済んだことに少しだけほっとする。
この画家がパリに初めて来たのは1913年の夏で、26歳。パリに到着して1年後には第一次世界大戦が勃発し、多くの在留邦人が帰国するなか、欧州残留を決め、家族からの送金が途絶える中、自分で整えられる髪型、おかっぱ頭にする。そして丸眼鏡。生前の写真や絵画を見る限り、相当数持っていて、眼鏡おしゃれの元祖といっていいだろう。だが、年来、遺品に眼鏡が見つからなかった。1990年代に君代夫人が晩年の住まいを地元エソンヌ県に寄贈し、2000年から一般公開されている記念館「メゾン・アトリエ・フジタ」に確認しても、遺族や関係者から帽子、靴や藤田手製の服、勲章類、パスポートは寄贈されていても、なぜか眼鏡はなかった。日本人はお棺に、来世でもよく見えるようにと眼鏡をよく入れると伝えたら、先方の学芸員は驚いていた。近年、思いがけず、戦後の藤田のコレクターの収集品のなかにひとつ見つかった。強い近視で、生涯眼鏡を手放すことがなかった藤田にたったひとつなのも不思議だが、その眼鏡を手に取って、あらためてこのフレームとレンズを通して、彼はモティーフを、自らの作品を、そして世界を見ていたのかと感慨深かった。もちろん、彼は画家として一般の誰よりものを、ひとを凝視していたし、最期を看取った君代夫人によれば、視覚情報の記憶力が半端でなく、一度会っただけのひとの顔をさらさらと似顔絵にしてプレゼントすることもしばしばだったという。
そんな藤田だが、「見る」だけの存在でなく、1910年代半ばから髪型やピアスなどによって自らをアイコン化し、さらにその姿を自画像として展覧会に出品することで、当人と自画像が相乗効果でその存在を幅広く認知させていった。自ら広告塔となって、異国の美術界を泳ぎきったのである。だからこそ、わたしが1990年代初めに藤田について研究し始めたころ、いろいろな方が藤田を「見た」思い出を問わず語りに聞かせてくださった。その多くが、1950年代のパリ滞在経験をお持ちだった。ふた回り年少だった君代夫人が百歳を目前に亡くなったのが2009年(彼女もまた、50年代以降のパリを知る、藤田最大の「観察者」だったが)。この約10年間でこの世を去られた方も多く、もっと話をうかがっておけばよかった、録音録画しておけばと思ってもあとの祭りだ。目下、この7月末から始まる没後50年記念展の準備をしながら、そうした人たちのお顔が脳裏をよぎることも多い。
今から思えば、この画家との出会いは1980年代末のパリだった。学生時代に語学研修に出かけた際、短い時間をパリ国際大学都市の日本館(メゾン・デュ・ジャポン)で過ごした。フランスの美術家を研究したいと思って語学研修と美術館めぐりを兼ねたパリ滞在だったが、そこで藤田にからめとられた、とりつかれた。当時は不思議な金箔地の裸体群像《欧人日本へ到来の図》があると思いつつ、その前で卓球をしたりしたにすぎない。ただ、日本で考えていた藤田(たとえば大原美術館の《舞踏会の前》のような乳白色地)とは違った印象で、どうしてこのような作家が20世紀前半のパリで成功を収めたといわれているのだろうという、素朴な疑問が始まりだった。その後、この作品は2000年の修復事業で関わることになる。この事業は、当時幅広く募金活動し、かつて日本館にお住まいになった方々にも募金依頼をしたので、本誌の読者にもご記憶の方もあるだろう。
この修復事業を支えてくださったのが、恩師でもある高階秀爾先生と、日本画家の平山郁夫先生だった。[…]
(続きは『ふらんす』2018年7月号をご覧ください)
(はやし・ようこ/美術史家。文化庁芸術文化調査官。著書『藤田嗣治 作品をひらく』『藤田嗣治 手紙の森へ』)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
「フジタの〈小さな職人たち〉」
今井敬子
[…]昨年より、本誌の表紙を飾るフジタの絵画〈小さな職人たち〉について、連載する機会をいただいている。手のひらに収まるほどの小さな板絵のシリーズは、50年前にフジタが亡くなると君代夫人に遺贈され、そののち、このシリーズの約8割にあたる95点が、私の勤務するポーラ美術館に段階的に収められることになった。コレクションの発端は、2002年の美術館の創設以前にさかのぼり、ポーラ化粧品メーカーのポーラ創業家二代目であったコレクターの鈴木常司(1930-2000)が、この可愛らしい作品群に魅せられて蒐集を始めたことにある。
画商の計らいで、この作品はそれぞれ金箔張りの凝ったデコレーション付きの額装が施され、コレクターの手元に届けられた。私がこの作品群と初めて対面した時も、子どもたちのポートレートはその額の中に収められていた。下町生まれのやんちゃな子のお仕着せ姿に出くわしたようで、それは気まずい出あいであった。ともあれこれらの細密画を覗きこむと、その丁寧な仕上げに反して、四隅に釘の穴がぞんざいに開けられていることが気になった。それは穏やかな老境を過ごす男性の耳たぶに、10 代の頃に手荒に開けたとおぼしきピアスの穴を見つけた時の感覚に喩えられようか。彼らには、今とは遠く異なる地での過去があったのだ。その忘れえぬ証拠として、体の一端に古い傷を残しているのである。
かつて〈小さな職人たち〉はその主人の手で生み出され、その住処をこの壁に定められた。フジタが君代夫人との生活を彩るためにこれらをコツコツと描きため、配置を幾度となく変更しながら、二人でこのサロンの壁に釘打ちして完成させた大壁画である。
2枚の扉の間に設置された〈小さな職人たち〉のシリーズは、1点の大きさが約15センチメートル四方で、横幅3メートル、高さ90センチの面に、合計115枚ほどの子どもの図が合わされている。フジタいわく、「九谷風」の文様を描いた装飾板を作り、子どもたちの百態図を囲み、壁面を埋めた。文様板の数は、この写真に写る範囲だけでも200枚以上に上る。これらをすべて装飾とみなしてのことか、この壁には夫妻の大切にする絵画が上に重ねて掛けられた。この壁の一帯は、十字架と祭壇画が安置された祭室のように構想されている。〈小さな職人たち〉は、さしずめ「プティ・メティエ」を奉ずるパリ下町界隈の小さな守護聖人たちの図像といえよう。夫婦はここで語らい、客人をもてなした。
この装飾壁が完成して以来、フジタが取材者に請われて肖像写真に収まる時は、この壁を背景にすることを選んだようである。女性像や少女像など、美術市場で人気の集まった絵の新作を自らの隣に置くことはなかった。昨今の記者会見に必須となったロゴの並んだボードのごとく、フジタが〈小さな職人たち〉の前に立つモノクロームとカラーのポートレート写真が何枚か残されている。それは、「職人(アルティザン)フジタ」を表明するステートメントにほかならない。
フジタ夫妻は、この写真の撮影時にはすでにパリ郊外への移住計画を進めており、1961年にはこの部屋を後にすることになる。そしてフジタの歿後、壁から離されたこの作品群は、主人との繫がりとも絶たれて、現在はポーラ美術館のコレクションに入るほか、所在不詳の絵画も数点ある。四隅の釘穴が、再び塞がれることはない。[…]
(いまい・けいこ/ポーラ美術館学芸課長)
(続きは『ふらんす』2018年7月号をご覧ください)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
「藤田嗣治と刺青のこと」
渋谷豊
明治の世に、欧米で日本の芸術といえば、たぶん浮世絵の次の次くらいに刺青が来た。日本の彫師たちの腕が評判を呼んでいたのだ。中でも人気だったのは伝説的な彫師、彫千代だが、藤田嗣治はその彫千代の刺青の見本帳を所有していたという。
刺青に対する藤田の関心は通り一遍のものではなかった。ときには実際に針を手に取ったし、彼自身、左腕に時計の刺青を入れている。キャンバスに乳白色の肌を描くことと、肌をキャンバスにして絵を描くこととに、何か相通じるものを感じていたのかもしれない。ただし、刺青はその所有者とともに消え去る運命にある。そこが普通の絵と違う。刺青とは花火のように儚いものなのだ(仮に皮膚を剝いで保存したとしても、肌の紅潮とともに色づき、筋肉の動きにつれて姿を変える刺青の「命」は失われる他はない)。藤田がシュルレアリストの詩人、ロベール・デスノスの体に入れた刺青も今はもうない。ひょっとすると写真くらいは残されているのかもしれないが、残念ながら私は見たことがない。だから、幾人かの証言を手掛かりに「失われた作品」に思いを馳せることしかできないのだが、それが存外、楽しかったりもする。
デスノスが藤田とユキ(藤田の3人目の妻。本名リュシー)の前に現れたのは1928年のことだ。それからしばらく3人の奇妙な三角関係が続くことになる。男2人でユキを争った格好だが、実は藤田とデスノスはけっこう馬が合った。芸術上のシンパシーも働いていたようだ。実際、藤田はこの頃シュルレアリスム風の絵を何点か描いているし、デスノスはその内の一つ「女猛獣使いとライオン」に想を得て「美しい猛獣使い」という詩を書いている。「美しい猛獣使いは娘っ子/御年はたちの娘っ子//アトラス山脈のライオンは……」で始まる軽妙な詩だ。
藤田がユキとデスノスに刺青を彫ったのはその頃だ。後にユキは「彼、とっても上手なの」と藤田の腕を讃えたが、針の痛みは生半可ではなかったらしい。晩年のデスノスと親交のあったドミニク・デザンティによると、藤田がユキの太腿に人魚を彫っている間、ユキは阿片とコニャックで痛みを紛らしていたそうだ。一方、デスノスは敢然としらふで挑んだ。その結果、「星が鏤(ちりば)められた幅広いペナントと、後脚で立った一頭の大きな牝熊」がデスノスの「腕」を飾ったのだという。少なくともユキの回想記にはそう書いてある。デザンティによれば、より正確には「左腕の内側」だったらしい。[…]
(しぶや・ゆたか/信州大学教授。訳書ボーヴ『ぼくのともだち』『のけ者』、サン=テグジュペリ『人間の大地』)
(続きは『ふらんす』2018年7月号をご覧ください)
*『ふらんす』2018年7月号では、林洋子さん、今井敬子さん、渋谷豊さんの寄稿の全文を掲載しています。ぜひあわせてご覧ください。
◇藤田嗣治没後50年・関連イベント
>「没後50年 藤田嗣治展」@東京都美術館
>歿後50年記念特別展示「フジタからの贈りもの─新収蔵作品を中心に」@ポーラ美術館
>シンポジウム「藤田嗣治、再訪─没後50年」